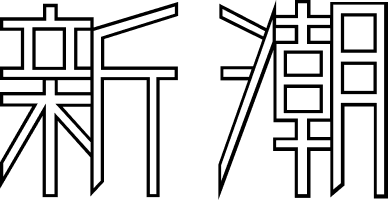ビタミンF
1,650円(税込)
発売日:2000/08/22
- 書籍
山本周五郎賞作家が放つ家族小説の最高傑作! あなたに元気を運ぶ短篇集です。
「ビタミンF」は、家族を元気にする“読むビタミン”。息子が理想通りに育たなかったり、娘に突然カレシができたり、夫婦の仲に危機が訪れたり……それぞれの形で“黄金期”を過ぎようとしている七つの家族は、次の季節をどんな表情で迎えるのか。夏バテに効く、感動の家族小説集です。
書誌情報
| 読み仮名 | ビタミンエフ |
|---|---|
| 発行形態 | 書籍 |
| 判型 | 四六判 |
| 頁数 | 296ページ |
| ISBN | 978-4-10-407503-4 |
| C-CODE | 0093 |
| ジャンル | 文芸作品、文学賞受賞作家 |
| 定価 | 1,650円 |
書評
波 2000年8月号より 「パパになった新人類」の物語 重松清『ビタミンF』
重松清の欠点は、ときとして上手すぎる点である。その気になれば何でも書けてしまうだろう職人芸を駆使すれば、あなたはサマセット・モーム? それともオー・ヘンリー? というような短編小説を量産することだって、できちゃうはずだ。いわゆる「大向こうをうならせる」ってやつですね。
しかし、最新刊『ビタミンF』に収められた短編は、彼のそのような器用さとは、ちょっと別のところで書かれているような気がした。設定とフィニッシュの鮮やかさで読ませる「いよっ、お見事!」な短編もないわけではないけれど(たとえば、別れた恋人と泊まったホテルを十七年ぶりに訪れる『なぎさホテルにて』)、全体のトーンはもっと鈍臭い。べつにいえば優しい。エンターテインメントとしての質が低いという意味では、もちろんない。こういう題材は切れ味で勝負したところで嘘臭くなるばかり。そのことを作者はよく知っているのだと思う。
ひと言でいえば、『ビタミンF』は、いまどきの家族、とりわけ影が薄いといわれて久しいお父さんたちを描いた短編集だ。七編の主人公は、みな「あなたに似た人」と形容しうる三十代後半~四十代の中年男性である。住んでいるのは、東京郊外のニュータウン。彼らは夫であり父であると同時に、家庭の外ではトラブルに日々頭を悩ませる会社員であり上司である。小説の主人公にはあまりならないような人たち、といってもいい。
しかし、ここが肝心、作者は彼らにちゃんと歴史を背負わせている。この世代は、子どものころに「ウルトラマン」や「宇宙戦艦ヤマト」に熱狂し、若いころには「新人類」と呼ばれ、元気のよかった二十代でバブル景気を経験し、いまや不景気の真っただ中で、小中高校生に育った娘や息子とどう対面したらいいか戸惑っている、そういう世代なのである。「新人類」上がりの父と、「どうして人を殺しちゃいけないの?」ってな台詞で大人の度肝を抜く「新々人類」の子どもたち。そんな親子が、のっぺりとしたニュータウンで暮らしている。ゾッとしない? しかし、それが二十世紀末の日本のリアルな家族像なのだ。
かかる現実を踏まえた七つの短編は、家族間、世代間のディスコミュニケーションを共通のテーマにしている、といえるかもしれない。じっさい、本書の登場人物は、みな、お互いの距離を計りながら、衝突を避けて暮らしているように見える。
自分がクラスでいじめられていることを両親に打ち明けられず、架空の級友にかこつけて〈「みんな、セッちゃんのこと、いじめてるわけじゃないよ。嫌ってるだけだもん」〉と自虐的な強がり方をする中学生の娘(『セッちゃん』)。不良っぽい少年と付き合っているらしい思春期の娘に気を揉みつつも〈「プラトニックなのか」〉なんて間の抜けた質問の仕方しかできない堅物の父(『パンドラ』)。気弱な息子や部下をふがいないと感じながら、じつは自分も親の期待を裏切ってきたのではないかと気づく係長(『はずれくじ』)。沈着冷静な理想の父親をやってきたつもりだったのに、娘が〈お父さんにはなにも言わないで〉といっていると妻に聞かされ愕然とする父(『かさぶたまぶた』)。
「日常」以上「事件」未満とでもいうか、いずれもありふれた家族の風景である。子どもたちはみな問題の火種を抱えているが、新聞沙汰になりそうな事件には発展しない。父も父で、おばさん化した妻にふっと倦怠を感じ、昔の恋人を思い出して「自分にはべつの人生もあったかもしれない」なんて妄想にふけったりはするものの、いきなり派手な不倫に走るほどの度胸はない。みんな小心。みんな不器用。彼らは、大声で怒鳴りあうこともないかわり、抱きあって涙を流すような和解もない。作者は、そんな家族を美化も特化もせず、悲劇にも喜劇にもせず、世間話でもするように、淡々と描いていくのだ。
やや大袈裟にいうと、明治以来の日本文学は、息子が家長である父を乗り越える物語として成り立ってきた側面がある。しかし、厳父の物語はもう通用しない。「父性の復権」を主張する人たちの言説が虚しく聞こえるのは、現代の迷える父親像を彼らがつかみそこねているからだ。逆にいうと、『ビタミンF』のようなところからしか、父親問題ははじまらないのである。だからこそ、読者は随所でドキッとし、ホロリとし、あるいは苦笑するにちがいない。なんだよ、これはウチの話みたいじゃないか、と思うはずだから。
ディスコミュニケーションの物語といったけれども、作者は各編の結末を希望的な予感で締めくくっている。コミュニケーションの糸口は必ずある、という同世代へのメッセージがここには込められているようだ。重松清の小説を読んでいて感じるのは、ある種の実用性である。役に立つ小説というのは、あってよいし、あるべきなのだ。観客ではなく当事者のための短編集。なるほど、だからビタミンなんだね。
▼重松清『ビタミンF』は、八月刊
しかし、最新刊『ビタミンF』に収められた短編は、彼のそのような器用さとは、ちょっと別のところで書かれているような気がした。設定とフィニッシュの鮮やかさで読ませる「いよっ、お見事!」な短編もないわけではないけれど(たとえば、別れた恋人と泊まったホテルを十七年ぶりに訪れる『なぎさホテルにて』)、全体のトーンはもっと鈍臭い。べつにいえば優しい。エンターテインメントとしての質が低いという意味では、もちろんない。こういう題材は切れ味で勝負したところで嘘臭くなるばかり。そのことを作者はよく知っているのだと思う。
ひと言でいえば、『ビタミンF』は、いまどきの家族、とりわけ影が薄いといわれて久しいお父さんたちを描いた短編集だ。七編の主人公は、みな「あなたに似た人」と形容しうる三十代後半~四十代の中年男性である。住んでいるのは、東京郊外のニュータウン。彼らは夫であり父であると同時に、家庭の外ではトラブルに日々頭を悩ませる会社員であり上司である。小説の主人公にはあまりならないような人たち、といってもいい。
しかし、ここが肝心、作者は彼らにちゃんと歴史を背負わせている。この世代は、子どものころに「ウルトラマン」や「宇宙戦艦ヤマト」に熱狂し、若いころには「新人類」と呼ばれ、元気のよかった二十代でバブル景気を経験し、いまや不景気の真っただ中で、小中高校生に育った娘や息子とどう対面したらいいか戸惑っている、そういう世代なのである。「新人類」上がりの父と、「どうして人を殺しちゃいけないの?」ってな台詞で大人の度肝を抜く「新々人類」の子どもたち。そんな親子が、のっぺりとしたニュータウンで暮らしている。ゾッとしない? しかし、それが二十世紀末の日本のリアルな家族像なのだ。
かかる現実を踏まえた七つの短編は、家族間、世代間のディスコミュニケーションを共通のテーマにしている、といえるかもしれない。じっさい、本書の登場人物は、みな、お互いの距離を計りながら、衝突を避けて暮らしているように見える。
自分がクラスでいじめられていることを両親に打ち明けられず、架空の級友にかこつけて〈「みんな、セッちゃんのこと、いじめてるわけじゃないよ。嫌ってるだけだもん」〉と自虐的な強がり方をする中学生の娘(『セッちゃん』)。不良っぽい少年と付き合っているらしい思春期の娘に気を揉みつつも〈「プラトニックなのか」〉なんて間の抜けた質問の仕方しかできない堅物の父(『パンドラ』)。気弱な息子や部下をふがいないと感じながら、じつは自分も親の期待を裏切ってきたのではないかと気づく係長(『はずれくじ』)。沈着冷静な理想の父親をやってきたつもりだったのに、娘が〈お父さんにはなにも言わないで〉といっていると妻に聞かされ愕然とする父(『かさぶたまぶた』)。
「日常」以上「事件」未満とでもいうか、いずれもありふれた家族の風景である。子どもたちはみな問題の火種を抱えているが、新聞沙汰になりそうな事件には発展しない。父も父で、おばさん化した妻にふっと倦怠を感じ、昔の恋人を思い出して「自分にはべつの人生もあったかもしれない」なんて妄想にふけったりはするものの、いきなり派手な不倫に走るほどの度胸はない。みんな小心。みんな不器用。彼らは、大声で怒鳴りあうこともないかわり、抱きあって涙を流すような和解もない。作者は、そんな家族を美化も特化もせず、悲劇にも喜劇にもせず、世間話でもするように、淡々と描いていくのだ。
やや大袈裟にいうと、明治以来の日本文学は、息子が家長である父を乗り越える物語として成り立ってきた側面がある。しかし、厳父の物語はもう通用しない。「父性の復権」を主張する人たちの言説が虚しく聞こえるのは、現代の迷える父親像を彼らがつかみそこねているからだ。逆にいうと、『ビタミンF』のようなところからしか、父親問題ははじまらないのである。だからこそ、読者は随所でドキッとし、ホロリとし、あるいは苦笑するにちがいない。なんだよ、これはウチの話みたいじゃないか、と思うはずだから。
ディスコミュニケーションの物語といったけれども、作者は各編の結末を希望的な予感で締めくくっている。コミュニケーションの糸口は必ずある、という同世代へのメッセージがここには込められているようだ。重松清の小説を読んでいて感じるのは、ある種の実用性である。役に立つ小説というのは、あってよいし、あるべきなのだ。観客ではなく当事者のための短編集。なるほど、だからビタミンなんだね。
(さいとう・みなこ 文芸評論家)
▼重松清『ビタミンF』は、八月刊
著者プロフィール
重松清
シゲマツ・キヨシ
1963(昭和38)年、岡山県生れ。出版社勤務を経て執筆活動に入る。1991(平成3)年『ビフォア・ラン』でデビュー。1999年『ナイフ』で坪田譲治文学賞、同年『エイジ』で山本周五郎賞を受賞。2001年『ビタミンF』で直木賞、2010年『十字架』で吉川英治文学賞、2014年『ゼツメツ少年』で毎日出版文化賞を受賞。現代の家族を描くことを大きなテーマとし、話題作を次々に発表している。著書は他に、『流星ワゴン』『疾走』『その日のまえに』『きみの友だち』『カシオペアの丘で』『青い鳥』『くちぶえ番長』『せんせい。』『とんび』『ステップ』『かあちゃん』『ポニーテール』『また次の春へ』『赤ヘル1975』『一人っ子同盟』『どんまい』『木曜日の子ども』『ひこばえ』『ハレルヤ!』『おくることば』など多数。
判型違い(文庫)
この本へのご意見・ご感想をお待ちしております。
感想を送る