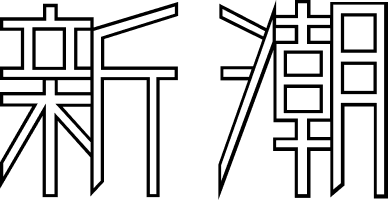第一章 息子達
誰もいない世界
スーパーマーケットにいる夢を見た。
暗い床に食品の陳列棚が並んでいる。人の姿はどこにもない。
脳の記憶がオレンジの姿を浮かび上がらせる。食品棚には暗いオレンジが山積みになっている。葉の付いた暗いパイナップルも山積みになっている。
ひっそりとした黒いアボカドの山。ほうれん草の束。食べられる物がなにもない。通路の両側には食品がいくらでも陳列されているのだが、調理の方法が分からない。
すぐに食べられる弁当やおにぎり、サンドイッチやカップラーメン、ポテトチップスがあればいいのにと思うが、あるはずのものが見つからない。その代わりに、トマトや泥付きのよく分からない根菜らしきものがある。
暗い山積みのトマトを見て、「コンビニじゃないんだ」と思う。
「コンビニだったらいいのに、コンビニってどこにあるんだろう?」と、人のいないスーパーマーケットの広い店内で思う。
スーパーマーケットを出ると夜だった。歩道には灯が点り、ビルが建ち並んで、様々な店の看板がビルの壁面や歩道の脇を埋めているが、広い車道には車の姿が一つもない。
車道は、黒く大きな川のように音もなく続いているが、その向こう側はよく分からない。
ふと見ると、歩道の街灯の下に人の姿がある。暗い影のようになった男は、こちらの様子を窺うでもなく、なにを見るでもなく、ただ立っている。
よく見るとそこはバスの停留所で、停留所の柱に打ちつけられた時刻表の板に体を半分隠すようにして、暗い影のような男はただ立っている。「バスを待っているんだ」と思うと、ビルの際に寄せて立てられている看板の陰にも、男が一人立っている。
路地に入るビルの角には地階の店に続く階段があって、その階段の途中にも男が立って、体を半分覗かせている。
気がつけば、電柱の陰にも他の看板の陰にも、ビルの入口の壁の陰にも男が立っている。服装からは男だと分かるが、顔は影になって見えない。
男達はなにをするでもなく、ただぼんやりと立っている。不思議に、恐怖感はない。害のない者がただ立っている。
「なぜ害がないと分かるのだろう?」と思った時、自分もまた夜の歩道にぼんやりと立っていた。
六十二歳の
五十二歳の
そばには誰もいなかった。カーテンを閉めた窓の外は明るくて、首周りに汗をかいているのを感じた時、外の生活音が聞こえた。遠くに車が走るような音がして、布団の中で感じる日の光は、それ自体が騒がしかった。上半身だけを起こして、掛け布団の端を掴んでギュッと目を閉じ、それを開くことを何度か繰り返した。目の奥の疲れが取れなくて、その重さに引きずられるようにして湿った布団の中に再び倒れ込んだ。
四十二歳の
声を出せば夢に呑み込まれないように思った。自分を落ち着かせるために、何度か大きく息を吐いた。ベッド際のリモコンを取ってテレビを点けた。
女性アナウンサーがなにかを喋っていて、いきなりの光の量がつらくて目を閉じ、「俺も年かな」と思った。閉じた目を半分開けると、ベッドの上掛けをめくってトイレに立った。トイレから戻ってベッドの端に腰を下ろすと、テレビの画面が眩しいのでリモコンのボタンで消した。暗い中でぼんやり座っていると別れた妻の顔が浮かんで来そうなので、目を瞑ってまたベッドの中に潜り込んだ。
三十二歳の
夢の中の男達が害のない存在だということは分かる。しかし、こわい。何人もの男に見られている、そのことがこわい。目を覚まさないと、ぼんやりと夜の道に立っている男達が近づいて来るような気がして、目を覚ました。自分の中の自分に体を揺さぶられるような気がして、目が覚めた。心臓の動悸は、その名残りのようなものだった。
部屋の中は暗く、夢生は「自分は闇の中にいる」と思ったが、胸の鼓動が落ち着くに従って、まだ夜なのだということが分かって来て、眠りに落ちた。
二十二歳の
部屋の中は暗いままだが、時刻は朝になりかけていた。起きるには早過ぎる時間だったが、目覚めてしまった凪生はベッドを出て、部屋の明かりを点けた。ベッドの端に腰を下ろして、凪生は「なんだってあんな夢を見たんだろう?」と、自分の見た夢を振り返った。
「なんで僕はカップラーメンなんかを探すんだろう?」と、料理が出来なくはない凪生は思った。「なんで僕はスーパーマーケットに行って、わざわざカップラーメンを探すんだろう?」
凪生の頭の中には、カップラーメンのパッケージがはっきり像となって残っている。カップラーメンなら、母親がいつも適当に見つくろって買い置きをしているから、凪生自身がわざわざスーパーマーケットまで探しに行かなければならない理由はない。「なんだろう?」と思ってしばらくそのままぼんやりしていて、またベッドの上に寝転がった。「そう言えば、僕はあんまりコンビニにも行かないな」と思っている内、意識が遠のいて明かりの点いたままの部屋で眠ってしまった。夜の街に男達がぼんやりと立っていたことなど印象に残らず、凪生の頭脳は夜の闇だけを見せた。
十二歳の
凡生は、夢の中にいた男の一人に手招きをされていたような気がした。「あれは誰かな?」と、見たばかりの夢を振り返った。
「誰なんだろう? お父さんじゃないけど、誰なんだろう?」と思いながらベッドを出た。朝の起きるべき時間だった。
昭生
昭生の父親は大正の末近くに生まれた。昭和の生まれではない。
小作農の次男だった彼は、小学校を卒業すると村を出て、町の井戸掘り職人の弟子になった。二二六事件の起こった年だった。地主に農地を借りて耕作をする貧しい小作人の家にも家督はあって、それは長男の兄に譲らなければならない。一度家を出てしまえば、生まれた家は胸の中だけに残る「生家」となって、帰るべき「家」はなくなる。まだ井戸水が生活の中心にあった時代、昭生の父は井戸掘り職人として独立する道を選んだ。
時代と共に戦時色は強くなり、その中で成長する昭生の父は、召集で陸軍に入り、終戦で親方の家に戻った。
入隊前、一人前の井戸掘り職人になりかかっていた彼は、軍隊で新しい時代の情報を得ていた。同じ隊にいた年上で妻子持ちの男は、水道工事の職人だった。昭生の父が「自分は井戸屋だ」と言うと、その男は「井戸屋はもう古いな」と言って、水道屋であることを明かした。「水道は、蛇口をひねればすぐ水が出て、井戸を浚う必要もないから、便利で衛生的だ」と言った。それから、「夏は水が温くなり、冬の寒さで水道管が凍結する恐れがある」とは言わずに、「水道工事は役所の仕事だから食いっぱぐれがない」と言った。「食いっぱぐれのない役所の仕事」という言葉が、希望のない軍隊生活の中で夢にも等しい将来への指針となった。
(続きは本誌でお楽しみください。)