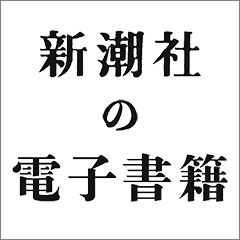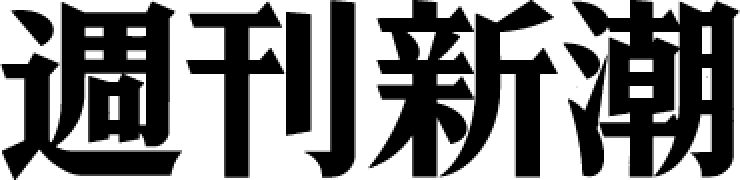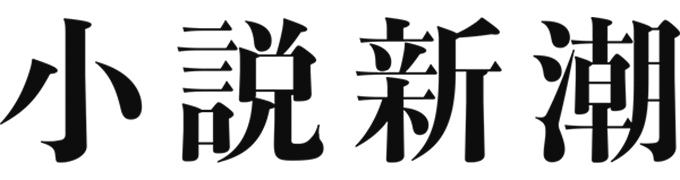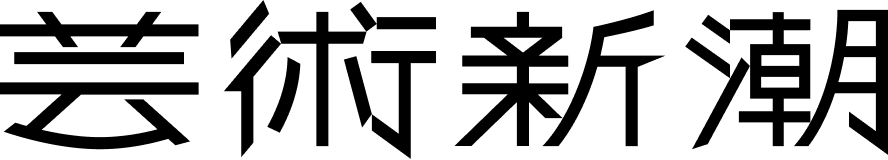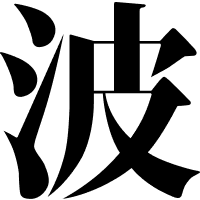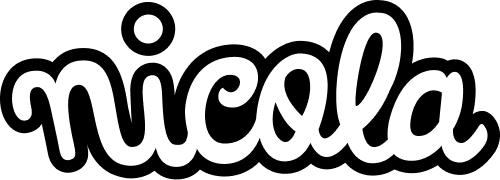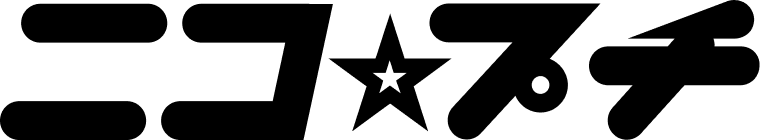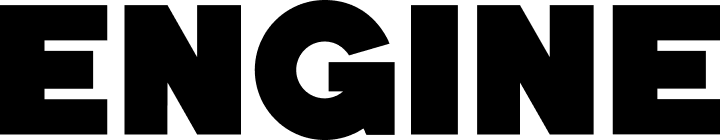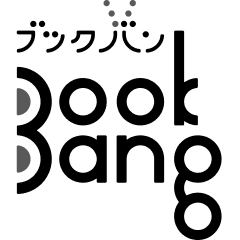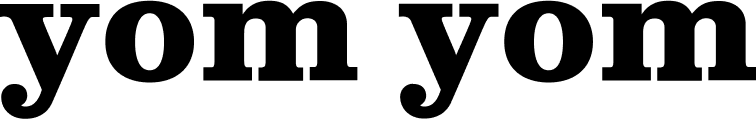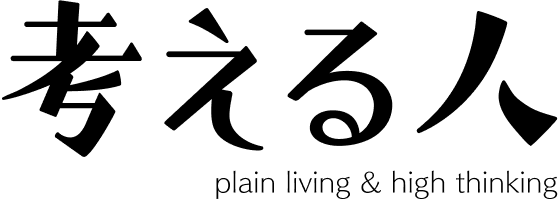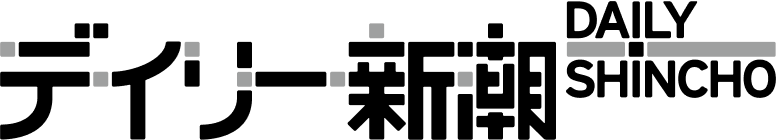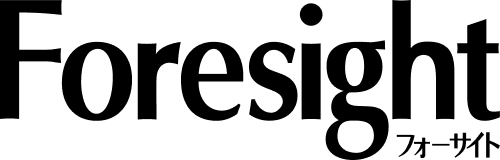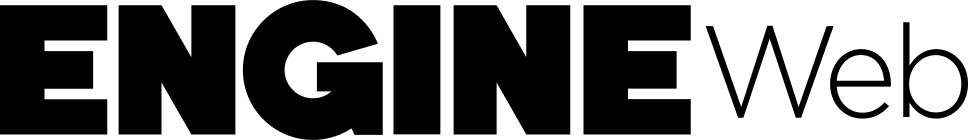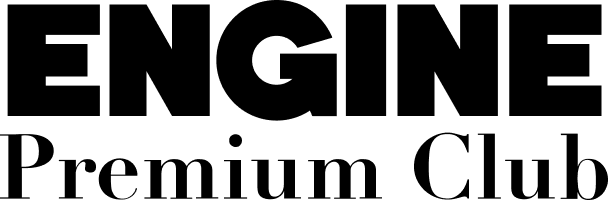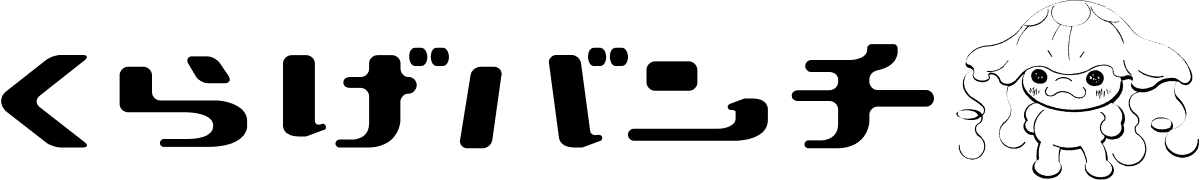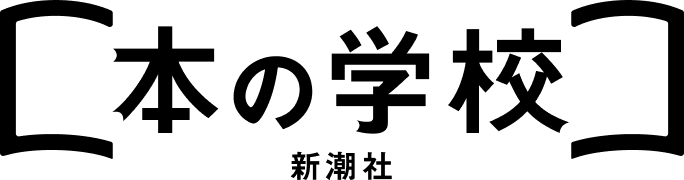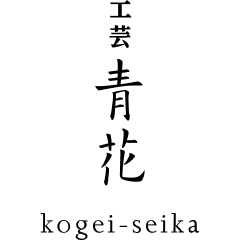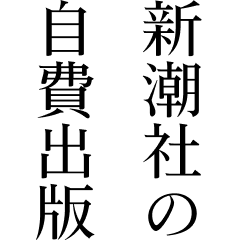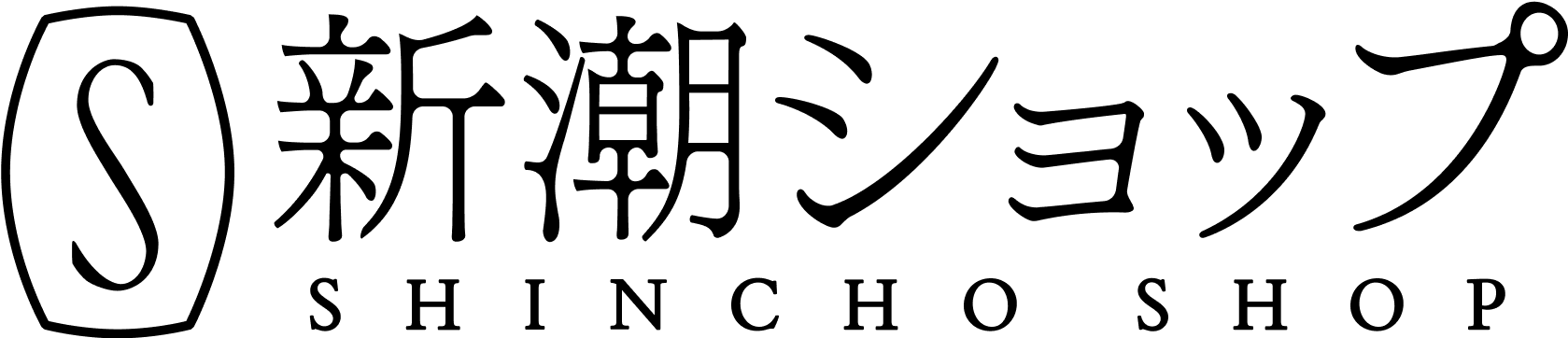JR東日本の広報誌に出てくるようなタイトルをつけましたが、先週末東北の取材に行った折、はじめて「東北ローカル線パス」を使いました。切符の存在は前から知っていましたが、JRだけの切符かと思いきや、私鉄も乗り放題なんですね。雪が降る前に弘南鉄道全駅の撮影をするにはちょうどよい切符です。(「大人の休日倶楽部」会員割引で若い人たちより安い値段です)。
当Webの編集にもご協力いただいている杉﨑行恭さんが、東武鉄道の木造駅の写真をアップされました。残念ながらここに紹介する駅舎は、すべて新駅舎になってしまいました。貴重な記録写真ですので、簡単な解説を杉﨑さんにお願いしました。(編集部)
特急寝台「あけぼの」がなくなるそうです。宮城県の県紙「河北新報」が関係者の話として報じて、何紙かが後追いをしていました。「あさかぜ」がブルートレイン化されてから50年以上、ファンから常に注目されてきた特急寝台用客車です。それは私の人生と期間がほぼ重なる年月です。
鉄道を専門としない一般誌のグラビアに鉄道の写真が掲載されるのは、さして珍しいことではありません。ただここ十年ぐらいでしょうか、その頻度が高くなっているような気もします。まさか「鉄道写真を載せておけば鉄道ファンがすぐに食いつく」とグラビア担当者が思い込んでいる訳でもないでしょうが、正直、「?」と思う企画もままあります。
鶴見線の話をつづけます。昨日のブログで鶴見臨港鉄道の沿線案内をご紹介します。この『沿線案内』には路線図と駅の紹介が細かい字で印刷されています。ただし大抵の沿線案内がそうであるように、発行年が書かれていません。ですから沿線案内を手にしたらまず年代特定をしなければなりません。実はこの作業が楽しいひととき。
『中央公論』7月号に「JR鶴見線ベニス化計画」という座談が掲載されています。副題に「鉄道を偏愛する3人がゆく 工場群と運河を巡るワンダーランド」とあります。偏愛する3人とは、水戸岡鋭治さん、梯久美子さん、原武史さんの3人です。
私が鉄道の写真を撮り始めたのは、昭和45年秋頃からです。最初はオリンパスのハーフサイズカメラでした。そのあとキャノンの一眼レフカメラを父親から譲り受けたのですが、ハーフサイズとキャノンの間に別のカメラを使用していた記憶もあります。