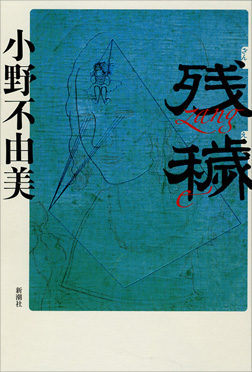第14回 山本周五郎賞
主催:一般財団法人 新潮文芸振興会 発表誌:「小説新潮」
第14回 山本周五郎賞 受賞作品
五年の梅
新潮社
白い薔薇の淵まで
集英社
第14回 山本周五郎賞 候補作品
選評

長部日出雄オサベ・ヒデオ
選評:長部日出雄 北原亞以子 久世光彦 花村萬月 山田詠美
以下に収録するのは、平成13年5月17日午後4時から6時までホテルオークラにおいて行われた同賞選考会での記録(小説新潮平成13年7月号に掲載)です。
|
乙川優三郎「五年の梅」 |
——では、刊行順で、乙川優三郎さんの「五年の梅」からお願いします。
北原 実は私、この作品に五点つけたかったんです。ただ、私が時代物を書いているものですから、幾つかのミスに気がついてしまったんですね。非常に端整な作品ですし、登場する女性も男性も、皆いやみがなく好感が持てます。過不足なく書かれているとも思いました。私など足元にも及ばないと感嘆する表現もあり、そういう意味で、完成度はかなり高いと思います。
ただ、江戸時代を書くのであれば、江戸時代のルールに従って書かなければいけないと思います。たとえば、「一月も前なら日の暮れる時刻だったが」というようなところがあるんですけど、江戸時代は日の暮れは必ず暮れ六ツで、「一月も前なら日が暮れる時刻」にはならないんですね。(編集部注・今回の掲載に際して訂正されています)
こういうところが、どうしてもひっかかってしまうものですから、○・五点だけ引きまして、四・五点にいたしました。これを基準にして点数をつけましたので、これが私の今回の最高点です。五点にしてもいいと思ったほど素晴しいところは、また後で言わせていただきたいと思います。
久世 僕は北原さんのように江戸時代について詳しくないから、欠点がないという意味では、四作のうちで、これが一番ないのかなという気がします。
ただ、テーマというのか、回り道してきた人間や人生みたいなものの関わり、それがちょっと生っぽいかなあ、と感じました。お説教というと表現が悪いけど、そういったものが台詞とか描写の中に滲んでくるんじゃなくて、かなりストレートに出ているのが三篇くらいあって、ちょっと残念でした。
それから、地の文章の中に使われる言葉というのは、たとえば現代語みたいなものは入ってもいいものなんですかね?
北原 地の文章は、しようがないと思うんです。ほかにも、女の人が「何々だわ」と言ってますでしょう。あれは明治時代になってからの幼児語ですから、江戸時代にはないんですけれども、それを言ったら、もう……。
久世 地の文章もかなり当時の言葉みたいなので書いてはあるんです。ところが時々、「紆余曲折を経て」とか、まあ紆余曲折という言葉は、当時なかったことはないんだけども、こういった人情話の中に現代っぽい言葉がふっと入ってくるのがね、なんかそぐわないような気がするんですが、そういうのはどうなのだろうか。
北原 私は仕方がないと思うんですが。そこだけが浮き上がっていてバランスを失っているのだったら、それは失敗と言わざるを得ないとは思います。ただ、全部、江戸時代の言葉で書けって言われると……。
久世 それは不可能でしょうね。
北原 不可能だと思うんです。
久世 雰囲気という点では、かなり気は使っていると思うんですが、ときおり他の言葉に置き換えたほうがいいんじゃないかというのが出てくる。そこに僕は抵抗を感じたんです。それから、普通は「何々していて、」と書くところを、「何々してい、」と点を打っているところがあります。べつに良い悪いじゃないんだけれども、僕はひっかかるんですね。文法的には正しくなくはないんだけれども、言葉にして読んだ時に「何々してい、」と言ったら、やっぱりおかしいと思う。
北原 朗読した時は抵抗がありますね。
久世 そうでしょう。文章というのは、やっぱりどこかで無意識のうちに音声化されているんですね。これをラジオか何かで朗読したら、「何々してい、」というのは、僕は必ずひっかかると思う。欠点だと言ってるわけじゃないんだけれども、わりあい目配りがしてあるだけにね。
北原 余計に目立っちゃうんですね。
久世 まあそれで、余計なことばっかり言いましたけれども、四点ですね。
山田 乙川さんのこれ、どうして「五年の梅」を表題作にしたのかが、私にはちょっと分からなくて。「小田原鰹」とかなら、山本周五郎賞という賞の名前には、一番合うような気がしますけど。
たとえばこの「五年の梅」っていうのを、もしも現代に置き換えて、サラリーマン社会なんかに置き換えたら、とても小説として成り立たない。時代背景とかにすごく頼っている部分があるんですね。そういう意味で、他の作品と表題作に差があるということで、あまり高い点数はつけられないので、私は三点です。
花村 本にした時の並べ方の問題なんでしょうけど、一番最初の作品を読んだ時に、ちょっと躓いて、しばらく保留してたんです。しかし改めて読み出したら、わりと素直に楽しめました。俺は時代小説のことはあんまりよく分からないんですが、悪い意味じゃなくて定型的な、落ちるとこに落ちるお話の楽しさのようなものを非常に感じました。抑制もきいていて、かなりいいと思います。四点です。
長部 こういう賞の選考の場合、短篇集というのは、どちらかというと不利なんです。必ず出来、不出来がありますから。でも、この短篇集は、わりとコンスタントに一定の水準が保たれていると思いました。表題作が実は一番落ちるんじゃないかなというふうに思ったのですが、それは、この人にはちゃんと作風がありまして、大した事件が起きない。しかし、語り口と台詞で、しみじみとした情感を漂わせるという独得のスタイルがあって、たとえば決闘場面でも決闘そのものは出さないとか、真ん中の部分は書かないで、輪郭を暗示して想像させるわけです。ですから、表題作よりも、あまり大した事件の起きない話のほうが、むしろ出来がいいというふうに思いました。
いずれにしても、ちゃんと自分の世界を持って、一番書きたいことを書く、書きたくないことは想像させるという、独自の作風を確立している点で、この人はコンスタントにずっと書いていける人だと思います。私は四点としたいと思います。
|
恩田陸「ライオンハート」 |
——次に恩田陸さんの「ライオンハート」をお願いします。
久世 僕は「志や良し」という感じがするんですね。ものすごく大きなフィクションに挑んでいて、欠点も多々あるんですけれども、フィクションのスケール、仕掛け、企み——この人の行く先には大きな楽しみがあります。前に出た「ネバーランド」にしてもそうで、好きな作家です。
この作品でも、昔の「ジェニーの肖像」だとか、いろいろと思い出させるものがあったり、それからなぜ舶来の話になるのかなと思うところもあったりしましたけれども、姿勢に好感が持てるので、僕はこれも四点です。
山田 私は全然逆で二点です。
これ、すごく難しいことに挑戦していると思うんですけど、日本人が外国を舞台にして、外国人を登場人物として出す時に、翻訳小説の文体をちゃんと持ってないと、すごく苦しいことになると思うんです。たとえば外国のテレビドラマを日本語で吹き替えした時に、すごく違和感を覚える——そういうような感じを受けました。超訳って感じ。
時空を超える話って、ある種の作家にとっては書きたいテーマの一つだと思うんですけど、それに挑戦するには、ちょっと文章力がついていかないかなという感じ。そういうものを書きたいんだったら、スティーヴ・エリクソンの「Xのアーチ」という作品があるんですけど、それをぜひ読むことをお薦めします。それからこの作品に限ったことではないのですが、一行ごとに改行するのは、どういう意図なんでしょう。特にこの作品、そのことによってすかすかしてる。で、二点です。
花村 実は、候補作四作の当たりをつけるために、それぞれ最初の数ページを読んでみたんですが、結局最後に残ってしまったのが、「ライオンハート」と「天国への階段」だったんです。どちらも体言止めを多用しているということと、「ライオンハート」に関しては、細かいところで意図がよく分からないという部分が気になりました。
また、お話自体も途中からなんとなく透けて見えてきて、こんなものなのかなと思いつつ、ちょっと古いレコードで「ヘンリー八世と六人の妻」というのがあったので、それをわざわざ引っ張り出して、聴きながら雰囲気にひたる努力をして読みましたが、俺が年を取ったのかなという感じがしました。十代から二十代の読者には、わりとすんなり受け入れられるのではないかと思って、そういう点を勘案して、三点です。
長部 これは、非常に凝った連作形式の話で、どれもまず一枚の絵に一種の発想が示されて、さまざまな時代と場所を行き来するわけです。エリザベスとエドワードというのが、さまざまに姿を変えてどの話にも必ず出てくるわけですが、読んでいくと、どれがエリザベスで、だれがエドワードなのかなというふうに、一種独得なミステリーのおもしろさというのが醸成されてくるように感じました。
一番それを感じたのは、「イヴァンチッツェの思い出」という一篇で、一九○五年のパナマが舞台です。パナマ運河工事が行われている時期なんですが、そこに集まってくる人々の中で、どれがエドワードなのかということが、ミステリーとして非常に楽しいんですね。イギリスの古典的な探偵小説の雰囲気を漂わせていて……。
このエドワードとエリザベスが「天球のハーモニー」では、とうとうロンドン塔で殺された少年王エドワード五世とエリザベス女王というところにまで行きます。遊びの感覚、ミステリーとゲームの感覚が豊富にあって、私は大変おもしろく読みました。
最後の場面で、女性の新聞記者が恋人の待つカフェに向かって行くところが、とても希望に満ちていて、一切答えが出ないような話でありながら、なおかつ最後にロマンチックな余韻を残したところが気に入りまして、私は四・五点といたしました。
北原 私は二・五点です。
素晴しい着想だとは思うんですけれども、その素晴しさ、面白さが読み手に伝わってこないような気がします。
その一つの原因が、擬音語の多さです。一ページに「キーン」だとか「バラバラ」だとか「パチパチ」だとか、何度も何度も出てきて、参ってしまいました。そういう意味では、花村さんと同じように、私も年なのかなと思いました。実際、私は大分年ですけど。
それともう一つ、いろいろな外国の土地を書くのであれば、行っていない人間にも、その土地の風土、光景を空想させてもらいたいんですけれども、ロンドンもシェルブールも同じところであるような感じがいたしました。
|
中山可穂「白い薔薇の淵まで」 |
——それでは次は中山可穂さんの「白い薔薇の淵まで」をお願いします。
山田 二・五点です。
去年の野間文芸新人賞の候補になった「感情教育」というのは、私も選考委員なので読んでるんです。それから比べるとかなりうまくなってて、「ああ、いいじゃないか」って思ったんですけど、それは主人公がインドネシアに行くまでなんですね。
「天国への階段」もそうですけど、都合が悪くなると外国に移動して、それでその逃げた恋人を外国に追っていくっていうのはあまりにもありきたりだし、もしも、そこの部分がなくて、すっぱりその前で切っていたら、たぶんこれを推したんじゃないかなと思うんですけど、あの最後で、全部を台無しにしてしまっています。よく分からないんですよね、一番最後の終わり方。不親切だなと思います。
花村 四点です。俺はかなり楽しく読みました。ときどき少女漫画で侮れないものにでくわしますが、それを言語によってさらに精緻かつエロティックに仕立てあげたかのような味わいがありました。
ただし、これだけの話を作るには、あまりにも枚数が少なかったのか、たとえば主人公の塁のトラウマを説明するところを父親がプロ野球選手云々といった会話だけで説明していく。そのあたりに非常な無理があるというか納得できないものを感じました。しかし、将来性を考えると、この人にはかなり可能性があると思います。
長部 これは本当に面白く読みまして、五点にしたいと思いました。自分が平凡な人間であるからなのかもしれませんけど、ここに書かれている女性同士の愛の生活というのは、私にとっては非常に新鮮でしたね。
塁という印象的な名前の主人公が、立居振舞とか考え方がじつに個性的で魅力的で、明らかに才能のある作家だというふうに感じられる。小説の中に作家を出して、しかもその人に確かに才能があると思わせるというのは、なかなか難しいと思うんですけど、この山野辺塁には、確かに才能があると信じられる。また才能のある作家を書く時には、実際にその作者にも才能が感じられないと駄目なわけですけれども、私は作者にも才能を感じました。無駄なことがほとんど書いてない。ほぼ全部の文章が生きている。イメージがまことに鮮明です。
そういう天才的な人を天才的に書くということと同じように、語り手の「わたし」の夫になる喜八郎というたいへん善良で凡庸な男、この描き方もまた鮮やかだと思うんですね。平凡な男を平凡に書いて、しかもくっきりと、その人間が見えるようにするというのは、やっぱり才能がなければできない。
私は山田さんの意見と逆で、ジャカルタに行ってからも面白かったですね。出てくる中国人が立花隆の顔を四角くしたようなとか書いていて、そういう表現も印象にはっきり残る。この作者にはユーモアのセンスがあるんですね。たとえば喧嘩をする時に「作家が本屋で読者をナンパしてどうすんのよ!」とか、温泉から帰って来て「ほんの温泉饅頭ですが」などといった言い方は、とてもユーモラスです。
そしてジャカルタで遂に塁に出会う。「そこで見たものを、わたしは一生忘れはしない」と書かれている姿は、これから読む読者のために言いませんけれども、私にはショッキングで、しかもそのイメージが鮮明に見えて、使い古された言い方ですが、「破滅型」というのを最近これほどヴィヴィッドに描いた小説はないというような気がしました。
それから、語り手の「わたし」とともに、この作者自体、常識に富んでいる人なんですね。ですから、最初の書き出しが、二人の交渉が終わってから十年後になっていて、語り手もある意味で落ち着いているのでしょうけれど、最後の場面では、そんな常識的な人がほとんど狂った状態になって、自転車を必死に漕いで破滅に向かって走っていく。そういうラストシーンにも私は鮮烈な余韻を感じました。
北原 私は三・五点です。
この方は大変にうまい、したたかな手腕の持ち主だと思いました。ジャカルタのシーンなんか、分量は少しなんだけれども、饐えたような臭いや煮えたぎっているような感じ、そういうものが目の前に、もわもわっと浮かび出てくるようで、感心いたしました。
それでなぜ三・五点かということになってしまうんですけれども、おしまいがどうしても納得できないんです。編集者の話で、塁たちが実は親を刑務所と精神病院に閉じ込めていたというようなことが分かって、そこできちんと結末をつけてしまったように思えるんです。すると、その後で自転車で破滅に向かって行くシーンの意味が分かりませんし、そもそも冒頭で、塁は十年前に二十八歳で死んだと結末を明らかにしているわけですから、説明の必要はないと思います。白日夢の中にいるような、こちらも酔っているような気分で読んでいるのに、そこで目が醒めてしまうんです。
久世 僕も、おしまいのあれがなんで必要なんだろうかなと思いました。この小説では、塁という人に謎があって、それが弟のことで、その弟がジャカルタにいてといった、そういう普通の小説の展開がかえって邪魔に思われました。つまりもう少し尺を短くして、百枚ぐらい削ってもいいから、女と女だけをこのタッチで書けば、もっと素敵だったんじゃないかな。喜八郎という人も、なるほど面白く、目に見えるように出てくるんだけど、この人もちょっと出番が多すぎるかなと僕には思えたんです。
もう一つは、結末の部分がレズと言いますか、女と女の間のこととの有機的な関わりがないように思えるんですね。弟を探しに行って、破滅へ向かってというのがね。女の人を愛する、女でありながら愛するという、そういった感じ方とか行為みたいなものと、普通の小説の結構みたいなものとの組み合わせがうまくいってないんじゃないかなという意味です。けれど、この手のものは決して嫌いじゃないんで、これも四点です。
|
白川道「天国への階段」 |
——それでは最後に、白川道さんの「天国への階段」をお願いします。
花村 中山さんと違って、今度は長すぎると思います。以前、ある週刊誌に連載されていた白川さんの小説をわりと楽しく毎週読んでいたんですが、ある時「脱兎のごとく駈け出した」という表現があって、それを読んだ途端に、もう進めなくなっちゃって読むのをやめた記憶があるんですが、この作品でも、手垢のついた比喩や表現がひっかかりました。また明らかな言葉の誤用など、校正面での杜撰さもあり、損をしています。
気合いを入れているのはよく分かりましたが、お話自体がテレビの二時間ドラマを見ているような印象は拭えず、これは二・五点です。
長部 書き出しの競馬場のシーンに、主な登場人物がだいたい出てきて、これからどういう話が始まろうとしているのか、それぞれの人にどんな背景があるのかといったことが、じつに具体的にわかりやすく、歯切れのいいテンポで展開されていきます。これは面白くなりそうだなというふうに大いに期待して読んでいったんですが……。
読み終わったあとの感想を一つだけにしぼって言えば、殺される及川広美というのが、一馬という息子に向けて、長い遺書を書きます。これがすこぶる論理的で明快で説得力に富む文章なんですね。まず名文と言ってもいいくらい、冷静で分別のある文章です。これだけの文章を書ける人だったら、あんな怪しまれるような呼び出し方をして、しかも、なんか誤解されるようなことを言う必要はないと思うんです。
誤解するほうも、「おまえには他にすべき大切なことが残されている」という及川の一言でもって、殺す決心をしたということになるわけですが、一馬にちゃんとお金をやって面倒見てくれというだけのことですから、きちんと情理を兼ね備えた手紙を書けば済むことであって、僕の疑問というのはこの点に尽きるんです。その一点だけで、説得力を欠いているというふうに思いまして、この人の大変な実力は十分に認めるんですけど、私は今回は三・五点です。
北原 私は三点です。面白いし、迫力もあるし、気持ちよく読むことはできたんですけれども、読み終わった後の手応えが少し軽かったんです。
長部さんのご意見に私もまったく同感で、なんで及川広美という人が、お酒を何十杯も飲んで、無理をして会いに行ったのか、私も不思議でならなかったんです。手紙一本出せば済むことなのに、そうしたら殺されなくても済んだはずなのにと、どうしても思ってしまうんです。もっとも、そうすると、及川広美殺しが成立しなくなっちゃうんですけれども。大変な力作で、筆力もあるとは思うんですが、その点が納得できない。
それともう一つ、私が女だから感じるのかもしれませんけれども、主人公の永遠の恋人である女性が結婚する時に、相手の血液型が彼と同じO型だったから結婚するというところがありますね。
花村 俺も唖然としたんですよね。こんな嫌な女、いねえよって。
北原 それが永遠のマドンナかという感じがしました。ヒロインに共感できないのは、読んでいてつらくなりますので、三点になりました。
久世 これまでの白川さんの作品と比べて、ちょっと子供っぽすぎるかなというのがあります。白川さんの作品の魅力だった無頼っぽいとか、ダークな匂いがするとか、そういうものが嘘みたいにここにないんですね。一所懸命たくさんの紙数を費やして書いているわりに、そういった匂いとか温度みたいなものがまるで伝わってこないというのは、この人のものとはちょっと考えられないなと思うくらいでした。
それと萬月さんがおっしゃった、常套句みたいなのがちょっと多すぎますね、いろんな些細な点がひっかかり過ぎるというのは、大きな力がそもそも欠けているんじゃないかなと、読んでてちょっと僕はつらくなりまして、残念ながら三点です。
山田 私も三点です。久世さん、北原さんと同じ点数ですけど、たぶんかなり意味合いが違うと思うのは、私は乙川さんも三点なんですけど、全部点が低いんで、まあこれが乙川さんと並んで一番いいほうかなという感じなんですけど。
話としては、成功した人が過去に復讐される話って結構ありがちなんですよね。「飢餓海峡」とか「砂の器」とか、よくある話と言えばよくある話なんですが、私の知り合いの五十歳前後の男性たちは、みんなこれを読んで号泣したと言うんですね。ナイーヴ過ぎて、私はこれではとても号泣できないんですけど。ただ、家に帰って、この本の続きがあると、「ああ、続き、残ってるんだ」と思える、そのページターナーという意味を考えると、やっぱりエンターテイメントって、そういう人を夢中にさせる何かがあるということが基本だと思うんで、それで三・○ということにしました。私の中では、この中ではいいほうのつもりです。
——集計点をご報告いたします。「五年の梅」十九・五点。「ライオンハート」十六点。「白い薔薇の淵まで」十九点。「天国への階段」十五点。「五年の梅」について、北原さんが美点について後ほど言い添えるとおっしゃいましたが……。
北原 この中に、「蟹」という小説があるんですが、ここに素晴しい表現があるんです。
単行本の百七十二ページなんですけれども、「潮風の染み込んだ雨戸や、湿っぽい台所の匂いもそうである。そうした匂いの集まりが志乃には家であり、」という一節がある。これだけなんですけれども、かつてあった日本を感じさせてくれる。昔はそれぞれの家の匂いというのがありました。それが、湿った台所の匂いであり、漬物の匂いであり、決していい匂いではないけれども懐しい匂いでした。
今は匂いというものが嫌われて、中年のおじさんの匂いまでとやかく言われるようになってしまいましたけれども、昔の日本には確かにいろいろな匂いがあった。それぞれに匂いがあった。それを、わずかこれだけの言葉で思い出させてくれた。これこそ時代物の持つよさじゃないかと思うんです。
長部 我々は普通、人の幸せというのはあんまり嬉しくなくて、どっちかというと、人の不幸を喜ぶという感覚で生きていると思うんですが、「小田原鰹」を読むと、鹿蔵という男は怠け者で働かずに不平不満ばっかり言って、妻子を金づるにして生きているような、まったくろくでもない奴ですよね。それで、女房のおつねが家出してからは全然駄目になってしまうんですが、誰からか初鰹が贈られてきて、ずっと白眼視していた周りの人たちも、みんな鹿蔵を見直す。つまり鹿蔵は幸せになっていくわけですが、こちらも読んでいてとてもいい気持になるわけですね。人が幸せになるのを見て、いい気持になるということは、今、ドラマや小説の世界でしかない。しかも、ろくでもない奴が幸せになっていい気持になるというのは、時代小説の中でしかないことなんじゃないかというふうに思いました。
この人の小説は、本当の悪人というのはあんまり出てこなくて、出てきても、悪人の書き方があんまりお上手とは言えないと思うんですが、しかし、この人は世の中に悪人がいるということを知らないわけじゃない。むろん知ってるんですけど、それよりも、人が幸せになったり、人助けをしたり、そういったことが読む人の心をしみじみとしたいい気持にさせる……そういうことを書きたくて書いてるんだと思いますね。
花村 俺は、北原さんのように時代小説の素養がないからなんでしょうが、「小田原鰹」を読み始めてしばらくして、地理の説明があるんですけど、「この作者は地図を見て書いてるんだな」というのが透けて見えて、どうも非常に乗りづらいところがあったんです。しかし、それを過ぎたあたりから、のめり込み出しました。「小田原鰹」はほんとうに素晴らしい話で、長部さんがおっしゃったのと似ているんですが、人間には悪い人間がいない、そういう小説ですね。それが、じつに素晴らしい味になっていると思うんです。
それと、北原さんがチェック入れていた百七十二ページですけど、俺もちゃんと、同じところにチェックが入ってます。「いいですね」って書いてあります(笑)。
北原 いいです、これは(笑)。
花村 「小田原鰹」と「蟹」は、ほんとに素晴らしい小説だと思いました。大好きです。ですから、いきなり結論めいたことを言っちゃうのはなんですけど、もし順当なら、この作品だと思います。ただし、将来性などを考えると、中山可穂さんにもすごいひっかかるものがあるので、自分でもまだ決断がつかない状態です。
でも、ほんとにこの乙川さんの小説は素晴らしいです。実は、三日ぐらいかけて読んだんですよ。あまりにもいいんで、俺、幾度も行きつ戻りつして楽しんだんです。最初のうちは、「文章に色気がねえよな」なんていう批判的なことを思ってたんですが、そうではないんですね。この方のスタイルなんですね。「蟹」のあたりでは、逆にすごい色香を感じまして、自分の読み方の浅さを恥じました。
山田 私の「いいですね」は、「小田原鰹」で鹿蔵が刺されちゃうとこ。どこかの娘を助けようとして刺されちゃって。その時に鰹の贈り主に思い至って、「だとしたら人さまに鰹を贈れるほど幸せになったのだろう……案外やるじゃねえか」と言うんですね。
私も萬月さんと一緒で、時代小説ってそんなに詳しくないので、むしろこれが現代だったら成り立つかどうかっていうところで見るんで、そこで欠点も長所も出てくるというか。時代小説じゃなくても、この部分はいいだろうという感じがしました。
久世 ちょっとケチをつければ、僕なんか商売柄、カメラが寄りで撮るか引きで撮るかとか、ミドルサイズで撮るかと言うんです。それでこういった人情話というか、小説の場合には、僕はミドルサイズが基本の絵じゃないかなと思うんですね。人物が二人出れば、二人とも映っている。アップにすると一人しか表情が分からなくて、もう一人のリアクションが同時には分からないわけです。だからこういう話というのは、ミドルのよさじゃないかなと思うんだけど、それがちょっと弱いと思うんです。
つまり、寄りと引きはあるんです。たとえば縁側で話している二人の一人ずつは撮っているけれども、このツーショットというか、ミドルサイズがもうちょっと欲しい。で、なおかつ庭があって縁側があって、その奥のほうに台所がちょっと感じられてみたいな、そういう高い絵を撮った時に、つまり高い絵というのは、人それぞれの経てきた時間、人生というようなものをシンボライズした絵ということなんだけれども、それがちょっと順当過ぎるというか、教条的なのが残念だなと思いました。
しかし、この人は、一年後、二年後というふうに、どんどん上手になられるだろうし、いいものを必ず書く人だと思います。
——「ライオンハート」に関してはいかがでしょうか。
山田 これはちょっと。「フロリダの空は、抜けるように青く高い。」——この一行で、小説とはこういう紋切り型の文章で書き出してはいけないということを、誰かが教えるべきだと思いますけど。だいたいフロリダの空って、光の粒子が多過ぎて抜けるような青空には見えませんね。むしろ、白い。
花村 この本の作りがとても楽しいんですね、絵とリンクしてて。ただ、時々、無理に絵にこじつけたようなところもちょっと感じました。おそらく若い読者には、非常に楽しめるんじゃないかとは思ったんですけれど、俺の中で評価の難しい作品です。
北原さんが擬音が多いとおっしゃられたんですけど、「きぃぃぃぃぃん」とか、そういう時に、なぜか太字になってるんですね。その意味がわからなくて。映像的な効果を狙ってるのかな。いいとか悪いとか、俺にはうまく言えないんですが、楽しんじゃったことも確かなんですよ。
山田 でも、これは、わりと不親切な小説というか、あとがきでキーワードがこれだというふうに書くんだったら、もっと分かりやすく、あとがきがなくても分かるように書くべきです。私は知ってましたけど、ケイト・ブッシュを知らなかったら読めないんじゃ、ちょっと困ると思いますね。
花村 それ以前に、やっぱり、外国を舞台にする理由がね。
山田 ないと思う。反対に、これを英訳してみようとすると、それが解る。
長部 こじつけるという言葉が出ましたけど、これ、こじつける小説なんですよね。無理してるんだけど、ああ、うまくこじつけたなと思って、私はその手際を楽しみながら読んだんです。とにかく、これはゲーム感覚の遊びの作物で、小説には、こういうペダンティックな遊びもあっていいんじゃないかなと思う。
そのペダントリーということで言うと、これは当然いろいろと調べなくちゃ書けないですよね。でも、この人は、調べたことにあまり深入りしないところがいい。わりとバランスよく、適当に書いてます。パナマ運河のところでも、当時のスキャンダルなんかうまく絡ませて。
ですから、きっと作者も楽しんで書いたろうし、これを同じように楽しむ読者というのは、きっといるだろうというふうに思って、私自身も片一方の頬で笑いながら読んだんで、高く評価したのを変えるつもりはありません。
久世 僕も、そっちの方角というのは、やっぱりあってほしいなと思うんですね。いろんなものをちりばめて、仕掛け作って、辻褄合わせてみたいな。それがちょっと自分勝手すぎる遊びになっているのが問題なんです。もう一つ知的なというのか、裏打ちがないと、この遊びは成り立たないんじゃないかなと思います。そこまで行ってないというのはありますね。ただ、たくさん小説が書かれている中で、こういうものもあって欲しいという意味なんです。
北原 時代物を書いている人間から言いますとね、私、乙川さんにケチつけてしまいましたけれども、欠点が分かるわけですよ。あ、ここで間違えちゃったというところが。でも、これだと分からない。
久世 それは誰にも分からないんじゃないですか。詩とか音楽とか好きなものをちりばめて、本人は結構乗って書いてるのかなとは思うんですね。ただ、それが伝わってこない。音楽が聴こえてこないんですね。
——「白い薔薇の淵まで」についてはいかがでしょう。
花村 完成度から言ったら絶対乙川さんのほうが上ですけれど、俺はこの作品を心底から推したいと思います。たとえば女同士がキスの時にガムをやりとりする描写の巧みさ。男女だったらちょっと……ですけれど。
山田 するよ、男女でも(笑)。
花村 ええっ、俺は嫌だな。
山田 私、「チューインガム」という小説で書いたもの。
花村 ほおー。とにかくポイント、ポイントでなかなかドキッとさせられる見事な表現があり、感服させられました。父親の野球の部分は承服できないし、欠点も多いんですけど。
山田 でも、これ、もっと鮮烈ないい作品になる余地がいっぱいあると思うんですね。だからもっと完璧に近いものを書いて賞を取ったほうが、私はいいと思うんだけどな。
久世 野球と親父の話の代わりに、この女と女という世界の上で成り立つエピソードが四つか五つあるべきなんです。そうすると二人の女がもっとよく見えてくるんですが、残念ながらそれがないんですよね。
花村 辻褄を合わせようとしたり、オチをつけようとして、それでせっかくの作品が駄目になってるんです。
山田 日常に埋め込もうとしすぎていると思うんですよね、この二人のことを。でも、日常に埋め込む描写の必要なんてまったくないんで、二人で部屋に閉ざされているところにいるんだったら、それをもっと密度濃く書いたら、もっとよかったと思う。
長部 僕はそこのところが反対の意見で、たとえばですね、この山野辺塁という人の小説は、そんなに量産できるタイプじゃないし、それほど売れる性質のものでもない。じゃあ、いったいどうやってご飯食べているのか。それから、この「わたし」という語り手のほうも、どの程度の収入を取っていて、どういうふうな暮しの仕方をしているのか。学生時代から、どんな生活を送ってきて、たとえば喜八郎とはどういう関係で今どうなっているのか等ということが、納得できるように書いてあると思うんですね。そういう日常的なこと、ディテールがちゃんと書かれているものは、僕は小説として面白いというふうに思うわけですよ。
日常的な条件がはっきり書かれていて、そこに普通の常識的な人間の関係から落ちこぼれてしまった二人だけの世界ができて、ありきたりな言い方をすれば、だんだんだんだん深みにはまっていくというのが、私みたいな平凡な人間にも実によく分かるように書かれている。
この「わたし」、川島とく子って、名前がまたすごくいいと思う(笑)。なんとも当り前の名前でね。川島とく子は山野辺塁にどんどんのめり込んでいくし、また山野辺塁のほうも、川島とく子にどれほど魅かれているかということがよく分かる。お互いにかけがえがない、どっちもこの人しかいないという感じになっていく。平凡な人が単に山野辺塁のほうに引っ張り込まれていくのじゃなくて、山野辺塁のほうも本当に川島とく子に打ち込んでいるし、お互い全力投球で、ボクシングで言えば、自分の持っている力とテクニックの限りを尽くして闘い合って、どんどんどんどん深みに入っていくという関係が描かれていて、僕はこれ、とてもいい小説だと思いましたけどね。
花村 俺も、「五年の梅」とこの「白い薔薇の淵まで」、本当は二つとも受賞させたいんですよ。どっちも素晴らしいんで。
ただ、エイズとか、そういうものに頼るなって言いたいんだよね。それで全部ぶち壊しにしているからさあ。
山田 ない方が鮮烈になる。先程、どなたかがおっしゃったユーモアとかいうのもいらないと思う。
花村 ただの病気じゃねえか。そういう意味では、乙川さんのほうが絶対上なんですよ。でも、きらめく部分があるんで、それに肩入れしたいんです。
長部 一作受賞が確かに正道ではあると思うんですけど、私は今回は、乙川さんと中山さんと二人だったらいいなと、内心思っています。
花村 俺も思ってます。
長部 乙川さんは安定感において、まったく疑問がないし、この人はもう、この線で書いていって、少しずつ少しずつ確実に力を高めて、ずっと残っていく人ですよね、長い道を。中山さんというのは、今回初めて読んだんですけど、これだけうまい人、僕は全く知らずにいた。そんなに急激に伸びてきたんだとすると、ここでもう一つ、賞でもってドライブがかかると、ひょっとしたら……。
山田 朝日新聞社の新人賞作品からここまで来て、ようやく何かつかんだよねっていう感じがあります。前回の野間文芸新人賞の候補作「感情教育」に比べても、急にうまくなったという感じがあるし、そういう意味ではいいかもね。
——「天国への階段」についての議論はいかがでしょうか。
花村 どうしても細部をあげつらうことになってしまうんですね。
山田 FBIに手紙持っていきたくなるよね、最後のとこなんか。やっぱ、無理あるなあ。
花村 そもそもちゃんと避妊しろよって主人公に言いたかった、俺(笑)。
でも、白川さんのこの作品は、読者の多大な支持があるようなので、それはそれで賞とは別の栄冠を受けているのだと、とらえています。こういう場であえて後押しの必要もないでしょう。
久世 この際、採点を変更してもよろしいでしょうか。「白い薔薇の淵まで」を四・五にしたい。そうすると、「五年の梅」と点数も同じになってくる。
北原 花村さん、それなら乙川さんを○・五点増やしてよ。
花村 正直に言います。純粋に作品として比較したら、俺は絶対に乙川さんです。でもね、後押ししたいじゃないですか、この賞として。
北原 それも分かる。でも、山本周五郎の雰囲気を持った人っていうの、乙川さんが初めてですもの。
久世 だから、僕、実はやっぱり二作ということが前提なんですよ。そのために○・五増やしたんです。
山田 私は乙川さん三・五でいいですよ。
北原 ありがとうございます。と言っても、乙川さんに会ったこともないんですけど。
——議論が煮詰められて、これはもう甲乙つけ難いといったことであれば、二作受賞やむなしですが、基本的には一作にしぼり込むという方向で議論を尽くしていただくようにお願いしたいと思います。
花村 作品本位でやったら、乙川さんになっちゃいますよね。
山田 だって、作風が全然違いすぎて、二つ比べられないじゃないですか。
長部 こっちが目配りが利いてなかったせいかもしれませんが、僕は、この中山可穂という人、全然知らなかったんですよ。
賞というのは、そういうまだ注目されていない作者を、こういう人がいますよと世の中に広く知らせることも大事で、今回は二作にさせてもらえるといいんじゃないかと思いますけどね。
花村 俺もですね、一番楽しめたのは乙川さんの作品集なんです。ただし、中山さんに才能のきらめきを感じたのも事実なんです。それは同じ天秤で測れないですよ。
北原 乙川さんは、着実という感じの人なんですよね。中山さんは安易な言い方ですけど、キラキラッという感じ。
長部 極端に言うと、中山さんはこの次は分からないというところもあります。乙川さんはまず間違いない。その安定感と、なんかちょっと危ないけど、ひょっとしたら化けるかもしれない。僕はこの作品ではもう、かなり化けかかってると思いますけど……。こういう人が化けてほしいですよ。
花村 そう。で、賞を取ることによって、自信になって、つまらないオチとかつけないようになってくる。やっぱり不安なんですよね。読者は分かってくれるかどうかとか、納得してもらえるんだろうかとか。でも、賞の作用としては、そういうつまらない心配をせずに書けるようになるということも大事だと思うんですよね。
山田 そういう親切な選考委員は、私が、何回か続けて芥川賞の候補になった時にはいなかった(笑)。でも、そのことに感謝してるんですけどねえ。
——今まで二作受賞になったのは、篠田節子さんと真保裕一さんの時だけです。
山田 前例があるんだったら、いいじゃないですか。
長部 議論が紛糾すると、二作受賞というのが一番楽な収拾の仕方であるわけですが、でも、そういう安易な方法につくんじゃなくて、このまったく違った作風の二つを、ぜひ山本周五郎賞として推したいということでいいんじゃないでしょうかね。
久世 賛成です。
花村 傾向が同じような作品が残ったんなら、重箱の隅をつついていけば簡単ですけどね、これは比較にならないですからね。
山田 そうすると、だんだん消去法になってきちゃって、欠点ばかり見つけていくということになるんで、例外で二作でいいと思いますけど。
——選考委員全員一致で二作受賞を望むということでよろしゅうございますか。
山田 私、今回は受賞作なしだと思っていたのですが、他の方々の御意見ももっともですね。いいですよ。
花村 お願いします。
——それでは二作受賞ということで、本年度は決定いたします。(拍手)
選考委員
過去の受賞作品
- 地雷グリコ
- 黛家の兄弟
- テスカトリポカ