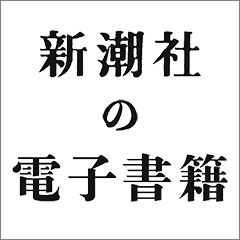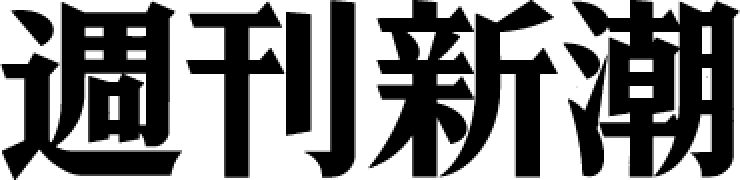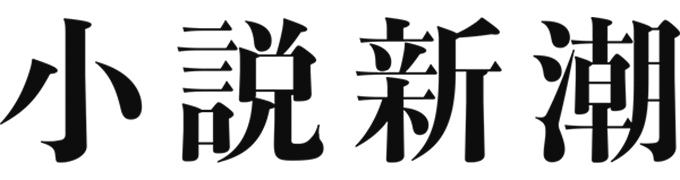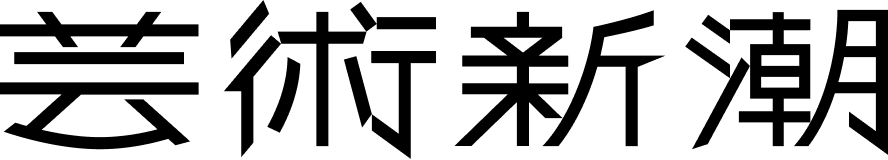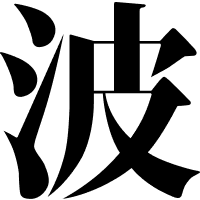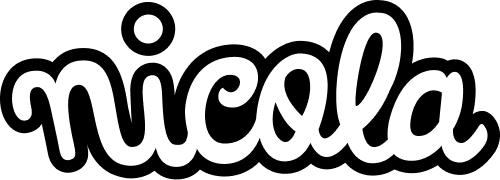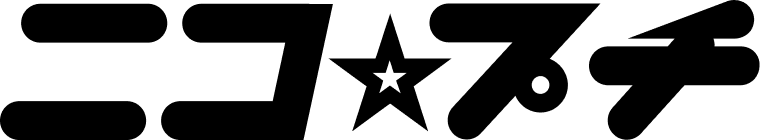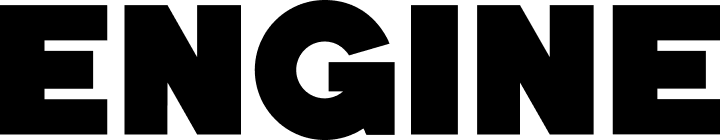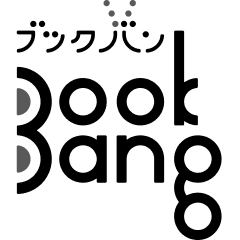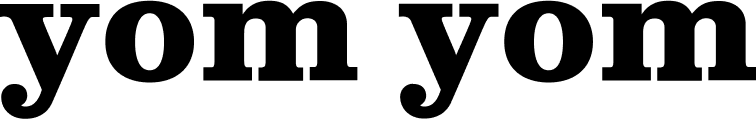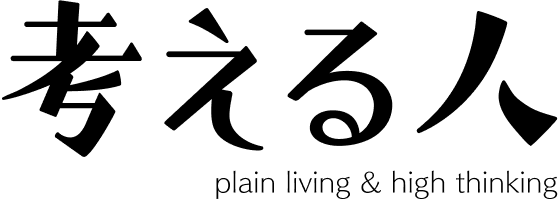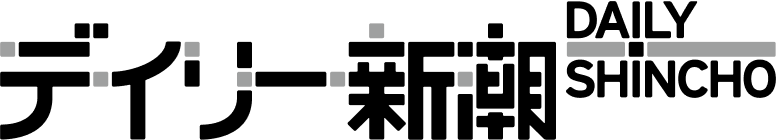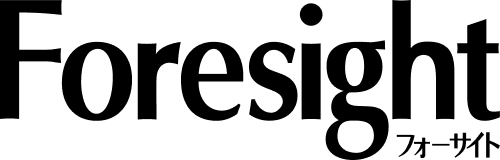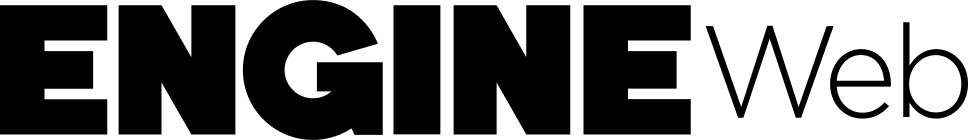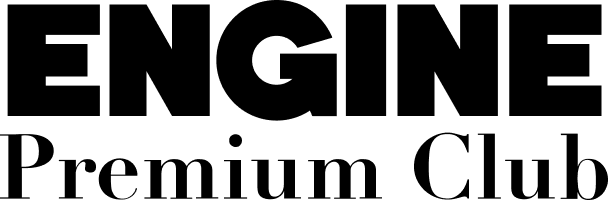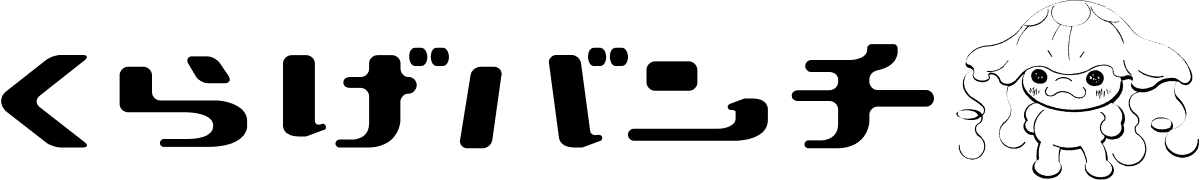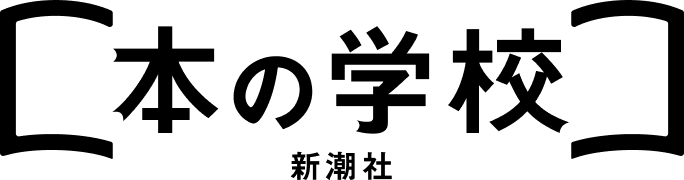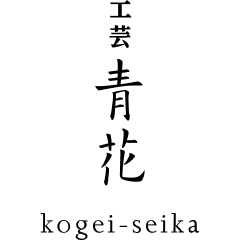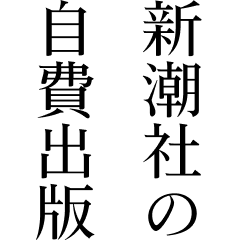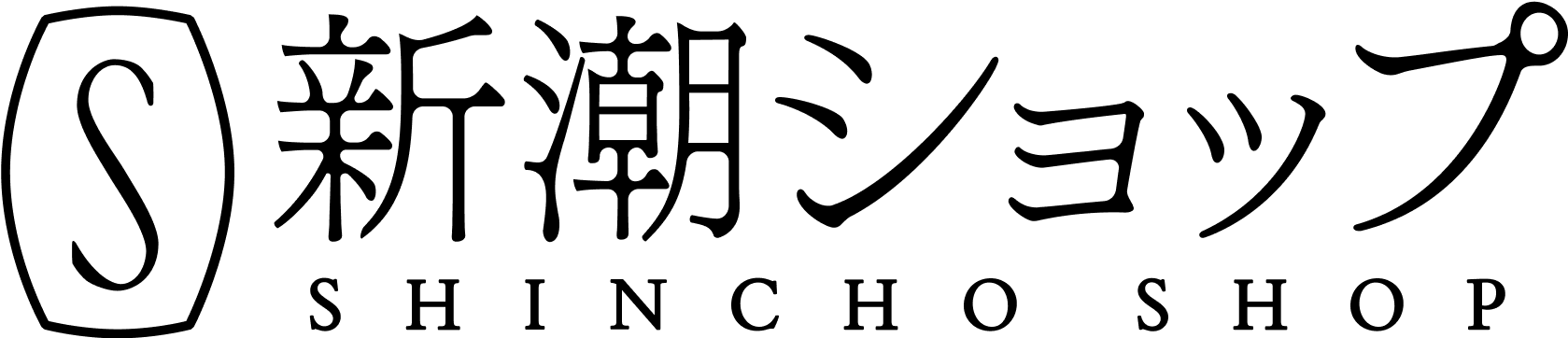フランスはどう少子化を克服したか
814円(税込)
発売日:2016/10/15
- 新書
ズレてない? 日本の政策。親に期待しない、3歳から学校に、出産は無痛で。「5つの新発想」を徹底レポート。
少子化に悩む先進国から、子育て大国へ。大転換のカギは、手厚い支援策の根幹を貫く新発想だった。「2週間で男を父親にする」「子供はお腹を痛めて産まなくていい」「保育園に連絡帳は要らない」「3歳からは全員、学校に行く」――。パリ郊外で二児を育てる著者が、現地の実情と生の声を徹底レポート。日本の保育の意外な手厚さ、行き過ぎにも気づかされる、これからの育児と少子化問題を考えるうえで必読の書。
取材にご協力いただいた皆さん
書誌情報
| 読み仮名 | フランスハドウショウシカヲコクフクシタカ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮新書 |
| 発行形態 | 新書 |
| 判型 | 新潮新書 |
| 頁数 | 224ページ |
| ISBN | 978-4-10-610689-7 |
| C-CODE | 0237 |
| 整理番号 | 689 |
| ジャンル | 政治、外交・国際関係 |
| 定価 | 814円 |
インタビュー/対談/エッセイ
子供の増える国、フランスの発想法
ピカピカの遊具、園内で手作りするごはん。保育士は園児をこまめに着替えさせて清潔に保ち、月に一度は季節の行事や遠足を催す。日本の保育園を数件見学した際、その設備と充実した保育内容に感銘を受けた。
一方、私が2人の子供を預けているパリ郊外の保育園では、給食はセンターでつくったものがほとんど。パリ市内では園庭すらない保育園が多く、外遊びも毎日ではない。着替えは汚れがよっぽど不快な状態(びしょ濡れなど)でなければさせず、Tシャツに粘土や絵の具をつけたまま帰ってくる。園の行事は年に2回、クリスマス会と学年末のお祭りのみで、運動会やお遊戯会はない。まして入園式も卒園式もない。比べてみると、日本はずっと手厚い保育を行っているのだ。日本の保育園は、素晴らしい……!
それでも私には、そこに自分の子供を通わせることが、とてもハードルの高いことのように思えた。それは日本の保育園で一般的な、「毎日の持ち物表」の存在を知ったから。乳幼児の場合、〈名前を書いた紙オムツ5枚、ビニール袋2枚、口拭きタオルとエプロン各2枚ずつ、着替え1枚ずつ、記入済みの連絡帳……〉。これらを毎日用意して持参し、降園時には使用済みオムツがビニール袋に入れて返却されるという。一方のフランスは、毎日手ぶらで通園し、手ぶらで帰宅する。手厚い保育を行う日本の園は、親に求められるものもまた、フランスよりずっと多いのだ。
フルタイムで勤務した後、悪臭を放つオムツを持ち帰り、朝晩と子供の世話をして、翌朝また5枚のオムツに記名する(返却時の混同防止のため)。そんな自分の姿を想像して、私には無理だ! と、泣きそうな気持ちになったのを覚えている。そしてそこから考えた。どうして保育園のあり方がこんなに違うのだろう。合計特殊出生率ではフランスは1・98、日本は1・42(2014年、OECDデータ)と、大きな開きがある。手厚い保育を行う日本で、なぜ子供が増えないのか。逆にフランスではなぜ、子供が増え続けるのか。
『フランスはどう少子化を克服したか』は、そんな素朴な疑問に端を発している。そこから現地の保育関係者に会い、子育てをめぐる諸制度を調べていくと、人間的で合理的、かつ現実的な「フランス式」が見えてきた。保育だけではない。父親の育児参加、無痛分娩、就学前教育と、子持ち家庭が経験する様々な局面に、国を挙げた子育て支援策が行き届いている。そしてそこには、日本とは全く異なる発想が採用されていた。保育が日本ほど手厚くなくとも、子供が増えていく発想法が。
少子化の危機に悩む日本に今必要なのは、まさにその「異なる発想」であることを、本書でご理解いただけると信じている。
(たかさき・じゅんこ ライター、パリ郊外在住)
波 2016年11月号より
蘊蓄倉庫
父親の育休? 父親の「産休」?
フランスでは、男性も育休をとって子育て参加……なんて日本人の大きな誤解! じつはあちらの育休取得率は、日本における取得率と同レベル、わずか2%台に過ぎません。大きく違うのは男の「産休」だと『フランスはどう少子化を克服したか』著者の高崎順子さんは指摘します。
一般的に、女性の産休は出産予定日の6週間前と出産翌日からの8週間ですが、男の「産休」は子供が誕生した日から始まるのがポイント。3日(出産有給休暇)+11日(子供の受け入れ及び父親休暇)の2週間で、入院中の妻とともに赤ちゃんの世話の仕方を学ぶほか、自宅での新生活をスタートさせます。この「産休」を大半の男性が取得しているというのです。11日間の父親休暇は2002年の施行からすばやく社会に浸透しました。本書では、フランスがいまも少子化を克服し続けている「5つの新発想」をご紹介します。
掲載:2016年10月25日
イベント/書店情報
著者プロフィール
高崎順子
タカサキ・ジュンコ
1974(昭和49)年東京都生まれ。東京大学文学部卒業後、出版社に勤務。2000年渡仏し、パリ第四大学ソルボンヌ等で仏語を学ぶ。ライターとしてフランス文化に関する取材・執筆の他、各種コーディネートに携わる。著書に『パリ生まれ プップおばさんの料理帖』(共著)等。