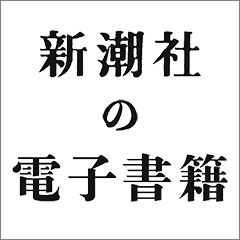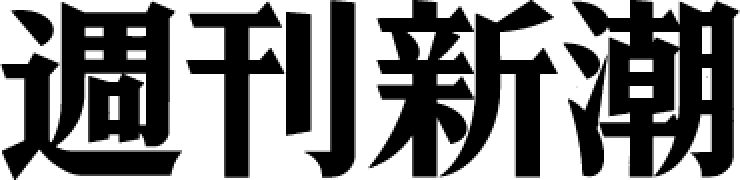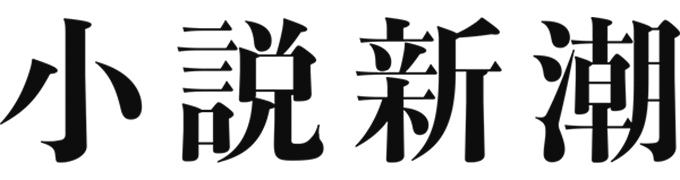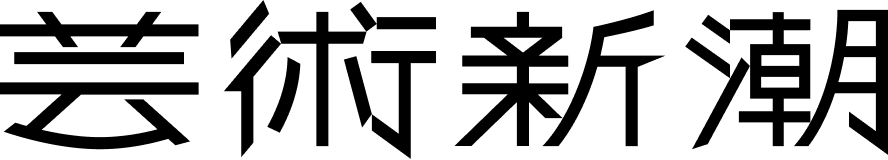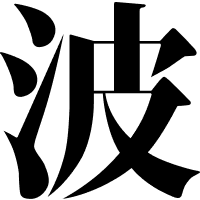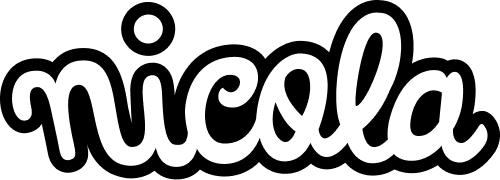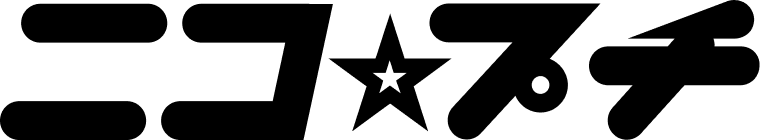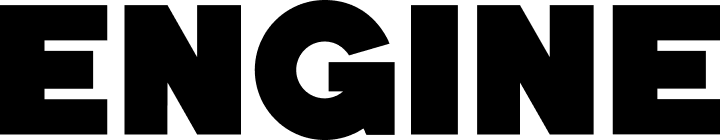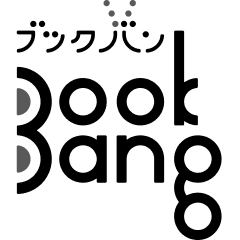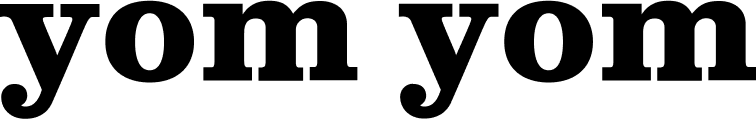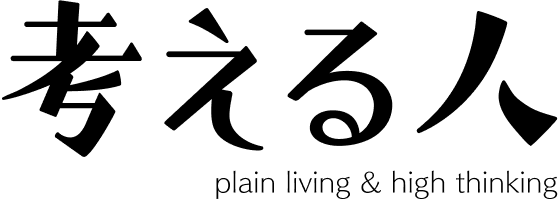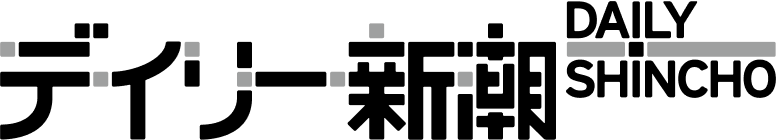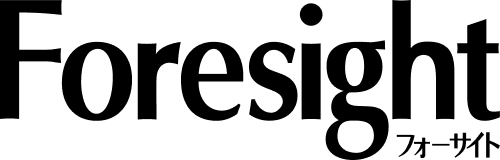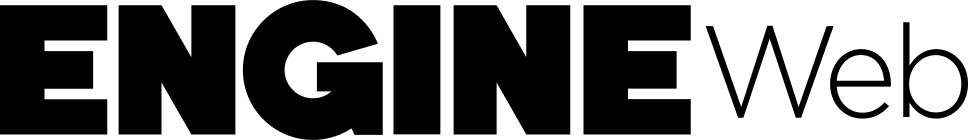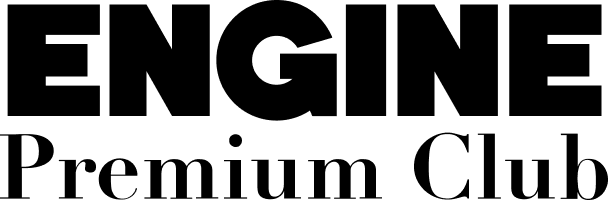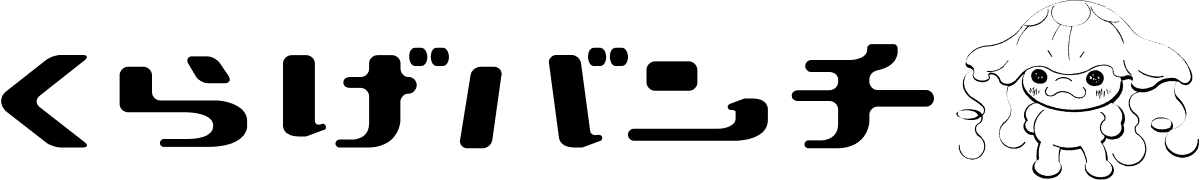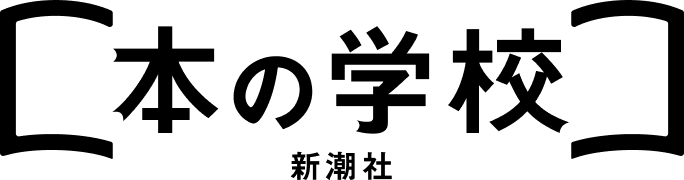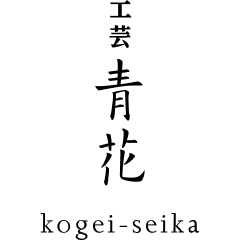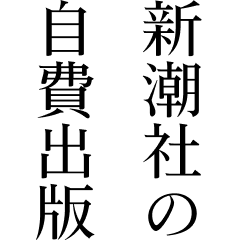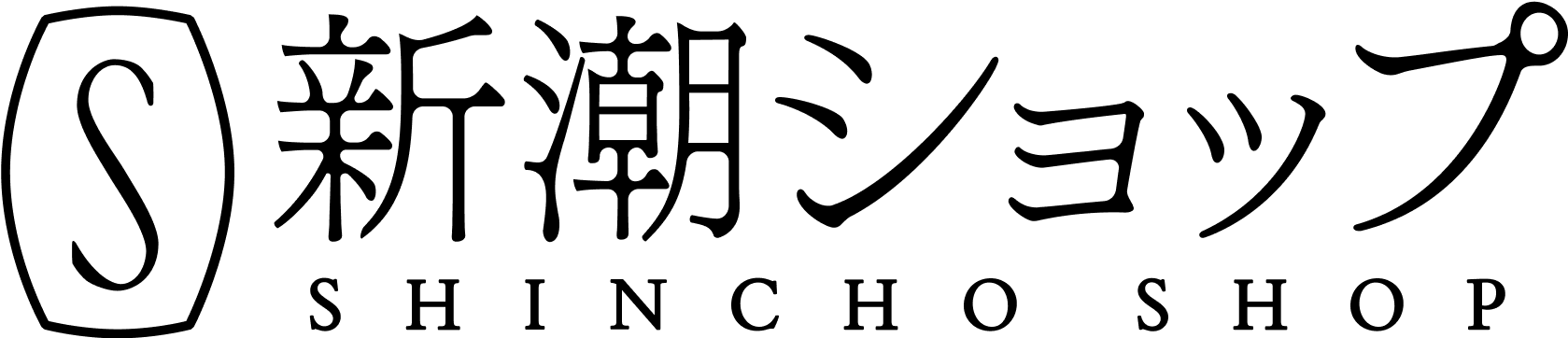お坊さんが隠すお寺の話
748円(税込)
発売日:2010/03/17
- 新書
- 電子書籍あり
檀家さんの我慢は、もはや限界寸前。マンネリ葬儀に法外な戒名料……。崩壊の危機迫る、現代のお寺事情。
日本人から信心が失われて久しい。それでもお寺は、「葬式仏教」を頼みに、かろうじて生き延びてきた。しかし、法外なお布施や戒名料ばかりを要求する一部住職に、檀家さんの我慢は限界寸前。結果、仏教に頼らない葬儀が急増、さらに過疎化や後継者難の影響もあって、地方の末寺は崩壊の危機に……。自業自得の日本仏教に、再生の道はあるのか。お坊さんが黙して語らない、それでも知っておきたい、現代のお寺事情。
書誌情報
| 読み仮名 | オボウサンガカクスオテラノハナシ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮新書 |
| 発行形態 | 新書、電子書籍 |
| 判型 | 新潮新書 |
| 頁数 | 192ページ |
| ISBN | 978-4-10-610357-5 |
| C-CODE | 0215 |
| 整理番号 | 357 |
| ジャンル | 宗教 |
| 定価 | 748円 |
| 電子書籍 価格 | 660円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2011/12/28 |
インタビュー/対談/エッセイ
波 2010年4月号より されど、葬式仏教。
それ以来、機会があればいつかこの問題について書いてみたいと思い続けてきましたが、いつのまにか社会の状況は戒名問題を飛び越えて、葬儀自体の必要性を問うまでにエスカレートしてしまいました。一方で、これまでお寺を支えてきた檀家が、過疎化などの影響で減り始め、やむなく寺門を閉じるところが続出するなど、日本仏教は明治の廃仏毀釈以来の危機を迎えようとしています。
「葬式仏教」という言葉があります。
この言葉に、寺や住職への批判と軽蔑の気分が濃厚に込められていることは、申すまでもありません。マンネリ葬儀に、法外な戒名料を要求されるばかりでは、それも致し方ないことでしょう。
なぜ、かくも仏教への信頼が崩れてしまったのでしょうか――。
国民(檀家)、寺側双方に言い分があるので、一口ではまとめ難いのですが、仏教全宗派が社会構造の変化や宗教への関心の低さなどを見落としたこと、仏を売り物にしようとする心ない一部の僧侶が国民の不信を深めたことを、大きな要因として挙げることができます。
その結果、全国のお寺の約二十パーセントが住職不在の空き寺になり、金持ち寺と貧乏寺の「お寺間格差」が広がるなどの事態を招きました。また、お寺や仏教に頼らない直葬や自由葬が急増して、最後の牙城である「葬式仏教」ももはや盤石ではありません。お寺がやせ細る一方で、葬儀社が焼け太るという、笑うに笑えない状況に陥っているのが現状であります。
こういった状況に、お寺や仏教はいかに対処していけばいいのでしょうか――。
私は、「きちんと葬式仏教をすることでしか日本仏教に未来はない」と思っています。死者供養の場から、このまま仏教が消えていくことが、日本人にとって好ましい状況だとは思いません。葬儀は、現代の日本人が仏教的儀礼に接する数少ない貴重な機会です。それをみすみす手放してもいいのでしょうか。ただしもちろん、これまでのように伝統にあぐらをかき、国民に法外な負担を掛け続けるようなことは論外です。国民の信頼を取り戻すために、今一度、葬儀において仏教が果たす役割とはどういうことなのか、そのことを真剣に考えるべきでしょう。
一信徒である私が、仏教再生の狼煙をあげようなどという、大それた気はまったくありませんが、お寺も国民も現実をしっかりと見据え、日本仏教の将来を一緒に考えるきっかけとなることを祈るばかりであります。
蘊蓄倉庫
『宗教年鑑 平成十九年版』によると、全国にはお坊さんが31万3000人いらっしゃるそうです。うち、14万6000人が、なんと女性だそうです! つまりお坊さんの約47%が「尼僧さん」。これは意外と知られていない事実ではないでしょうか。お坊さんの世界でも、男女平等、女性の「社会進出」が進んでいるという証左ではあるでしょうが、その他にも要因はあるようなのです。詳しくは本書でどうぞ。
担当編集者のひとこと
「葬式仏教」は、必要です。
宗教学者・島田裕巳氏の『葬式は、要らない』(幻冬舎新書)が話題を呼んでいます。「要らない葬式」というのは、つまり従来型の仏教葬のことのようです。「葬式は必要ない」と思っていた人が、それだけ多かったというのは驚きではありますが、実際、お寺やお坊さんに頼らない葬儀が、都市部を中心に急増しているのは事実のようです。確かに、生前ろくに付き合いのなかったお坊さんが読経するだけだったり、戒名料として常識外れの金額を請求されたりすると、「こんな葬儀ならば、要らない」と多くの人が思うのは、ある程度は致し方のないことのように思えます。
しかし、本当に「お葬式は、要らない」のでしょうか?
本書『お坊さんが隠すお寺の話』でも、戒名をはじめ、同様の問題を扱っています。けれど、結論は逆。「それでも、お葬式は必要」。死者を弔う儀式というものを軽視してはいけないと述べています。
ただでさえお寺は、過疎化や後継者不足に悩まされていて、すでに全国のお寺のうち20%が住職のいない空き寺になっているようです。加えて、葬儀における仏教離れがこれ以上進むと、それこそ死活問題となります。
檀家さんの不信を招いた悪弊を見直し、きちんと葬式をする――これしか日本仏教が生き残る道はない、本書ではそう説いています。
2010/03/25
著者プロフィール
村井幸三
ムライ・コウゾウ
1925(大正14)年福島県生まれ。仏教研究家。盛岡高等農林学校(現・岩手大学農学部)卒業。農林省、福島民報、福島テレビに勤務。1985年頃より仏教史の研究に没頭。著書に『山のお寺の上人さま』『日光院はじまり物語』『お坊さんが困る仏教の話』など。