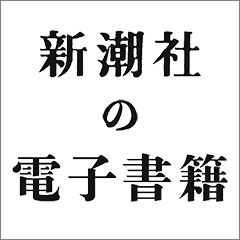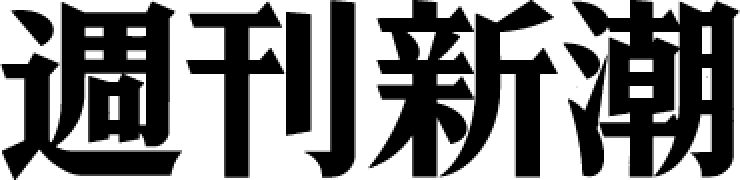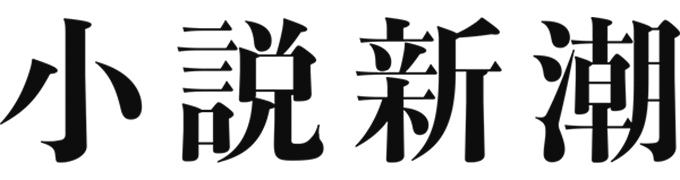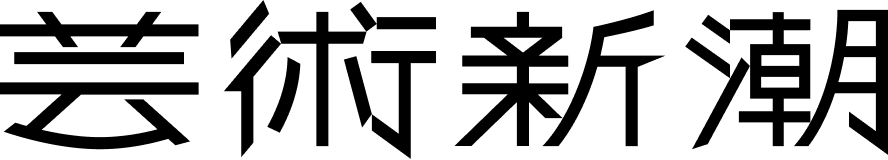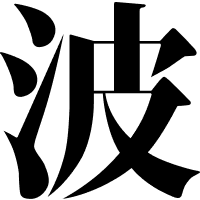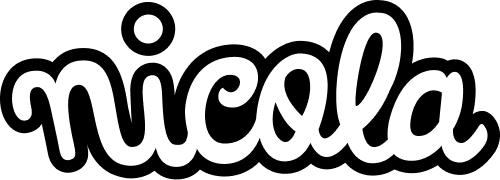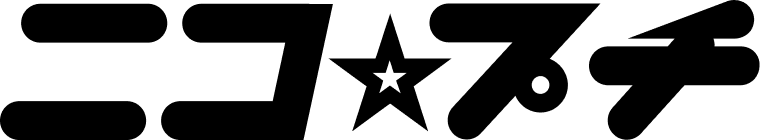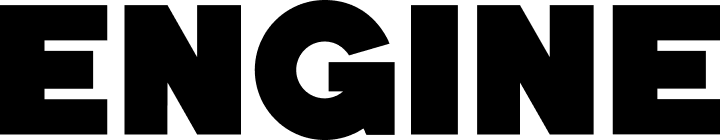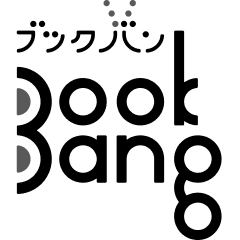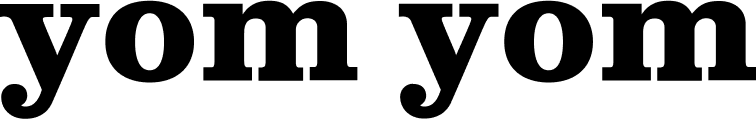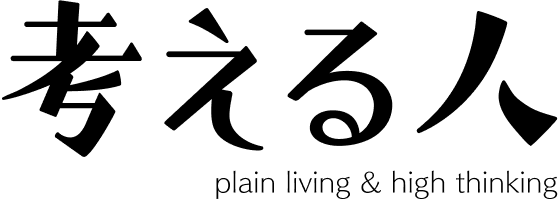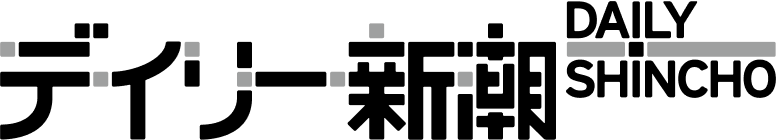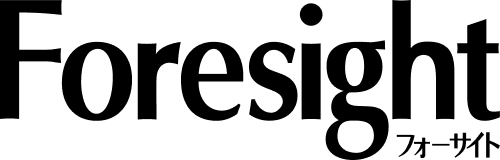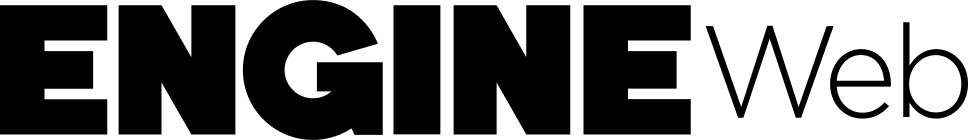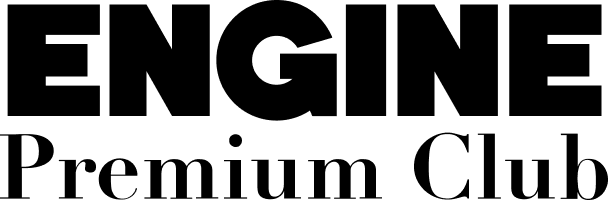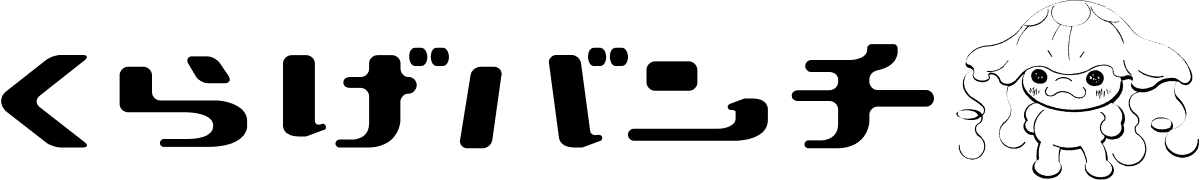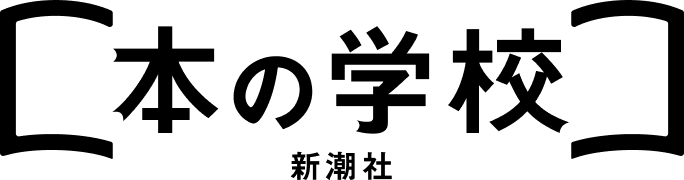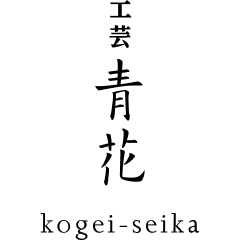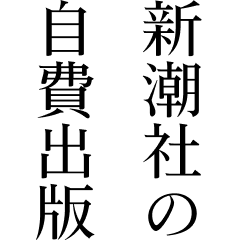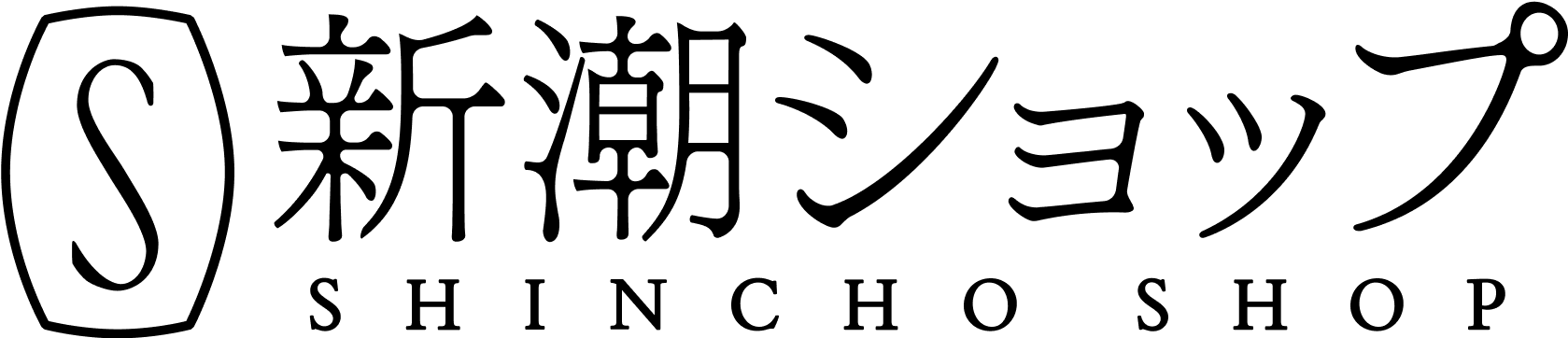未完のファシズム―「持たざる国」日本の運命―
2,090円(税込)
発売日:2012/05/25
- 書籍
- 電子書籍あり
昭和の軍人たちは何を考え、一九四五年の滅亡へと至ったのか。
天皇陛下万歳! 大正から昭和の敗戦へ――時代が下れば下るほど、近代化が進展すればするほど、日本人はなぜ神がかっていったのか? 皇道派vs.統制派、世界最終戦論、総力戦体制、そして一億玉砕……。第一次世界大戦に衝撃を受けた軍人たちの戦争哲学を読み解き、近代日本のアイロニカルな運命を一気に描き出す。
「高みの見物」と「成金気分」
徳富蘇峰、日本人を叱る
伊勢喜之助中佐の弾丸効力調査
殲滅戦思想の密教と顕教
「皇道派」とは何か
「統制派」とは何か
「八紘一宇」の構想と挫折
「天皇陛下万歳」でなぜ死ねるか
一九四一年の死生観
玉砕という必勝哲学
あとがき
書誌情報
| 読み仮名 | ミカンノファシズムモタザルクニニホンノウンメイ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮選書 |
| 雑誌から生まれた本 | 波から生まれた本 |
| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |
| 判型 | 四六判変型 |
| 頁数 | 352ページ |
| ISBN | 978-4-10-603705-4 |
| C-CODE | 0331 |
| ジャンル | 日本史 |
| 定価 | 2,090円 |
| 電子書籍 価格 | 1,320円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2012/11/23 |
書評
青島戦役から敗戦へ、軍人が辿った道
〈著名人が薦める〉新潮選書「私の一冊」(5)
日本ほど近代の総力戦に不向きだった国もない。総力戦に必要な工業資源がまったく欠乏し、人的資源も十分というわけでない。とくに著者が強調する弱さは、明治憲法の体制には総力戦を阻む構造がはらまれていた点にある。帝国憲法は政治力の集中を天皇大権への侵害として嫌ったからだ。
しかも、日本は「中途半端に大きかった」のであり、小国でなかったあたりに日本が妙に背伸びする根拠があった。何によらず背伸びは危険を伴い、転んだり打ち所が悪いと国家さえ滅びる。この「持たざる国」が自滅自殺しないにはどうすればよいのか。著者は、資源もなく統率力もない日本が総力戦の時代に生きる術を考えた軍人として、小畑敏四郎、石原莞爾、中柴末純、酒井鎬次らをとりあげ、「持たざる国」にふさわしい日本陸軍の方策は何であったのかを問うのである。
一九四五年の敗戦の悲劇は、日本が第一次大戦で「成金気分」を味わいながら、新しい戦争の厳しさを理解できなかった知的貧困に原因の一端がある。青島出兵でドイツの要塞を落とした司令官・神尾光臣は、砲兵や工兵との連携によって火器を集中的に運用し、犠牲を最小限に抑えながら、近代戦の理想を確かに理解した。しかし、青島だけでも手一杯の日本は、もっと規模の大きな物量戦ともなるとお手上げであった。
ソビエト・ロシアという仮想敵国相手の本格的な会戦が開かれるなら、どのくらいの物量が必要になるか見当もつかない。そこで改訂された『統帥綱領』や『戦闘綱要』に魂を入れた「作戦の鬼」小畑敏四郎は、兵隊や兵器や弾薬が足りなくて当たり前だ、それで戦ってこその皇軍だと開き直る。また、敵の虚をつく夜襲や夜間移動を駆使して優勢な敵を圧倒する信念をもつべきだというのだ。ただし小畑は、英米ソのような「持てる国」相手に戦争できる能力がない日本にとって、やむをえないのは防衛戦争だけであり、避戦に徹するべきだというホンネを隠していたというのだ。他方、石原莞爾は日本を「持てる国」にすればよいと考え満州国の建設に乗り出した。しかし、日本が進歩すれば米英もそれ以上に発展するので、ソ連のように計画統制の経済を実現することで何とかして米英に伍せると信じたのである。しかし、石原は避戦の小畑と違って、世界最終戦争まで力を蓄えて将来米国と決戦をすると夢想した。
この二人と異なり工兵の中柴が精神力の価値を無限大に評価したのは興味深い。彼は、東条英機の『戦陣訓』の事実上の執筆者として死を恐れぬ兵士教育で「持てる国」に匹敵する戦闘力を高めようとしたのだった。一方、酒井は長期総力戦をやれば敗北必至の日本も、奇襲や電撃戦で短期に勝利し、早期講和に持ち込めば勝機はあると信じた。陸軍航空隊と戦車部隊の推進者であった酒井は、機械化部隊を歩兵の作戦に合わせて分散運用する東条のような旧式の軍人と衝突した。東条による石原の予備役編入よりも酒井の予備役のほうが一年も早かったというから余程に東条に嫌われたのだろう。
音楽評論家でもある著者の歴史観は格別に独創的というわけではないが、歴史の切り口や人物への見方に冴えが見られるのは魅力である。
(やまうち・まさゆき 東京大学名誉教授)
「文藝春秋」2012年8月号 「文藝春秋BOOK倶楽部」より

インタビュー/対談/エッセイ
昭和の軍人たちは何を考えていたのか
――近代日本とは何だったのか? 本書のテーマを一言でまとめるとそうなりますが、しかしアプローチの仕方が、従来の近代日本論とはかなり違いますね。
ひとつには、第一次世界大戦の意味合いを重視したことでしょうか。従来の図式だと、日露戦争の勝利から第二次世界大戦の敗北へ、という流れで見ていく。つまり日露戦争で列強の仲間入りを果たし、大正はデモクラシーで比較的平和な時代だったけれども、昭和初年の世界大恐慌で揺さぶられ、軍部が暴走し始めて社会はファッショ化し、日米戦争に突入した挙句に滅びた。この図式が間違いとは言えません。しかし、大正年間には第一次世界大戦という、人類史上初めて「世界大戦」と呼ばれた長期総力戦が行われた。この戦争の衝撃は近代日本を語るうえであまりに軽視されてきたのではないか。むしろそこを基点にすると、時代の流れがきれいに辿れるのではないか。
――しかし当時の日本人は、実際のところ、第一次大戦をそんなに深刻に受けとめていたのでしょうか。
たしかに多くの日本人は高みの見物を決めこんでいました。戦争特需でバブル並みの好景気にも恵まれた。しかし、徳富蘇峰のように、「成金気分」に酔いしれる暢気な日本人を叱りつけた思想家もいましたし、とりわけ軍人たちは第一次世界大戦におおきな衝撃を受けていたのです。次なる戦争が起きるとすれば、それはもっと大規模な総力戦になるに違いない。兵器にせよ兵士にせよ、またそれを支える資源や経済にせよ、とにかく莫大な物量を備えていなければならない。だが、今の日本には、世界の列強に伍していけるほどの国力はない。では「持たざる国」日本が「持てる国」相手の戦争に勝つためにはどうすればよいのか……。こういった冷静な現状認識と痛切な危機意識を軍人たちは共有していた。もちろん「どうすれば」という点に関しては、考え方の相違や対立がありましたけれど。
――その共通認識と相違・対立に目配りしながら、昭和の軍人たちの著作や報告書や綱領が読み解かれ、ひいては一九四五年の敗戦へ至る「持たざる国」日本の運命が描かれていきます。
陸軍や海軍、あるいは大本営の公式見解や統一方針ではなく、むしろ個々の軍人たちの思想に焦点を絞ってみたのです。昭和の軍人たちの戦争観・戦争哲学を読み解き、近代日本に光を当てる。従来の研究にはなかった視角かと思います。でも実際、「皇道派」の小畑敏四郎や「統制派」の石原莞爾、さらには酒井鎬次や中柴末純といった軍人たちの著作を読み込んでいくと、彼らが第一次大戦の衝撃を身にしみて感じ、またそれを前提として日本の進むべき途をそれぞれ模索していたことがよく分かります。小畑は「持たざる国」の身の丈に合った戦争を考え、石原は「持たざる国」を「持てる国」にしてから「世界最終戦」に勝利するという遠大なヴィジョンを描き、酒井は「速戦即決」の電撃戦以外に日本の活路はないと思い、そして中柴は物資や物量の不足を補うために「精神主義」を賞揚した。
――詳しい経緯や背景は本書の叙述に譲るとして、この「精神主義」が、やがて日本国民にも浸透していきます。
最もファナティックな精神主義者は中柴末純でしょう。しかし「一億玉砕」を賛美し正当化しようとした彼のファナティスムでさえ、ある意味で、現実に根ざしたものでした。日本が「持たざる国」であることを重々承知していたからこそ、背伸びをするために「精神」という下駄を履かせて、持たざる物量をカバーしようとした。日本はじっさい背伸びをし過ぎて悲惨な結末を迎えたわけですが、それにしても日本人はなぜ、近代化が進展すればするほど神がかっていったのか。そのあたりのアイロニカルな事情は、第一次世界大戦の衝撃を始点にし、中柴末純の思想を終点にして見てゆくと、鮮明になるように思います。
――とはいえ、これは軍人ばかり登場する本ではありません。文学者の話がまた面白い。童話作家として知られる小川未明が第一次大戦をどう捉えていたか、宮澤賢治の『銀河鉄道の夜』と石原莞爾の『世界最終戦論』はどうリンクするのか。
有島武郎の岳父は青島戦役の将軍でしたしね。
――本書は小社の『波』に連載されたものに、かなりの加筆がなされて出来上がったものです。連載中に3・11がありました。なにか意識されましたか。
ここで描いたのは主に一九一四年から四五年までの日本です。戦後の話は皆無に近い。でも書き手としては3・11以降、近代と現代がリアルタイムで重なるような感覚がありました。今回私たちは日本が世界に冠たる地震大国であることを痛感させられたわけですが、原子力発電のリスクについては欧米並みかそれ以下にしか見積らずにやって来た。かつては戦争に勝つために精神力という非科学的な下駄を履いたとすれば、戦後は経済成長のために原子力の安全神話という科学的な下駄を履いてきた。リスクを軽視してまで背伸びをして生きるという、中途半端な近代先進国としてのあり方は、今も変わっていないのではないでしょうか。
(かたやま・もりひで 慶應大学法学部准教授)
波 2012年6月号より
担当編集者のひとこと
日本人はなぜ「天皇陛下万歳!」で死ねたのか
百年ほど前の日本はどんな国だったのか。そしてそれから三十年のあいだに、この国はどんな運命を辿り、いったん滅びたのか。滅ばざるをえなかったのか。
これが本書のテーマです。大正初年から昭和二十年の敗戦までの物語。すこし堅い言い方をするなら、近代日本論。著者はこの大きなテーマを、まるで友人に話して聞かせるような親密な筆致で論じていきますが、その際、斬新な切り口をふたつ用意しました。
ひとつは、大正三年(一九一四)に勃発した第一次世界大戦の意味合いを重視し、人類史上初めて「世界大戦」と呼ばれたこの長期総力戦の衝撃を基点として、時代の流れを追っていくこと。もうひとつは、大正・昭和の軍人たちの戦争観・戦争哲学を読み解くことによって、彼らが第一次大戦の衝撃をどう受けとめ、また受けとめ損なったかをきれいに腑分けしながら明らかにすること。
そこから何が浮かび上がってくるでしょうか。中途半端な近代先進国として必死に背伸びしようとしたわが国の姿です。たしかに百年前の日本は世界の列強の仲間入りを果たしていたものの、欧米の列強に伍していけるほどの国力はなかった。軍事力、経済力、そして資源に関して、アジアの後進国に比せば「持てる国」だったけれど、欧米の先進国に比せば「持たざる国」でした。そんな国が、第一次大戦の次に予想される世界的な総力戦にどうしたら勝てるのか。精神主義に頼るのか、物質主義に転換するのか。そもそも「天皇陛下万歳!」が明治や大正よりも昭和になってから声高に叫ばれるようになったのはなぜか。近代化が進めば進むほど、日本国民はどうして神がかっていったのか……。
本書には「持たざる国」日本の、そんなアイロニカルな運命が活写されています。とはいえ、これは軍人ばかり登場する本ではありません。小川未明や宮澤賢治の短篇の読み解きが要所で興趣を添えています。著者の硬軟とりまぜた物語術をご堪能ください。
2012/05/25
著者プロフィール
片山杜秀
カタヤマ・モリヒデ
1963年宮城県仙台市生まれ。政治思想史研究者、音楽評論家。慶應義塾大学法学部教授。慶應義塾大学法学部政治学科卒業、同大大学院法学研究科後期博士課程単位取得退学。大学院時代からライター生活に入り、『週刊SPA!』で1994年から2003年まで続いたコラム「ヤブを睨む」は『ゴジラと日の丸――片山杜秀の「ヤブを睨む」コラム大全』(文藝春秋)として単行本化。主な著書に『音盤考現学』『音盤博物誌』(アルテスパブリッシング 吉田秀和賞・サントリー学芸賞)、『未完のファシズム――「持たざる国」日本の運命』(新潮社 司馬遼太郎賞)、『近代日本の右翼思想』(講談社選書メチエ)、『見果てぬ日本――司馬遼太郎・小津安二郎・小松左京の挑戦』(新潮社)、『鬼子の歌――偏愛音楽的日本近現代史』(講談社)、『尊皇攘夷――水戸学の四百年』(新潮選書)など。