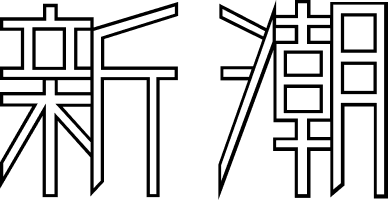ブラック オア ホワイト
1,650円(税込)
発売日:2015/02/20
- 書籍
夢を見なければ人生の三分の一は空白だ。それは罪だと思わないか。
書評
白い夢と黒い夢がくれるもの
人に話したくなるような夢を見ても、実際に話すとなると躊躇してしまう。内容があまりに個人的だと、気恥ずかしさが勝つ。自分の夢が、他人にとって面白く興味深いもの、という自信もない。
たとえば「龍の形をした雲を見たんですよ」と話したところで、実物のその雲を見ていない相手にとっては、まさに雲をつかむような話であろう。
そんなつかみどころのない「夢」を小説に取り込んだらどうなるか? これがとてつもなく愉快で、恐ろしい。小説の中の夢を脳内のスクリーンに映す快感を覚えた。
同級生の葬儀で再会した「私」と都築君。定年までの年数を相当残して会社を辞めた都築君から都心の高層マンションに誘われて、いつのまにか彼の夢の話を聞くことになる。エリート商社マンだった都築君から聞かされる幸福な「白い夢」と、グロテスクな「黒い夢」。その不思議な夢の話に引き込まれていく「私」。
夢の背景となるのは日本のバブル期。若い人が聞けば、昔話か、まるでよその世界の出来事だろうが、この国の土台には、向かうところ敵なしで経済大国を築き上げた日本人がいたのだ。そのひとりである都築君は、出張先のスイスの湖畔のホテルで、バトラーに硬い枕を注文する。そうして用意されたのが、それぞれ黒と白のカバーの掛かった二つの枕。
「ブラック・オア・ホワイト?」
この情景からすでに夢の世界が始まっているようだ。眠りの始まりは夢の始まりに通ずる、どこまでも曖昧で甘美な世界。筆で夢の世界に引きずり込まれたら、あとは行く末を見届けるしかない。
「白い夢」を堪能した後「黒い夢」を見ると、前者では味方だった人が、後者では悪意むき出しの顔を見せる。はたしてどちらが現実の顔なのか。ただし、これはあくまで夢なのだから、本当の顔などわからないのだ。そして魅惑的な女性も登場し、都築君を翻弄する。
自分の中にある自分でも気づいていない感情が夢にあらわれる、それはきっと誰にも覚えがあることではなかろうか。だからこそ都築君が見る夢の意味を考えてしまう。いったい何を暗示しているのだろう。たかが夢、されど夢。幻想と言い切れない自身の深層心理を探りたくなる。
一方で、「白い夢」と「黒い夢」を聞かされる「私」は、都築君がなぜ夢の話をするのか、と考える。都築君は自らの夢のせいで、順調だったキャリアを踏み外し、どんどん道を失っていく。それが「私」とどんな関係があるのか。「私」に語りながら、つまり読み手に語っている。やがて都築君の夢が、現実へと近づいてくるが、この先の夢の結末は見た(読んだ)人のもの。
ところで、夢を見ている時の感覚を思い出させる場面がある。都築君が京都で見た夢で、彼は武士になっている。それを夢だと自覚しながら、急に足に冷たい水がかかった際、「無礼者!」と水をかけた小僧を大声でしかりつける。
自分の立場も言葉使いも、時代と場面に合わせているのが面白い。たしかに夢を見ている自覚があるときには、その夢の世界のルールにいつのまにか自分を合わせている。その瞬間は、夢を楽しんでいるのだ。タイムスリップでもなく、異界に迷い込んだわけでもなく、あくまで自分の夢で。
一日は誰にとっても二四時間。「一日のうち、八時間を働き、八時間を眠り、八時間をそのほかのことに使っている。つまり、人生の三分の一は眠っているんだ」
人生の三分の一は、睡眠という誰とも共有出来ない孤独な時間の中にいる。よく考えてみると、夢と小説は似ている。小説は、作家の見ている夢のようなものだ。それを言葉というツールで読者に伝える。作家と読者はまったく同じ「夢」を見ることは出来ないけれど、よく似ている「夢」を見ているのだと思うと、三分の一の孤独が癒やされそうだ。
(なかえ・ゆり 女優・作家)
波 2015年3月号より
単行本刊行時掲載
日本人の怪物性が目覚める前に
高いエンターテインメント性と思想的な深さを兼ね備えた感動的作品だ。
学生時代の友人であった「都築君」が私を高層マンションの自宅に招く。二人とも六十代になった。〈親しかったクラスメイトとしばしば会ったのは二十代までで、それぞれが所帯を持ち、仕事も忙しくなると自然に交流はなくなった。三十代と四十代のおよそ二十年間は、たしかに誰がどこで何をしていたかわからなかった〉。自然と、話は空白の時代の出来事になるはずだ。しかし、都築君の話は、少し変わっていた。これまでに見た夢の話だ。その夢の内容は、寝るときの枕の色によって変わってくる。白い枕のときは楽しい夢、黒い枕の時は苦しい夢を見る。
ユダヤ教にカバラーという神秘思想がある。カバラーとは、ヘブライ語で「受け入れ」「伝承」という意味だ。人間の知恵には、理性で割りきれる光の部分と、理性では説明できないドロドロとした闇の部分がある。光の領域を拡大すると、気づかないうちに闇の領域も拡大している。そして、その乖離は解消されることになると説く。乖離が大きければ大きいほど、解決のときに激しい衝撃が起きる。カバラー思想は、十九世紀末に人間の心の闇を分析する心理学という形で再登場した。浅田次郎氏がこの作品で取った手法は、カバラー思想を彷彿させる。この作品が、英語、ドイツ語、ヘブライ語などに訳されれば、大きな反響を呼ぶと思う。
都築君の父も祖父も商社マンだった。ただし、祖父はもともと南満州鉄道の理事で、戦後、公職追放になった後に商社に勤務することになった。都築君は、父と祖父がどのような仕事をしたかについては、ほとんど知らない。ところが、都築君の夢は、第二次世界大戦前、国際連盟による日本の委任統治領(事実上の植民地)だったパラオ、1980年代の中国やインド、幕末の京都などが舞台となる。
個々のエピソードに迫真性があるのは、浅田氏がこの作品を準備するにあたって、総合商社の第一線で活躍した人々から詳細な取材をしたからと思う。不祥事で北京の日本大使館に呼び出されたときの状況について、こんな記述がある。〈大使は別件で外出している、というようなことを参事官は言った。つまり、大使はこの案件にかかわるべきではない、という意味さ。背筋が凍ったね。国家間の外交問題に発展しかねない大問題だ、と言っているようなものだ。/国家を代表する特命全権大使は、慎重でなければならない。だから事案が重大で、なおかつ不可測であるときは、「別件で外出」する〉。こういうことは、実際に経験した人から取材しないとわからない。
明治以降の日本の近代化の過程で、軍隊と総合商社は不可欠の存在だった。第二次世界大戦後、武力によって国際政治に影響力を与えることを断念せざるを得なくなった日本は、経済力のみで生き残らざるを得なくなった。その点からすると、総合商社は、戦後の日本国家そのものだったのである。しかし、戦後は、戦中、戦前と連続している。〈大陸への進出は軍部の独走ではなく、財閥の利権を護るためだったと聞いたことがある。噂ではない。入社して間もないころ、酔っ払った担当役員の口から、まことしやかに聞かされた。世代からするとその役員は、当事者のひとりだったはずだ。/僕らの歴史認識では、戦前と戦後の日本に連続性がない。だがそれは、戦後教育を受けた僕らの錯覚で、べつに日本人がそっくり入れ替わったわけじゃないんだ。/(中略)それが歴史の真相だとすると、辻褄が合うじゃないか。元大本営参謀がのちに総合商社を率いて活躍したことも、元満鉄理事がうちの会社の役員に迎えられたことも。/本質は何ひとつ変わっていない。そう考えたとたん、背筋が凍りついたよ。商社マンとしての僕の不幸は、ミステイクでも不運でもなくて、総合商社という怪物の生理によって必然的にもたらされたのではないか、と思ったんだ。/その仮定が正しいとしよう。/世界大戦まで惹き起こした怪物にとって、人殺しなど朝飯前さ〉
現在、過激組織「イスラム国」が、欧米やロシアのみならず、日本もテロ攻撃の標的にしている。日本人人質殺害事件によって「イスラム国」の脅威がリアルになった。「目には目を、歯には歯を」ということで、日本人の中に潜んでいた怪物性が目を覚ますかもしれない。自らの姿を等身大で認識したいと考えるすべての日本人にこの本を勧める。
(さとう・まさる 作家・元外務省主任分析官)
波 2015年3月号より
単行本刊行時掲載
著者プロフィール
浅田次郎
アサダ・ジロウ
1951(昭和26)年、東京生れ。1995(平成7)年『地下鉄(メトロ)に乗って』で吉川英治文学新人賞、1997年『鉄道員(ぽっぽや)』で直木賞、2000年『壬生義士伝』で柴田錬三郎賞、2007年『お腹召しませ』で司馬遼太郎賞、2008年『中原の虹』で吉川英治文学賞、2010年『終わらざる夏』で毎日出版文化賞、2016年『帰郷』で大佛次郎賞、2019(令和元)年に菊池寛賞をそれぞれ受賞した。『蒼穹の昴』『椿山課長の七日間』『薔薇盗人』『憑神』『夕映え天使』『赤猫異聞』『ブラック オア ホワイト』『母の待つ里』など多彩な作品があり、幅広い読者を獲得している。