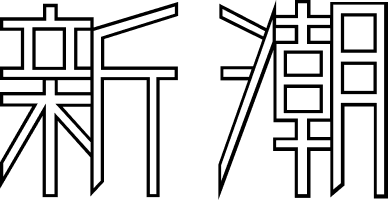アスクレピオスの愛人
1,760円(税込)
発売日:2012/09/28
- 書籍
昼は崇高な使命に身を捧げる女医。しかし白衣を脱いだ夜の彼女は、どこまでも罪深き女……。アスクレピオス、それは医術を司る神の名。
WHOのメディカル・オフィサーとして感染症の最前線で働く志帆子。命を賭してウイルスと戦う彼女が本当に求め続けているものとは? 純粋であるがゆえに残酷で、ひたむきさゆえに奔放――。男たちを翻弄してやまない、マリコ文学史上最強のヒロイン誕生! 東京、ジュネーブ、アンゴラ、バンコクを舞台に、さまざまな問題を抱える現代医療の世界を鮮烈に生き抜く女を描く、衝撃のメディカル・ロマン。
目次
第一章 フェーズ4
第二章 金の糸
第三章 傷痕
第四章 疑惑
第五章 対峙
第六章 出発
第七章 逆転
第二章 金の糸
第三章 傷痕
第四章 疑惑
第五章 対峙
第六章 出発
第七章 逆転
書誌情報
| 読み仮名 | アスクレピオスノアイジン |
|---|---|
| 雑誌から生まれた本 | 週刊新潮から生まれた本 |
| 発行形態 | 書籍 |
| 判型 | 四六判変型 |
| 頁数 | 368ページ |
| ISBN | 978-4-10-363110-1 |
| C-CODE | 0093 |
| ジャンル | 文芸作品、文学賞受賞作家 |
| 定価 | 1,760円 |
書評
波 2012年10月号より 『アスクレピオスの愛人』刊行記念特集 個人性と社会性の黄金バランス
女性性は個人性の象徴で、男性性は社会性の象徴といわれる……。働く女性の多くを立ち止まらせるのは、この個人性と社会性のバランスがうまくとれなくなったときだろう。特殊な技能が必要な職種や、多くの部下を抱えるエグゼクティブ・キャリア・ウーマンなら尚更で、キャリアを重ねれば重ねるほど、内面のみならず、見た目でも、オジサンだかオバサンだかわからなくなる危機と葛藤しなければならない。
だが、林真理子さんが描くキャリア・ウーマンは、いつもこの個人性と社会性のバランスが絶妙なのだ。いや、24時間、365日、どこを切り取ってもバランスが良いというワケではなく、グーッと社会性に寄る(寄りすぎる?)時間や日もあれば、リバウンドのように思う存分、個人性に浸りきるときもある。だからこそ、こんなにも魅力的なヒロインに出来上がるのだろう。
こうして書くのは簡単だが、やってるほう(ヒロイン)も、やらせているほう(林さん)も、人の3倍は汗をかいている。オンとオフのスイッチとかいう俗っぽい言葉では表しきれない、個人性と社会性の黄金バランスには、ハンパない集中力と行動力が必要なのである。
『アスクレピオスの愛人』のヒロイン、佐伯志帆子は、WHOのメディカル・オフィサー。バツイチで、一人娘は元夫と暮らしている。その優秀さとワールドワイドな仕事ぶりは、たとえば英語、フランス語だけでなく、タイ語、スペイン語、スワヒリ語もできる……ということでもわかろう。
そんな彼女を仕事人として尊敬しつつ、ふと見せるチャーミングな仕草や大人の色気、モテ女ならではの大胆さと勝手さ、経済力のある女性特有の嗜好を愛してやまない男性たち。世代はさまざまだが、職業は全員、医者である。
医者と一口に言っても、実家の職業や経済状況、出身大学から始まって、目指したジャンル、勤務先、そこでのポジションなどによって、見え方も在り方も大きく異なるものだ。根っこにある志の高さは同じでも、厳然たるヒエラルキーが存在するし、医者ならではの常識と非常識が混在する。同じ医者として、互いの事情や立場がわかりすぎるだけに、ふとした瞬間、とてつもない嫉妬や羨望の想いに陥るのである。志帆子をとりまく男性医師のなかで、もっとも年配の者による「金か名誉かのどちらかが欲しいもの」という決めつけは、社会性の生き物である男性ならではの言葉だろう。
どんな職種でも、働く女性はいまだに男尊女卑の四文字を多かれ少なかれ感じているし、闘っている。その闘いに疲れて、女をウリにすることを選択する女性も少なくない。いいとか悪いとかではなく、林さんは、そういう女性を目ざとく見つけ、描いていく。志帆子の元夫の妻になった元キャビン・アテンダントの結花の生きざまと感情もまた、バブルという時代の波と出会い、別れた経験のある女性には、痛いほどわかろう。こうした登場人物の感情は当然、景気とかトレンドにも大きく左右されるし変化していく。
その時代時代の空気感や細かいディテールを描くのは、もともと林真理子さんが大得意とするところだ。「もしかして、そこで働いていた?」と思わせるほど、あまりに“事情通”ゆえ、その都度、舞台になった業界やヒロインと同じ職業に就く者たちを震撼させてきた。今回も、日本の医学界や国際機関、はたまた厚労省をはじめとした省庁をもアッと言わせるシーンが随所に出てくる。ちょっと見聞きするだけでは書けない業界だけに、いつも以上に事細かな取材が必要だったろうと推察できる。このパワフルな取材力もまた、林さんの小説の醍醐味といえよう。
特に、後半の、産婦人科における死産から医療裁判に至る部分は、まさしく、「平成の『白い巨塔』」。また、高齢出産で子をもった林さんならではの産婦人科や小児科の医師に対する冷静な視点とダイナミックな描写は圧巻だ。
実は私は医者の娘である。父だけでなく祖父も医者で、父方は、いわゆる医者の家系だ。父が私に医者の道に進むように願ったことは、只の一度もないと思うが、小学校から入った私立のエスカレーター式学校の同級生には、医者になった女子が4人もいる。全員、医者の娘である。思えば、彼女たちはみな、仕事でもプライベートでも肉食系女子だったが、50代半ばのいま、どうしていることだろう。『アスクレピオスの愛人』を読んで、彼女たちにすごく会いたくなった。
仕事柄、ドラマ化や映画化の際のキャスティングも考えてしまう。俳優の顔が浮かびやすいのも林さんの作品の大きな特徴だろう。私の中で志帆子を演る女優はもう決まっている。

▼進藤奈邦子/「作家・林真理子」に書かれるということ
だが、林真理子さんが描くキャリア・ウーマンは、いつもこの個人性と社会性のバランスが絶妙なのだ。いや、24時間、365日、どこを切り取ってもバランスが良いというワケではなく、グーッと社会性に寄る(寄りすぎる?)時間や日もあれば、リバウンドのように思う存分、個人性に浸りきるときもある。だからこそ、こんなにも魅力的なヒロインに出来上がるのだろう。
こうして書くのは簡単だが、やってるほう(ヒロイン)も、やらせているほう(林さん)も、人の3倍は汗をかいている。オンとオフのスイッチとかいう俗っぽい言葉では表しきれない、個人性と社会性の黄金バランスには、ハンパない集中力と行動力が必要なのである。
『アスクレピオスの愛人』のヒロイン、佐伯志帆子は、WHOのメディカル・オフィサー。バツイチで、一人娘は元夫と暮らしている。その優秀さとワールドワイドな仕事ぶりは、たとえば英語、フランス語だけでなく、タイ語、スペイン語、スワヒリ語もできる……ということでもわかろう。
そんな彼女を仕事人として尊敬しつつ、ふと見せるチャーミングな仕草や大人の色気、モテ女ならではの大胆さと勝手さ、経済力のある女性特有の嗜好を愛してやまない男性たち。世代はさまざまだが、職業は全員、医者である。
医者と一口に言っても、実家の職業や経済状況、出身大学から始まって、目指したジャンル、勤務先、そこでのポジションなどによって、見え方も在り方も大きく異なるものだ。根っこにある志の高さは同じでも、厳然たるヒエラルキーが存在するし、医者ならではの常識と非常識が混在する。同じ医者として、互いの事情や立場がわかりすぎるだけに、ふとした瞬間、とてつもない嫉妬や羨望の想いに陥るのである。志帆子をとりまく男性医師のなかで、もっとも年配の者による「金か名誉かのどちらかが欲しいもの」という決めつけは、社会性の生き物である男性ならではの言葉だろう。
どんな職種でも、働く女性はいまだに男尊女卑の四文字を多かれ少なかれ感じているし、闘っている。その闘いに疲れて、女をウリにすることを選択する女性も少なくない。いいとか悪いとかではなく、林さんは、そういう女性を目ざとく見つけ、描いていく。志帆子の元夫の妻になった元キャビン・アテンダントの結花の生きざまと感情もまた、バブルという時代の波と出会い、別れた経験のある女性には、痛いほどわかろう。こうした登場人物の感情は当然、景気とかトレンドにも大きく左右されるし変化していく。
その時代時代の空気感や細かいディテールを描くのは、もともと林真理子さんが大得意とするところだ。「もしかして、そこで働いていた?」と思わせるほど、あまりに“事情通”ゆえ、その都度、舞台になった業界やヒロインと同じ職業に就く者たちを震撼させてきた。今回も、日本の医学界や国際機関、はたまた厚労省をはじめとした省庁をもアッと言わせるシーンが随所に出てくる。ちょっと見聞きするだけでは書けない業界だけに、いつも以上に事細かな取材が必要だったろうと推察できる。このパワフルな取材力もまた、林さんの小説の醍醐味といえよう。
特に、後半の、産婦人科における死産から医療裁判に至る部分は、まさしく、「平成の『白い巨塔』」。また、高齢出産で子をもった林さんならではの産婦人科や小児科の医師に対する冷静な視点とダイナミックな描写は圧巻だ。
実は私は医者の娘である。父だけでなく祖父も医者で、父方は、いわゆる医者の家系だ。父が私に医者の道に進むように願ったことは、只の一度もないと思うが、小学校から入った私立のエスカレーター式学校の同級生には、医者になった女子が4人もいる。全員、医者の娘である。思えば、彼女たちはみな、仕事でもプライベートでも肉食系女子だったが、50代半ばのいま、どうしていることだろう。『アスクレピオスの愛人』を読んで、彼女たちにすごく会いたくなった。
仕事柄、ドラマ化や映画化の際のキャスティングも考えてしまう。俳優の顔が浮かびやすいのも林さんの作品の大きな特徴だろう。私の中で志帆子を演る女優はもう決まっている。
(やまだ・みほこ 放送作家)
▼進藤奈邦子/「作家・林真理子」に書かれるということ
波 2012年10月号より 『アスクレピオスの愛人』刊行記念特集 「作家・林真理子」に書かれるということ
「アンアン」をはじめとする雑誌のコラムで、ほんわかとした真理子節、そう、あのふっくらとしたくちびるがイメージさせる、親しみのわくエッセイを真理子さん、と認識していたから覚悟が足らなかった。ご紹介いただいた当初から『女文士』や『ミカドの淑女』などの美しいハードカバーの本をサイン入りで下さっていたのに、組織のリストラやら、2人のティーンエイジャーとイベント好きの友人のいる日常やら何やらで手一杯の毎日、しっかり読む間もないままに週刊新潮の連載小説は始まってしまった。あの献本は、「覚悟せよ」というメッセージだったのに。女としてもいろいろあったのよ、は宇野千代さんや瀬戸内寂聴さんぐらいそのころが遠くなってからはOKだけれど、現在進行形は世間的にかなりNGと思われる。林さんは主人公を磨いて輝かせて、なのにその頂点で彼女を引き摺り下ろして泥沼に這い蹲らせたりする。それで、ああ、普通の人生でよかった、なんて読者の共感をぐぐっと掴む。それが作戦?
「新潮社は林真理子を平成の山崎豊子に育てたい」と仕掛け人、石井昻さんは私に諭した。「ついてはスケールの大きな話が進んでいくにふさわしい背景が必要」「はい」「で、是非ご協力いただきたい。新潮社の取材力がバックです」(ほおー)。週刊新潮は平成を週刻みで記録しているのだから、過ぎ行くこの時代を書き上げるための素材は層をなして築きあげられているわけだ。で、私に求められているのは、背景設定、つまり「大道具係」?
この方面の関係者が読めば私がモデルだということは仕事柄、見当がつくだろうが、やはり林さんの小説だから艶話が展開する。これがそのまま私の素行と誤解されるといけない、というご配慮で、小説の連載が始まる同じ号の週刊新潮に林さんと私のグラビア記事が企画され、そちら方面はあくまでもフィクションです、という林さんの発言も掲載された。
私がモデルのはずのヒロイン佐伯志帆子は、しょっちゅう私と違うことを考え、私が今までにしでかした失敗や犯した罪を元に作り上げた人生の「グラウンドルール」を無視した言動をとる。とくにわが国の新型インフルエンザに対する水際作戦を批判的にみていたりして声を出して笑ったりする。だめ、そんなの、絶対にありえない。日本にしかできないことを、日本政府が日本の国民のためにやってなにが悪い。過剰でもいい、日本はここまでできるんだから、やってもいいじゃない、重症者の比率がさほど高くないことはもっと後にならなければわからなかったことなんだから。オーストラリアだって真剣に鎖国を考えたりしていたし、ベルギーの代表は国際会議のとき、WHOは事実を伝えるだけでいい、国境コントロールをするかしないかは初期情報からわれわれ加盟国で判断する、あれこれ指図するな、と遠まわしに言っていたし。志帆子ときたら恋愛についても、「ルール」をしょっちゅう無視する。あらあら、これじゃあとで泥沼だわ。一言ご忠告差し上げたい、と思ったりする。この「ルール」は、これをネタに本が一冊書けるから、そう簡単には披露できないけれど。
前出の石井さんのもちかけ話も、ジュネーブに取材にいらしたときも、小首をかしげてふんふん、と聞かれていた林さん。華やかで、美しくて、きらきらした世界を書かれるのが身上なのに、「国際」がつくとはいえ、「公務員」の取材には気乗りなさらなかったに違いない。けれどもジュネーブで林先生をお迎えした、厚生労働省から出向中の若きエースたちはイケメンぞろい、しかもスマートでおしゃれ、貧乏ったらしくもなく、理想に燃え、英知をほとばしらせていて、このまんま、このキャストでドラマの撮影に入れそうな勢いだったから、やっと先生の嬉しそうな笑顔を見ることができたし、WHOのメディカルキットからフィールド活動用のコンドームが出てきたときには、好奇心で目を輝かされていた。まさにそのとき、林さんの瞳の中にめらめら燃えていたのは、作家としての闘志だったのだ。
連載開始一週前の前ふり記事に、「作家が書く医療小説をお楽しみに」というようなおっしゃり方をなさっていた。小説は作家が書くに決まっているのに、とそのときの私は思ったのだけれど、どうやら、医療小説の分野は医療畑出身者の独壇場、が常識だったのだということにやっと気がついた。新潮社平成プロジェクト、フィーチャリング林真理子、医療小説『アスクレピオスの愛人』、をどうぞお楽しみに。

▼山田美保子/個人性と社会性の黄金バランス
「新潮社は林真理子を平成の山崎豊子に育てたい」と仕掛け人、石井昻さんは私に諭した。「ついてはスケールの大きな話が進んでいくにふさわしい背景が必要」「はい」「で、是非ご協力いただきたい。新潮社の取材力がバックです」(ほおー)。週刊新潮は平成を週刻みで記録しているのだから、過ぎ行くこの時代を書き上げるための素材は層をなして築きあげられているわけだ。で、私に求められているのは、背景設定、つまり「大道具係」?
この方面の関係者が読めば私がモデルだということは仕事柄、見当がつくだろうが、やはり林さんの小説だから艶話が展開する。これがそのまま私の素行と誤解されるといけない、というご配慮で、小説の連載が始まる同じ号の週刊新潮に林さんと私のグラビア記事が企画され、そちら方面はあくまでもフィクションです、という林さんの発言も掲載された。
私がモデルのはずのヒロイン佐伯志帆子は、しょっちゅう私と違うことを考え、私が今までにしでかした失敗や犯した罪を元に作り上げた人生の「グラウンドルール」を無視した言動をとる。とくにわが国の新型インフルエンザに対する水際作戦を批判的にみていたりして声を出して笑ったりする。だめ、そんなの、絶対にありえない。日本にしかできないことを、日本政府が日本の国民のためにやってなにが悪い。過剰でもいい、日本はここまでできるんだから、やってもいいじゃない、重症者の比率がさほど高くないことはもっと後にならなければわからなかったことなんだから。オーストラリアだって真剣に鎖国を考えたりしていたし、ベルギーの代表は国際会議のとき、WHOは事実を伝えるだけでいい、国境コントロールをするかしないかは初期情報からわれわれ加盟国で判断する、あれこれ指図するな、と遠まわしに言っていたし。志帆子ときたら恋愛についても、「ルール」をしょっちゅう無視する。あらあら、これじゃあとで泥沼だわ。一言ご忠告差し上げたい、と思ったりする。この「ルール」は、これをネタに本が一冊書けるから、そう簡単には披露できないけれど。
前出の石井さんのもちかけ話も、ジュネーブに取材にいらしたときも、小首をかしげてふんふん、と聞かれていた林さん。華やかで、美しくて、きらきらした世界を書かれるのが身上なのに、「国際」がつくとはいえ、「公務員」の取材には気乗りなさらなかったに違いない。けれどもジュネーブで林先生をお迎えした、厚生労働省から出向中の若きエースたちはイケメンぞろい、しかもスマートでおしゃれ、貧乏ったらしくもなく、理想に燃え、英知をほとばしらせていて、このまんま、このキャストでドラマの撮影に入れそうな勢いだったから、やっと先生の嬉しそうな笑顔を見ることができたし、WHOのメディカルキットからフィールド活動用のコンドームが出てきたときには、好奇心で目を輝かされていた。まさにそのとき、林さんの瞳の中にめらめら燃えていたのは、作家としての闘志だったのだ。
連載開始一週前の前ふり記事に、「作家が書く医療小説をお楽しみに」というようなおっしゃり方をなさっていた。小説は作家が書くに決まっているのに、とそのときの私は思ったのだけれど、どうやら、医療小説の分野は医療畑出身者の独壇場、が常識だったのだということにやっと気がついた。新潮社平成プロジェクト、フィーチャリング林真理子、医療小説『アスクレピオスの愛人』、をどうぞお楽しみに。
(しんどう・なほこ WHOメディカル・オフィサー)
▼山田美保子/個人性と社会性の黄金バランス
著者プロフィール
林真理子
ハヤシ・マリコ
1954(昭和29)年、山梨県生れ。1982年エッセイ集『ルンルンを買っておうちに帰ろう』が大ベストセラーになる。1986年「最終便に間に合えば」「京都まで」で直木賞、1995(平成7)年『白蓮れんれん』で柴田錬三郎賞、1998年『みんなの秘密』で吉川英治文学賞、2013年『アスクレピオスの愛人』で島清恋愛文学賞、2020(令和2)年、菊池寛賞を受賞。2022年、野間出版文化賞を受賞。そのほかの著書に『不機嫌な果実』『アッコちゃんの時代』『我らがパラダイス』『西郷どん!』『愉楽にて』『小説8050』『平家物語』など多数。2018年、紫綬褒章を受章。
判型違い(文庫)
この本へのご意見・ご感想をお待ちしております。
感想を送る