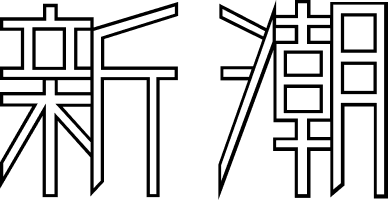電車道
1,760円(税込)
発売日:2015/02/27
- 書籍
鉄道開発を背景に、日本に流れた百年の時間を描いた著者最高傑作!
インタビュー/対談/エッセイ
予想を超える面白さ
【目次】
「電車」を描く意味/変わらずに続く営み
「正しく自由」であること/新しいアイデアとは
「電車」を描く意味
磯崎 羽生さんと最初にお目にかかったのは、僕が勤めている会社の研修でご講演いただいた時でしたが、その後に横尾忠則さんと三人でお会いしたんですよね。横尾さんが「死ぬまでに絶対に会っておきたい人が二人いる。イチローと羽生善治だ」とおっしゃるので(笑)、羽生さんにお願いして横尾さんのアトリエにお邪魔しました。
羽生 ええ、ランチをご一緒した後、だいぶ長い時間お話ししましたね。
磯崎 横尾さんはその日のツイッターに「将棋も文学も美術もその源流はひとつ」とかなり荒っぽいことを書き込んでいますが(笑)、確かにそんな話題も出ましたので、今日もそういったところにまで話を広げられれば、と思っています。
羽生 そうですね。あの時、横尾さんの「Y字路」に描かれた分かれ道というテーマについて話をしたのを覚えています。今回出版されたのは『電車道』という作品ですが、お書きになる前はどのようなテーマをお考えになっていたんですか。
磯崎 僕はいつも、どんな展開になるか自分でもわからないまま小説を書き始めます。今回の場合、家の近くのお寺に洞窟の祠がありまして、何となく昔そこに人が住んでいたような気がするという、最初にあったのはそのイメージだけでした。ですから、書き始めの段階では、電車を描く小説になるなんて、まったく考えていなかったんです。
羽生 そうなんですか。書いている間に次第に構想が浮かび上がってきたということなんですね。
磯崎 ええ。その辺りは百年前は桑畑で、農家がまばらに点在しているような土地でした。それがなぜ今、住宅地に変貌を遂げたのか。調べていくと、鉄道が敷かれて駅ができたことが決定的な契機になったことがわかりました。そこでどうやらこの小説は鉄道の歴史を描いていくことになるのではないかと、朧気に見えてきたんです。
羽生 この小説は長い間の人の営みや時代を描いていますが、電車はそこに繋がってくるものだったんですね。
磯崎 そうですね。調べてみて気づいたのは、現代のわれわれは「電車を使っている」と思っていますが、実は逆なんです。電車を使わざるを得ない場所に、居住地が作られているんです。例えば僕が今住んでいる東京の世田谷はもともと雑木林だらけの土地でした。そこに鉄道が敷かれたわけですが、その電車を利用する人を確保するために、林が切り拓かれて住宅地が作られるんですね。その結果、それまでは職住近接が当たり前だったのに、郊外に住んで通勤するという生活形態が生まれた。つまり、電車を利用せざるを得ないような場所に家を作らされている。その受動性というか、反転した歴史みたいな感じが面白くて、小説に書いてみたくなりました。
羽生 私も実家が八王子という郊外なので幼い頃から電車によく乗っていましたが、電車にはそこに暮らす人々の生活があらわれている気がしますね。通勤ラッシュや終電間際の酔っ払いなど、人間模様を見る思いでした。電車自体は無機的なのですが、何かもの悲しさを感じることがあります。
磯崎 羽生さんは奨励会時代、片道一時間半かけて通われていたんですよね。
羽生 ええ。その頃、対局が夜中までかかると終電もなくなるので、始発まで待って家に帰りました。普通の方々が出勤してくる時に、反対方向に向かって帰るわけです。当時、十五、六歳でしたが、“ああ、自分は道を踏み外してしまった。変な道に進んだんだな”と、リアルに実感したのを覚えています(笑)。
変わらずに続く営み
羽生 本が刊行されてからの反応や、手ごたえはいかがですか。
磯崎 この作品は今まで書いた中で最も長い小説です。書き終えたとき、そういう意味での達成感があったのも事実ですが、それ以上にこんな凄い作品を本当に俺が書いたのか? という驚きの方が大きいですね。とても自分が書いたものとは思えない(笑)。
羽生 ある作家の方が「書いてしまったら、後は自立した子供を陰から見守るような気持ちになる」と言っておられましたが、やはり自分の手から離れていくという感覚が強いんですね。
磯崎 先ほども申し上げた通りで、僕は事前の設計図は作らず、一文ごとにどう繋げたら面白いかだけを考えながら書き継いで、それが最終的に一つの作品になるという書き方なんです。一文をひねり出すのに何日もかかることもあります。そうやって書き上げてみると、確かに成長したわが子のように思えることがありますね。可愛いけれど、作品はやっぱり他者なんです。小説が独り歩きを始めて、書評などで褒められたりすると、益々自分から遠ざかっていく気がしますね。
羽生 今回の作品は何世代にもわたる長い時間を描いていますが、そういった世代を繋ぐ話は何となくセンチメンタルになりやすいように思うんです。それなのに、むしろ淡々と描写されているのがとても印象的でした。
磯崎 有難うございます。おっしゃる通りで、こういった年代記は愛憎入り乱れるウエットな書き方をしようと思ったら、いくらでもそうできるんです。ただ、僕がこの小説を書きながら考えていたのは、個々の人間が直面している過酷な状況や苦難は、実は過去の歴史の中で何度も反復されているということなんです。誰しも自分が直面している問題はシリアスにとらえがちですが、百年前の人にも同じような悩みがあったんだと考えると、それは一つの救いになる。そういう相対化したい気持ちが僕の中にあったことは確かです。
羽生 なるほど。そういえば今日は北陸新幹線の開通日ですが、新幹線ができてもやっていること自体は何も変わらないんですよね。速度が上がって時間が短縮されたという二次的なことはあるにせよ、人間の営みとして考えると、根本的な部分は昔も今も変わっていないなと思います。
磯崎 僕らはとかく“戦前戦後”とか、“インターネット以前と以後”とか、“東日本大震災以前と以後”というように、大きな事象を境に歴史が変わったと考えたがります。でも、実はそういう変化を受け入れながら、人間の営みはずっと続いてきた。その続いてきたという事実の方を、僕はポジティブにとらえたいですね。それは醒めて冷淡に生きるのとは、全く逆の生き方なのだと思います。
「正しく自由」であること
羽生 小説も含めて、人間が文章を書く行為も昔からずっと続いてきていますよね。それに関しては、小説家というお立場でどのように感じておられますか。
磯崎 自分は小説の大きな歴史の中の一部分でしかない、ということは感じています。僕自身、大好きなガルシア=マルケスや北杜夫さんの小説を読んだから今、小説を書いているわけで、今後もしかしたら僕の小説を読んだ若い人が新しい小説を書いてくれるかもしれない。小説を書く際には奇をてらった表面的な新しさを狙うべきではないと、僕は考えています。歴史を受け入れた上で、自分の個性や身体性を通じて表現していく。小説はそうやって再生産され続けていくのだと思います。
羽生 文章は、何でもいいから書くということなら誰にでもできますが、小説のような表現形態になると、違ったプロセスが必要になってきます。その中で自分らしさや個性を出すためには、何が重要なんでしょうか。
磯崎 僕は四十歳過ぎてデビューした、文章修業などもしていない人間で、そんな人間がいうのも何ですが、小説家になりたくてもなれない人の典型的なパターンは、小説への憧れが強すぎる人だと思うんです。小説家や文学を崇拝しすぎることは、かえってマイナスに働きます。小説の歴史に忠実であるためには、「正しく自由」でなければいけないと思っています。
羽生 「正しく自由」になるというのは矛盾しているようでもありますが、そこが重要なんですね。
磯崎 羽生さんも将棋に関して、「基礎を弁えた上で新しい手を指す」とおっしゃっていますよね。
羽生 将棋の場合、もちろんルール上の制約もありますが、上達するということは自分にある種の制約をかけていくことでもあるんです。つまり、制約をかけると不自由になりますが、それによってミスが少なくなったり、自分のスタイルが出来上がったりしていきます。ですから、確かに「正しく自由」に指すという感覚は私の中にもありますね。
磯崎 横尾さんの「将棋も文学も美術もその源流はひとつ」という言葉も、そういう部分をいいたかったのではないかと思います。羽生さんは言語脳科学者の酒井邦嘉さんとの対談の中で、「将棋を指していてなぜ面白いかというと、どうなるか分からないという状況が毎回続くからなのです」と語り、「自分の期待や予想をはるかに上回る場面が出てくる」と話されています。これは小説を書く面白さに似ていると思いましたが、この感覚は自分一人で研究していてもダメで、対局でないと出てこないものでしょうか。
羽生 対局の方が圧倒的にその面白さがありますね。相手がいますので、予想をしても必ず予想外のことが起きますから。また、対局者二人ともが予想もしなかった展開になることもある。それが将棋の不思議なところです。さらに言うと、二人の考えることが一致していない方が、むしろ思いがけない方向に進んで面白い内容になるように思いますね。
新しいアイデアとは
磯崎 同じ対談の中で、最近の将棋は過去のデータを分析して様々な局面をセオリーやパターンにまとめようとしていることに息苦しさを感じる、とおっしゃっていますが、小説も1970年代頃に記号論が流行って、ロラン・バルトらによって物語の構造分析が試みられたことがありました。ただ、それも最近は下火になって、小説のセオリーや構造を分析することは無理だと諦められてしまったような感じがあります。将棋は、構造分析のような研究が進んでいるんですか。
羽生 それはまさに「電車道」なんですよ。北陸まで新幹線が通ったけれど福井まではまだ、という具合に、ある一定の場所までは道ができています。それ以外の所を見つけて新しい道を作ろうと試みるわけですが、一方でここに道を通しても仕方がないと、見向きもされない場所もあります。それに関しても研究されてデータとして積み重ねられているのですが、あまりその方向に偏ってしまうのは健全ではないな、という思いはあります。将棋には無限ではないけれど膨大な可能性があるのですから、常に新しいところへ行ってみようとする方が面白いと思いますね。
磯崎 横尾さんのアトリエでお喋りしたときに、「最近は勝ち負けよりも、今までにない新しい試みができた時に充実感を感じる」と羽生さんがおっしゃったのがとても印象に残っています。でも、革新的だったり前衛的な方法というのは、最初はなかなか多くの人に理解されないんじゃないですか。
羽生 私は新しい試みといっても、その9割以上はそれまでに存在したアイデアの組み合わせだと思っています。多くの場合、組み合わせ方が新しいのであって、本当にゼロから生まれたアイデアはごく僅かなんです。また、将棋の世界では自分が思いついたアイデアは、その時点ですでに他の人にも浮かんでいると思ってほぼ間違いないですね。みな考えているテーマはだいたい共通していて、あとは誰が最初に指すかというタイミングの問題なんですよ。ですから、完全に自分だけのオリジナルな新しい道を見つけるのは、実はとても難しいことのような気がします。
磯崎 羽生さんたちの世界では、将棋という一つの大きな問題を棋士全員で解いているような感じがありますね。羽生さんが対局の中で新しい発見をされるように、僕も実際にパソコンに向かって文章を紡いでいくことで、初めて見えてくる何かがあると思っています。やはり現場での力は大きいですよね。
羽生 現場では作家の方には締切、われわれには持ち時間という制約があって、追い詰められることもあります。でも、そうやって切迫した時の方がかえって集中したり深く取り組めたりもするんですよね。小説を書いている時に感情の起伏はある、つまり喜怒哀楽を感じるものですか。
磯崎 書きながら「これはいい話だ」と自分で感心することもあります。今回の小説にはムササビが何度か登場するのですが、最後にムササビが森に帰っていく場面が書けた時には、いい描写だと思って、本当に一日気分がよかった(笑)。子供に向かって「何かほしいものはないか」と聞いたりするほどでした。
羽生 充実感は、書いていく中に存在するんですね。
磯崎 そんな時は、自分の苦労が報われたというよりも、何か別のものが巣立っていく感覚がありますね。
羽生 まさにムササビですね(笑)。
磯崎 この作品は「電車道」ではなく、「ムササビ小説」と呼んだ方がいいかもしれません。
(はぶ・よしはる 将棋棋士)
(いそざき・けんいちろう 作家)
(2015年3月14日、la kaguにて)
波 2015年5月号より
単行本刊行時掲載
※トークイベントの動画はこちら
時代を超えて、繰り返されてきたこと
ある高台の町を舞台に、日本に流れた百年の時間を描き、自然災害や戦争、さらには資本主義経済と抗いがたいものに翻弄されながら絶えまなく続いてきた人間の営みを活写した長篇小説『電車道』。磯崎さんの代表作になるであろう呼び声高い本書が、どのようにして生まれたのか? じっくりお話を伺いました。
――『電車道』は、磯崎さんの初めての連載小説にして、これまで書かれた作品の中でも最長のものになりました。本作を書こうと思われたきっかけなどはあったのでしょうか?
さかのぼると2011年になりますが、この年の10月に北杜夫さんが亡くなられたんです。ちょうどその頃、僕は、「どくとるマンボウ」シリーズの著者としてではなく、『楡家の人びと』を始めとする北さんの小説にもう一度光を当てることができたら、と思って、文芸誌で北さんとの対談を企画していたんですね。それが地震や仕事の都合もあって結局実現できないままになってしまった。これは小説家になって以来、最大の後悔となりました。
北さんが亡くなられた後、『楡家の人びと』を改めて読み返したら、やっぱりすべての小説家がこれを目指すべきだと思うくらいすばらしい小説で、そのときに自分も早くこういう長編を書かなければいけないと思いました。『終の住処』や『赤の他人の瓜二つ』も自分のすべてを出し切って書いたものの、まだ作者のコントロールが効いている小説でした。そこで、もっと小説の奥へ奥へ入りこむような、小説の底にずっと潜水したまま書き続ける力をつけないと長篇は書けないだろう、と思って、『往古来今』の連作短篇に挑みました。
英文学者でボルヘスの翻訳をされた篠田一士さんが、「『楡家の人びと』の文学的勝利を、一口で要約すれば、叙事のおどろくべき徹底である」と言っているように、どこまで作者を消して、小説に内在する力に寄り添い、具体性だけで書き進めていくことができるか。『往古来今』の最後に収録された「恩寵」で、ようやくそれができたんです。
――『電車道』は鉄道開発を背景にして、舞台となる高台の町に流れた百年の時間そのものが主人公のような小説です。こうした構想は、最初からあったのでしょうか?
それがないんですよ。電車が出てくることも、百年の時間というのもまったく考えていませんでした。最初の一行を書いて、そこから動き出していく書き方は、デビュー以来変わっていません。最初のきっかけは、世田谷の自宅の近くに喜多見不動というお寺があって、毎年元旦に初詣にいくのですが、そこの境内に洞窟があるんです。ちょうど人が入れるくらいの大きさで、なかに祠があって。あるとき、この洞窟には昔、人が住んでいたんじゃないか、と思ったことから、この小説の冒頭部分が生まれました。
それから、およそ百年前という設定が見えてきて、どんどん書き進めていくうちに、不思議なことに、この時代にもしかしたらこういう史実があるんじゃないか、と思って調べてみると、それが本当にあるんです。気味悪いくらいに。例えば、戦時中に盆踊りやヨーヨーが流行したことや、路面電車を先導する告知人制度、戦争が激化するなかで犬の回収令があったことなんかもそうでした。金属類回収令はわりと知られていると思うんですが、生き物にもそういうことがありそうだと思って調べると、やっぱりある。
女優がロケ地の奄美大島で自衛隊機の墜落事故を目撃する場面もそうです。これは昭和37年の夏になにか女優がショックを受けるような出来事がないだろうか、と思って探すとちゃんとある。不思議なくらい小説に導かれている感覚があって、それはこの小説を書くうえで大きな支えになりました。
まず史実ありきではなく、いま書き進んでいる方向が間違っていないことを史実が受けとめてくれている。しかも史実というのは一般的には小説の外部を支えるもので、脚注のような役割になりやすいのだけど、『電車道』に書かれた出来事は、実際にあったことでも、本当にこんなことがあったのか、と思わずツッコミを入れたくなるぐらいに、ある意味嘘っぽい、つまり「小説の言葉」になっているんです。
――では、『電車道』というタイトルも最初から決まっていたわけではないんですね。
書き進めていくなかで見つかった感じですね。相撲好きの方はご存知かもしれませんが、「電車道」というのは「立ち合いから、一直線に相手を押しや寄りで土俵の外に出すこと。その様が電車のレールのようにまっすぐであるところから、このように呼ばれるようになった」という意味の相撲用語なんです。この言葉のグイグイ押し切っていく感じが、この小説の時間の流れであり、のちに電鉄会社の社長となる男の生き方であり、高台の町の私立学校の校長の一直線な生き方を捉えているように思いました。それに、このふたりの男の人生は決して交わることなく平行に走り続けていて、まるで電車のレールのようでもある。
最初は洞窟に住み始めた男の話なのか、と思っていたら、書き進めていくうちに、もしかしたらこの小説は電車の歴史になるのかな、と気づいて。すると、またいろんな事実が出てくるんです。2015年の今現在の感覚では、僕たちが電車を使っていると思っていて、電車が遅れたとか文句を言ったりしているんだけど、舞台となる高台の町だって、元を辿れば電車にお客さんを乗せるためにつくられた住宅街なわけだから。実際には、僕たちが電車を使わされていて、そもそも成り立ちの順番が逆なんですよね。
――あたり一面、桑畑だった土地に、線路が通って駅舎が建ち、気づけば家だらけになっていたり、町の風景や人々の暮らしぶりの変化の軌跡が細やかに描かれていく一方で、変わらずにあるものも際立って感じます。
これも進めていくなかで気づいたのだけど、この小説に書かれているのは、「反復」なんです。一番わかりやすいのが、政治家を目指して落選した男が伊豆の温泉場でイギリス人女性と恋をする。その後、隠し子の女優は映画監督と、さらにその息子が電車のなかで恋に落ちます。その他にも、労働や経済の問題もそうですよね。「時代が変わった」とはよく言うけれど、実は同じことがずっと繰り返されている。明治時代の丁稚について調べてみたら、現代のサラリーマンと大差ないんですよ。
「それにしても百年前の勤め人の苦悩と、昭和から平成に元号が変わろうという時代の新人社員の苦悩がさして変わっていないのだとすれば、それはもう絶望を通り越して滑稽というしかない、反復は、個人にとってみれば単なる悲劇かもしれないが、歴史にとってみれば一種の緩衝剤のような機能を果たすことになる」と作中に書いたように、そうした反復を僕はむしろポジティブに考えているんです。
これは「過去」を描くことにもつながる話だけど、人間は自分たちの眼の前にあるものが一番たいへんだし大事だと錯覚しがちなんだけど、本当にそうなのか。それを相対化して考えたい。ずっと反復され続けてきたものは確かにあって、今も昔も実は変わっていない。いいものも悪いものも結局続くんです。そこに継続性が担保されていることがわかると、今を生きることがすこし楽になるんじゃないかって。
――路面電車の先走りも、銀行の窓口業務も、戦場の兵士も、様々なかたちの労働が作中に出てきますが、同時に、そうした労働を可能にさせている人間の従順さへの複雑な思いも全体を通じて響いているように感じました。
極端な例としては、戦闘機の操縦士が上からの命令だからといって、どうして従順に敵に体当たりしていくのか。実際には逃げたり別の行動だってとることができるはずなのに、仕事だと言われたら従ってしまう。その判断停止への怒りは、洞窟の男にもあるし、社長にも女優にもある。いったい何故そうなるのか、と問われれば、それは経済がそうさせているんだけれど、銀行員になった女優の息子によぎる「朝から晩まで奴隷のように働けば少なくとも生活の心配だけはしなくて済む身分になったことが、そんなに嬉しいのか?」という疑問はやっぱりありますよね。
――経済に翻弄される人間の姿と対比的に、自然のゆたかさが魅力的に描かれています。なかでも、電鉄会社社長の老夫婦がムササビを放野するところは忘れがたい場面でした。
のちに社長となる男がイギリス人女性と一緒に大島桜を見にいって、ムササビに遭遇するところは、以前実際に、僕もムササビが突然飛び立つところを見たこともあって、いい場面だなと思って書いたんです。ただ、再び大島桜を見にいったところでもう一度ムササビを出すことには躊躇して、さすがに出し過ぎかな、とずっと迷っていました。しかし実際に書いてみたら、老夫婦とムササビの別離の場面をよかったと言ってくれる人が多くて、小説に導かれるように、あのひときわ光る一文を書けたことに、自分の小説家としての成長を感じました。この一文を書くために出てきてくれたんじゃないかって思ったら、ムササビに感謝したいくらい(笑)。
――戦争中に犬を連れて逃げ出す少女も印象的でした。
あの少女は当初、戦争中のエピソードだけのはずでした。でも、すごくよかったから、またどこかで出したいな、という思いはあった。それが電鉄会社の社長の葬式に、隠し子が現れるという展開が生まれたところで、そうだ、この女優をあのときの少女にしよう、と決めたんです。
その回が「新潮」に載ったときに、連載をずっと読んでくれている友人からメールが届いて、「だから、戦争中の食糧難のときに社長から高台の町の学校に米俵が届いたんですね」と言われて、あっ、そうだったのか! と自分でも驚いたんです。米俵のことを書いた時点では、社長は高台の町の宅地開発に関わっていたからだと思っていて、隠し子があの学校に通っているなんて、まったく考えていなかったので。その指摘を受けたときに、小説が作者に教えてくれたように感じて、自分は小説の中にちゃんと潜り続けることができたんだ、と確認した瞬間でもありました。
――最後に、この作品を書き上げた今のお気持ちを聞かせていただけますか。
ボルヘスは生涯、短篇しか書かなかったわけですが、もし長篇を書いていたら、こういう作品になったんじゃないかなって、書き上げたときに思ったんです。不遜に聞こえてしまうかもしれないのですが、書いた自分を誇らしく思うのではなくて、書いた自分がその小説を見上げてしまう感覚。たとえば走り高跳びで、自分はかつてあんなに高く跳ぶことができたけれど、今の自分はもう二度とあの高さは跳べない、ということがあるじゃないですか。その感覚に近いかな。ただ、一度でもそれを跳ぶことができたというのは、小説家としてもう充分すぎるくらい幸せなことだと思うんです。
(いそざき・けんいちろう 作家)
波 2015年3月号より
単行本刊行時掲載
磯崎憲一郎×羽生善治トークイベント動画
著者プロフィール
磯崎憲一郎
イソザキ・ケンイチロウ
1965(昭和40)年、千葉県生れ。早稲田大学商学部卒業。2007(平成19)年『肝心の子供』で文藝賞、2009年『終の住処』で芥川賞、2011年『赤の他人の瓜二つ』で東急文化村ドゥマゴ文学賞、2013年『往古来今』で泉鏡花賞をそれぞれ受賞。他の著作に『眼と太陽』『世紀の発見』『電車道』『鳥獣戯画』『アトリエ会議』(横尾忠則、保坂和志との共著)等がある。