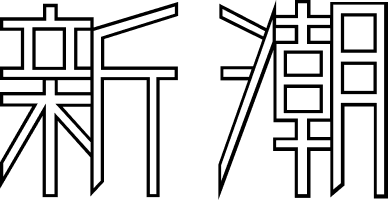ジーン・ワルツ
1,650円(税込)
発売日:2008/03/21
- 書籍
どこまでが医療で、どこまでが人間に許される行為なのか。強烈なキャラクターが魅せる最先端医療ミステリー!
美貌の産婦人科医・曾根崎理恵――人呼んで冷徹な魔女(クール・ウイッチ)。人工授精のエキスパートである彼女のもとにそれぞれの事情を抱える五人の女が集まった。神の領域を脅かす生殖医療と、人の手が及ばぬ遺伝子の悪戯がせめぎあう。『チーム・バチスタの栄光』を越えるドラマティックな衝撃が
あなたを襲う!
目次
序章 遺伝子のワルツ
一章 減数分裂
一月 帝華大学
二章 受胎告知
二月 マリアクリニック
三章 エンブリオ
三月 帝華大学
四章 心音覚知
四月 マリアクリニック
五章 托卵の技術
五月 帝華大学
六章 双角の魔女
五月 マリアクリニック
七章 借り腹の論理
六月 帝華大学
八章 妊娠と現実と蹉跌
六月 マリアクリニック
九章 魔女VS.アルマジロ
七月 帝華大学
十章 啓示
七月 マリアクリニック
十一章 出産の奇跡
九月 帝華大学
十二章 非母観音
九月 マリアクリニック
十三章 メディア・スター
十月 帝華大学
最終章 セント・マリアクリニック
十月 マリアクリニック
書誌情報
| 読み仮名 | ジーンワルツ |
|---|---|
| 雑誌から生まれた本 | 小説新潮から生まれた本 |
| 発行形態 | 書籍 |
| 判型 | 四六判 |
| 頁数 | 272ページ |
| ISBN | 978-4-10-306571-5 |
| C-CODE | 0093 |
| ジャンル | ミステリー・サスペンス・ハードボイルド |
| 定価 | 1,650円 |
書評
波 2008年4月号より 現役医師の「最後の切り札」
この春、ある産婦人科が閉鎖された。福島県立南会津病院産婦人科。神奈川県とほぼ同じ面積の豪雪地帯でただ一つの産婦人科だった。勤務医は三十代の医師一人。赴任して以来、緊急連絡に備えるため風呂に浸かったことはない。眠れないし、酒はもちろん飲めない。休みは一ヶ月に半日。肉親の葬式も欠席……そんな彼の孤軍奮闘はあっけなく終わる。県が人材不足を理由に、産婦人科医の撤退を決めたのだ。
この先、妊婦たちは山道を五時間以上かけ、産科に通うことになる。そんなに時間がかかってしまっては、陣痛が起きてから病院に向かう途中で子供が生まれるかもしれないし、道中でトラブルが起きたら、お腹の子は助からないだろう。
福島でドミノ倒しのように産科が崩壊したのは因縁めいている。いま、全国各地で産科崩壊の危機に直面している。トリガーを引いたのは福島県で起きた妊婦の死亡事故だった。妊婦の死亡は分娩を請け負った福島県立大野病院の産婦人科勤務医の過失であるとして、死亡事故から二年後の二〇〇六年二月、福島県警は業務上過失致死の容疑で勤務医を逮捕。冒頭の医師同様、一人で同病院産婦人科を守ってきた医師は、警察官に両腕を抱えられ、頭から上着をかけられ、腰ロープに手錠と連続児童殺人犯と見まごう仰々しさで送致され、その“市中引き回し”の様子は東北のローカルニュースで一斉に放映された。
平和ボケの日本人は、お産の現場にコウノトリや天使が舞ってると思っているのかもしれないが、現実は母親と胎児と医師が生死を賭す修羅場である。詳しいデータは本著で紹介されているので割愛するが、ときに天井まで血しぶきがあがるほど大出血することもある。それでも都市部で死亡例を聞かないのは、輸血がすぐ届く立地条件、小児科医や麻酔科医による人海戦術のおかげであって、陸の孤島に従事する一人の医師にはなす術もない。
ところが、有識者に人権派弁護士、偏向ジャーナリスト、記者クラブ……といった官僚の寄生虫連中はこぞって医師を罵倒した。一〇〇%安全なお産ができない産科医は殺人者だと。安全なお産ができるための設備や人材が不足しているのは官僚と地方自治体の怠慢であって、医師はその尻拭い役である。安直なスケープゴートに過ぎないが、疲弊している地方の産科医を萎縮させ、撤退させるには十分だった。
逮捕直後に開かれた日本産科婦人科学会の臨時集会で、過疎地の医師たちは窮状を訴えた。だが、同学会トップに君臨する東京大学医学部産婦人科講座は、潤沢な人材を拠出する英断には至らなかった。来賓出席した官僚も右に同じである。それどころか、崩壊の一途をたどる地方の産科を横目に、長期的な安全性を検証する名目で、東大系列の医師たちが不妊治療で生まれた子供たちを研究対象とする動きまである。
『ジーン・ワルツ』の魅力は、映画化された『チーム・バチスタの栄光』同様、先の見えないドキドキさせるストーリー展開に、お産の現実と無名の医師たちの声なき声が投影されている点にある。物語の舞台は潰れる寸前の診療所。一年前には病院長を慕う妊婦たちで賑わっていたが、過疎地の産婦人科医が業務上過失致死容疑で逮捕された事件のあおりを受けて、閉鎖を余儀なくされる。主人公は名門大学病院に勤務する女医。教授に睨まれながらも、閉院間近の診療所の最後のお産を請け負うことになる――。海堂氏が、現役医師としてのささやかな抵抗ともいうべきアイロニーを、物語にふんだんに盛り込んでいるのが、おわかり戴けるだろう。
話を現実に戻すと、大野病院の死亡事故は、公判で新たな解剖所見が出てから流れが変わった。捜査当局の解剖所見に“見落とし”があることがわかったのだ。海堂氏がすべての作品で一貫して訴えている、異状死をめぐる司法当局のいい加減な対応は、この裁判でも争点になりつつある。病理解剖で鍛えられたであろう洞察眼と先見性には感服させられる。
作者は本作品でも、時流に先駆けた「最後の切り札」を主人公に用意している。麻雀でいうなら字一色、大四喜、四暗刻、天和((C)海堂尊『螺鈿迷宮』)。神か悪魔の悪戯のような起死回生のあがりは、ぜひ貴方の目で見届けていただきたい。
この先、妊婦たちは山道を五時間以上かけ、産科に通うことになる。そんなに時間がかかってしまっては、陣痛が起きてから病院に向かう途中で子供が生まれるかもしれないし、道中でトラブルが起きたら、お腹の子は助からないだろう。
福島でドミノ倒しのように産科が崩壊したのは因縁めいている。いま、全国各地で産科崩壊の危機に直面している。トリガーを引いたのは福島県で起きた妊婦の死亡事故だった。妊婦の死亡は分娩を請け負った福島県立大野病院の産婦人科勤務医の過失であるとして、死亡事故から二年後の二〇〇六年二月、福島県警は業務上過失致死の容疑で勤務医を逮捕。冒頭の医師同様、一人で同病院産婦人科を守ってきた医師は、警察官に両腕を抱えられ、頭から上着をかけられ、腰ロープに手錠と連続児童殺人犯と見まごう仰々しさで送致され、その“市中引き回し”の様子は東北のローカルニュースで一斉に放映された。
平和ボケの日本人は、お産の現場にコウノトリや天使が舞ってると思っているのかもしれないが、現実は母親と胎児と医師が生死を賭す修羅場である。詳しいデータは本著で紹介されているので割愛するが、ときに天井まで血しぶきがあがるほど大出血することもある。それでも都市部で死亡例を聞かないのは、輸血がすぐ届く立地条件、小児科医や麻酔科医による人海戦術のおかげであって、陸の孤島に従事する一人の医師にはなす術もない。
ところが、有識者に人権派弁護士、偏向ジャーナリスト、記者クラブ……といった官僚の寄生虫連中はこぞって医師を罵倒した。一〇〇%安全なお産ができない産科医は殺人者だと。安全なお産ができるための設備や人材が不足しているのは官僚と地方自治体の怠慢であって、医師はその尻拭い役である。安直なスケープゴートに過ぎないが、疲弊している地方の産科医を萎縮させ、撤退させるには十分だった。
逮捕直後に開かれた日本産科婦人科学会の臨時集会で、過疎地の医師たちは窮状を訴えた。だが、同学会トップに君臨する東京大学医学部産婦人科講座は、潤沢な人材を拠出する英断には至らなかった。来賓出席した官僚も右に同じである。それどころか、崩壊の一途をたどる地方の産科を横目に、長期的な安全性を検証する名目で、東大系列の医師たちが不妊治療で生まれた子供たちを研究対象とする動きまである。
『ジーン・ワルツ』の魅力は、映画化された『チーム・バチスタの栄光』同様、先の見えないドキドキさせるストーリー展開に、お産の現実と無名の医師たちの声なき声が投影されている点にある。物語の舞台は潰れる寸前の診療所。一年前には病院長を慕う妊婦たちで賑わっていたが、過疎地の産婦人科医が業務上過失致死容疑で逮捕された事件のあおりを受けて、閉鎖を余儀なくされる。主人公は名門大学病院に勤務する女医。教授に睨まれながらも、閉院間近の診療所の最後のお産を請け負うことになる――。海堂氏が、現役医師としてのささやかな抵抗ともいうべきアイロニーを、物語にふんだんに盛り込んでいるのが、おわかり戴けるだろう。
話を現実に戻すと、大野病院の死亡事故は、公判で新たな解剖所見が出てから流れが変わった。捜査当局の解剖所見に“見落とし”があることがわかったのだ。海堂氏がすべての作品で一貫して訴えている、異状死をめぐる司法当局のいい加減な対応は、この裁判でも争点になりつつある。病理解剖で鍛えられたであろう洞察眼と先見性には感服させられる。
作者は本作品でも、時流に先駆けた「最後の切り札」を主人公に用意している。麻雀でいうなら字一色、大四喜、四暗刻、天和((C)海堂尊『螺鈿迷宮』)。神か悪魔の悪戯のような起死回生のあがりは、ぜひ貴方の目で見届けていただきたい。
(なす・ゆうこ 医療ジャーナリスト)
刊行記念対談
波 2008年4月号より
[海堂 尊『ジーン・ワルツ』刊行記念対談]
桜宮サーガの先へ
東 えりか×海堂 尊
ファンタスティック・シティ、東京
東 『ジーン・ワルツ』という新作のタイトルを拝見して、遺伝子についての話、生殖医療を扱っているんじゃないかと予想して読みました。なぜワルツなんだろうと思ったら、遺伝子のビートが三拍子であるということが冒頭に出てくる。それが小説の最後ではまったく違う意味で使われていて、まず驚かされました。
海堂 ありがとうございます。
東 海堂さんは一貫して、桜宮という架空の地方都市を舞台に書かれてきましたね。だから私は、桜宮という場所で土地と人のサーガを、桜宮サーガをこれからも作っていくんだ、とばかり思っていたんです。『ジーン・ワルツ』はこれまでと同じ物語世界ですが、舞台は初めて桜宮を出る。今度は東京です。
海堂 現実の日本は東京と地方との一対一の関係で出来ていると僕は思っています。東京と千葉、東京と茨城、東京と埼玉というように。千葉と埼玉という地域ごとの繋がりは、たとえ近接していても非常に薄いんです。だから日本全体で物語を構築するためには、東京と、地方都市を二つか三つ書けば済むのです。東京はスペシャル・シティ、ファンタスティック・シティですが、桜宮は地方都市の普遍的な象徴です。東京以外の地方都市を知る人が皆「あそこかもしれない」と思えるようにしたかった。いま「週刊朝日」で連載している『極北クレイマー』は極北市という北海道の景気の悪い街が舞台なのですが、これからも東京と、いくつか属性の違う地方都市を書いていくつもりです。
東 対談のために全て読み直したのですが、よくここまで世界をきちんと作られたなとあらためて感心しました。
海堂 張り巡らせた蜘蛛の糸に自分の首がからまって、最近ちょっと苦しくなってきましたけれど(笑)、こういう構造にした方がらくちんなんです。絶対書かなきゃいけないけれど、あんまり意味がないことってある。建物の配置とか、ああいうところで手抜きができるんですよね(笑)。それからどんな物語でも、主役と脇役が存在しますよね。主役にはいっぱい筆が割けますけれども、残念ながら脇役には割けない。この方式だと、脇役を主役に、あるいは別の話の主役を脇役にすることもできる。
東 私は去年まで北方謙三という作家の秘書を二十年以上務めていたのですが、やはり彼にもそういう小説があります。「ブラディ・ドール」というシリーズで、架空の街で起こる事件を十作にわたって書いている。主役がどんどん入れ替わり、物語世界が少しずつ網羅されていく。一つの小説で千五百枚なり二千枚書いても完結したらそれだけで終わりですけれども、五百枚の小説が十巻だと一つのサーガになっていく。だから海堂さんがなさっているやり方は、言い方は悪いけれどもとても効率の良い小説の書き方だと思います。ボスもこういうことをしていたなあ、と懐かしく読みました(笑)。最終的に誰が主役かなんて、あまり意味がなくなってきますよね。
海堂 実際、人間は誰しも自分が主役だと思いながらも、自分が世界の中心だとは思えない。たとえばテレビに出ているようなアイドルたちが世界の中心だと思う人もいるかもしれないけれども、でも彼らは自分が世界の中心にいると考えるかというと、それも違う。そういう光景が一番現実に近いんじゃないでしょうか。いわば神の視点で、世界の一部分を一作ずつ書いていくことで一つの虚構世界が完成すれば面白いんじゃないかと思います。そして最後には、閉じた輪の中で永遠にぐるぐる回っているような感じが理想ですね。
僕に限らず、たとえば北方先生もいろんなシリーズを書かれていますけれども、読めば「ああ、これは北方先生の作品だ」と思う。結局舞台を変え、時代を変えても、その人が語った物語だとわかってしまう。つまり、全ての人は結局、ひとりで一つの虚構世界を抱えているんじゃないか、というのが僕の仮説なんです。
鳥瞰的な小説
東 海堂さんの小説のキャラクターで私が大好きなのは、中年もしくは初老の女性なんです。今回も妙高という助産婦が脇を固めていますし、『バチスタ』シリーズでは藤原と猫田という素晴らしい看護師さんがいる。他の作家にはない、小説家としての特質の一つだと思います。
男性作家は、女性が非常に上手か非常に下手かに分かれると思っています。主役に女性を据えた場合にそれがはっきりしますが、海堂さんはものすごく上手。今回の理恵もそうですし、『螺鈿迷宮』のときの小百合とすみれの二人も大変素晴らしい。田口医師は等身大の描写なんだと思いますけれども、作られたキャラクターとしての女性像が抜群に上手いと思いますね。
海堂 おお、女性の描き方を褒められたのは、初めての気がします(笑)。中年のおっさんは上手いと言われますが(笑)。看護師さんには今でも大変お世話になっていますから、そのせいでしょうか。
東 階級社会にかっちり組み込まれていない人の存在が、組織の中では絶対重要なファクターになるんです。彼女たちは敵にすると一番怖いけれども、味方にすると一番強い存在。その状況を描くのがすごく上手。院長の三枝茉莉亜、それから山咲みどり――この小説の中ではそれほど出てきませんが、『医学のたまご』ではとってもいい感じに描かれている。
それから清川という、イケメン系のお医者さん。『ジェネラル・ルージュの凱旋』の速水のように、個人ファンがつきそうです。白鳥みたいなトリックスターを好きな人もいるけれども、やっぱり読者は恰好良いキャラが好きなんですよ。
海堂 そうですね。やっぱり人は単純で、男は恰好良く、女は可愛く綺麗なのがいい。それはもうしょうがない(笑)。
東 そして、主人公の理恵という女性医師。プロフェッショナルでありながら、子どもを産むことに真摯に向かっていく点に感銘を受けました。物語のクライマックスでは、こうなるだろうなとわかっていても涙が出ましたもの。
海堂 ありがとうございます。
東 もちろん小説だからフィクショナルなところもありますけれども、エンターテインメントにはカタルシスが必要です。きちんと小説を楽しませる、という姿勢には正直感動を覚えました。
そういう作りこんだ虚構の世界と、現実に起こっている出来事をどちらも使って、物語世界を膨らませているのがすごいですね。現役のお医者さんであり小説家であるという方は他にもいらっしゃいますけれども、海堂さんのように、その周りの制度や社会状況にまで目を配り問題意識を持って書かれている方は少ないのではないでしょうか。小説がとても鳥瞰的なんです。『チーム・バチスタの栄光』のころからそうでしたけど、上から全体を見回して、大事なところだけにところどころピンスポットをあてて書いてらっしゃるような印象を受けます。
海堂 なにしろバカは高いところに登りますから(笑)。
東 いえいえ、すべてのヒーローは高いところに登るものです。
海堂 いつのまにか梯子が外されていたりして……。
お仕着せの制度を打ち破る
東 私は農学部の畜産学科出身で、1980年代に5年ほど、動物に関する医療商社で仕事をしていたことがあるんです。当時は牛や豚の受精卵をいじることが盛んに行われていました。だから私もあのシーンと同じものを見たことがあるんです。相手は牛ですけれども。でもあまりにも普通に行われていて、非常に違和感がありました。これは神の領域ではないかと。ですから理恵がヒトの卵子に人工授精を施す最初のシーンは、強い既視感と感慨をもって読みました。
今ではヒトの人工授精も珍しくなく、私のまわりにも不妊治療をしている人も多い。けれども現実よりも、医学的なことを丁寧に描写している『ジーン・ワルツ』を読むと、本当にこんな時代が来たんだ、あのころの未来とは今なんだ、と強く実感しました。
海堂 この小説がもしノンフィクションだったら、不妊なんてかわいそう、治療は大変だ、と一瞬思うだけで、その後人々の関心は離れてしまうでしょう。小説なら、今は他人事でもいつか自分の身にも起こるかもしれない、と考えさせられるんじゃないか。そのためにある程度の長さと、完結した物語が必要だと思います。
東 これから子どもを産む人たちに、もしかしたら私たちが何かしてあげたほうがいいんじゃないかと思ってしまう小説でもありますね。女性の虐げられた部分を――と言ったら言い過ぎかもしれませんけれど、私たちもちゃんと考えようよ、と問題提起している。ご都合主義過ぎるという意見もあるかもしれませんが、この小説に関しては、海堂さんの考えが終始一貫して底に流れているのがよくわかる。女性はもちろんですけれども、男性にも読んでもらいたい。
昨年、柳沢厚労相が「女は産む機械」発言で叩かれましたけれども、女性の身体に生む機能が備わっていることは事実です。でも婚姻届が出てなければダメだとか、自分の子はお腹を痛めた子だけで人の子は自分の子として育てられないなどのタブーが未だにある。国は産めよ増やせよと言いますが、産科の撤退もありますし、実際にはやりにくい状況だと思うんです。でもこの小説はその現実にきちんと反旗を翻している。諸手を挙げて応援したい小説だと思いました。
海堂 とてもうれしいです。女性の気持ちはなかなか男にはわからないので、どういう風に受け取られるか心配していました。ほっとしています。
制度が実情についてこないというのは日本の宿痾みたいなもの。問題はその状態をこれからもよしとする態度だと思います。生殖医療の枠組みを作っている官僚や一部のお偉いさん方のうち、実際に不妊治療に関わっている人は少ないんじゃないでしょうか。今年の三月、日本学術会議が代理母出産について原則禁止とする報告書を出した。医学研究的な場合のみ例外として認めるとは言うものの、研究だけで十分な治療が出来るはずがない。実際に苦しんでいる、子どもを欲しがっている人はたくさんいるのに、その人たちの声を聞かずに制度を作ろうとしている。制度を作る人たちだって同じ市民のはずなのに、なぜわからないんだろう。そこが興味深い。
東 実際同じ立場に立たないと実感できないんじゃないでしょうか。
海堂 そう、人ごとだからですよ。結局ああいう決まりは学会の上層部と担当官僚が一緒になって拵えているわけですね。世論ではなく、現在の法律にそぐうものを出そうとしている。法律というのは洋服や鎧のようなもので、現実という身体ありきのもののはずなのに、官僚は身体の方が鎧や洋服に合わせるべきだ、と言う。今は身体の調子が悪くなって壊れている状態です。
東 その比喩を使えば、『ジーン・ワルツ』は身体のほうが筋トレして力をつけ、周りの洋服を打ち破ってしまう、そんなパワーを持った小説だと思います。
海堂 この物語にずっと通底しているのは、理恵のことを悪いと言える人が本当にいるのかという問いかけです。社会制度上は――今の日本学術会議の答申が受け入れられれば、理恵の行為は「罪」ですよね。では何を害したがゆえの罪なのか。罪とは必ず何かに対して不利益をもたらすものです。泥棒は相手の財産権を侵害するから罪を問われる。代理母出産を罪とする最大の根拠が非常に曖昧なまま、議論もほとんどなされていないんです。医療のトップと言われる人たちが数年にわたってあれこれ話した結果がこれです。
実際には外国で代理母出産を選ぶ人もいる。彼らの行為は罪にならないのに、同じことでも日本でやると罪になるんですね。殺人ならば外国でも日本でも罪になりますが、そういう普遍性もない。
東 たとえば小児臓器移植も、日本では無理でもアメリカならばできる。それも「○○ちゃん基金」などでお金を得た人たちだけが可能なわけですよね。それを美談としてもてはやしているマスコミも、きっと日本での手術は弾劾するでしょう。
海堂 そこで集めたお金はアメリカの医療を高めるために使われるわけだから、日本から資金が出て行くことになる。そうすると日本の医療はどんどんさびれていきます。日本でやったほうが経済を潤すし、医療の向上にも役立つ。なのになぜできないかというと、官僚が、もしくは国会議員がそう決めたからですよ。
東 この小説を読んで、セント・マリアクリニックのような病院を作ろうとする人、あるいは賛同する人が出てくるかもしれません。
海堂 ところがこういう先鋭的な病院ができると、国はこれを敵(エネミー)として排斥しようとするんです。実際に代理母出産を推進している諏訪クリニックの根津八紘医師の病院には国税局の査察と保険診療の審査が立て続けに入ったというし、病気腎移植を手がけていた万波誠医師は保険医の指定を取り消されそうになっている。
東 ではどうしたらいいと思いますか。
海堂 官僚に光を当てることですね。今の社会の混乱、特に医療行政の混乱の原因は官僚の決定にある。それによって引き起こされた惨状というのを個人名を出して、正確に告知していけばいいと思います。また官僚が行ったことを個人の責任に還元するべきです。それぞれの法案などの意思決定の際にどういう人たちが関わったか、名前をちゃんと記載してもらう。こうしたことを行うだけで、ずいぶん行政の現場も変わると思います。そうでもしないと、無責任な行政が行われる土壌になりかねない。例えば、新医師研修制度を起案し作成した人は、今の地方医療の破壊に一役買ったとも考えられるわけですから、それは誰かを明らかにしていく。社会に対する行政の影響力の大きさを考えたら、それくらいの制度は構築して当然だと思いますよ。だって官僚はパブリック・サーバントなんですから。
(あづま・えりか 書評家)
(かいどう・たける 作家)
(かいどう・たける 作家)
著者プロフィール
海堂尊
カイドウ・タケル
1961(昭和36)年、千葉県生れ。医学博士。外科医、病理医を経て、現在は重粒子医科学センター・Ai情報研究推進室室長。2005(平成17)年、『チーム・バチスタの栄光』で「このミステリーがすごい!」大賞を受賞し、翌年、作家デビュー。確かな医学知識に裏打ちされたダイナミックなエンターテインメント作品で、読書界に旋風を巻き起こす。2008年、『死因不明社会』で、科学ジャーナリスト賞受賞。他の著書に『ジェネラル・ルージュの凱旋』『イノセント・ゲリラの祝祭』『ケルベロスの肖像』『極北ラプソディ』『スリジエセンター1991』『輝天炎上』『ジーン・ワルツ』『マドンナ・ヴェルデ』『ガンコロリン』『ほんとうの診断学』などがある。
判型違い(文庫)
この本へのご意見・ご感想をお待ちしております。
感想を送る