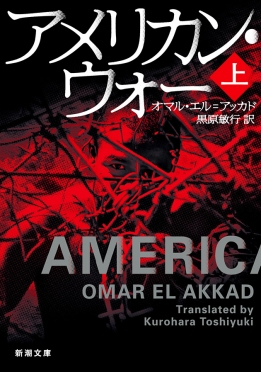アメリカン・ウォー〔上〕
693円(税込)
発売日:2017/08/29
- 文庫
内戦で分断されるアメリカと引き裂かれた家族の悲劇。全米騒然の巨弾エンタメ小説!
2075年、環境破壊のために沿岸地域が水没しつつあるアメリカ。化石燃料の使用を全面禁止する法案に反発した南部三州が独立を宣言、合衆国は内戦に陥った。家族の大黒柱をテロで失った南部の貧しい一家の娘サラットは、難民キャンプへ避難する。北部へのゲリラ戦を繰り返す武装組織に接近する兄。サラットに自爆テロ攻撃をそそのかす謎の男。苛酷な運命に導かれる彼女はどこへ向かうのか――。
書誌情報
| 読み仮名 | アメリカンウォー1 |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮文庫 |
| 装幀 | (C)Moises Saman/カバー写真、Magnum Photos/カバー写真、新潮社装幀室/デザイン |
| 発行形態 | 文庫 |
| 判型 | 新潮文庫 |
| 頁数 | 320ページ |
| ISBN | 978-4-10-220131-2 |
| C-CODE | 0197 |
| 整理番号 | エ-8-1 |
| ジャンル | 文芸作品 |
| 定価 | 693円 |
書評
再びの南北戦争を描く暗黒郷(ディストピア)小説
昨年、すなわち2016年は、エンタテインメント文学の読者にとって、忘れられない一年だったと思う。
まず6月にイギリスで行われた国民投票で、同国の
どちらも僅差の結果ではあったが、これまでフィクションで世界を揺がす様々な“
本を開いてまず愕然とするのは、掲げられた北米の地図からフロリダ半島が消えていることだろう。2075年という近未来、進んだ温暖化により海面が上昇し、アメリカ大陸でも各地で陸地が水没している。今年6月にアメリカの新大統領は、気候変動対策の重要な取り決めであるパリ協定からの離脱を宣言したが、そんなアメリカ合衆国の現在と地続きの未来の姿が、この小説の中にあるのだ。
それだけではない。今世紀に入ってからというもの、大統領選のたびに、州民の支持政党によりアメリカの地図は赤(共和党)と青(民主党)の二色に塗り分けられてきたが、その分断が招いた深刻な結果として、メキシコ湾沿いのテキサス、ミシシッピ、アラバマ、ジョージア、サウスカロライナの南部五州が自由南部国として分離独立を宣言。本国との間で戦争が始まっている。タイトルの“アメリカの戦争”は、第二次南北戦争と呼ばれるその内戦状態を指している。
ある老人が来し方をふり返るプロローグに続いて、物語は開戦から間もないルイジアナ州の町で幕をあける。歴史ある大都会のニューオリンズも大きな水溜りと化すほどの海水の氾濫は、主人公の少女サラットの町に迫り、両親、双生児の妹ダナ、兄サイモンとともに、彼女は水際で暮らしている。南部五州に挟まれた彼らの州にも戦争の不穏な空気がたちこめ、両親は子どもを連れて北部に逃れる機会を窺っていた。
しかしその矢先、一家は自爆テロで父親を失う。残された4人は、窮乏のために難民キャンプ行きを余儀なくされるが、元気なサラットはマーカスという少年と出会い、親友となる。一方、そこで出会った北部出身の元医師ゲインズを通じ、自分や南部の人々が置かれている状況について目を開かれていくが、やがて悲劇的な事件がキャンプを襲い、彼女の人生を暗転させてしまう。
読者の前に繰り広げられていくのは、60年後に待ち受けているかもしれないディストピアの風景だ。暗澹たる未来予想図は、古くはキングやマキャモンがホラー小説の題材とし、最近ではコーマック・マッカーシーが『ザ・ロード』の中で描いている。しかし、読者が本作に慄然とするのは、その世界の前提に既視感をおぼえるからだろう。
資本主義の歪みが生む貧困や、化石燃料(石油・石炭・天然ガス)をめぐる争い、さらには横行するテロリズムといった危機的状況の数々は、現実の世界においても絵空事ではない。むろん、戦争の危機もである。主人公とその一家を取り巻くアメリカの混沌は、紛争の解決手段として海外への派兵と武力行使を繰り返してきた国が、今度は内戦という陥穽に落ちて、もがき苦しむ姿そのものといっていい。
オマル・エル=アッカドは、カイロで生まれ、カタールで育ち、カナダやアメリカでジャーナリストとして活躍している。外側からこの国を眺めてきた作者らしく、“世界の警察”としてアメリカが行ってきた過去を冷徹に見つめ、憎しみが新たな憎しみを生む、終わることのない復讐の連鎖をペシミスティックな物語に紡いでみせる。
サラットの数奇な運命をたどるナラティブのさりげないマジックも、本作をエンタテインメント文学として際立たせているものの一つだろう。「戦争は銃で戦うが、平和は“物語”で戦うものだ」という一節からは、作者が本作に取り組んだ動機と強い意志がいやというほど伝わってくる。
(みつはし・あきら ミステリー評論家)
波 2017年9月号より
インタビュー/対談/エッセイ
憎しみの普遍性を描く
構成:編集部
――この作品は2074年にアメリカで第2次南北戦争が勃発してしまうという、非常に興味深い設定の作品ですが、書き始めたきっかけは何だったのですか?
OEA 書きはじめたのは2014年の夏で、第1稿はほぼ1年後にできました。ですからトランプが大統領になる前のことです。具体的なきっかけがあるとすれば、その数年前の出来事でしょうか。NATO主導のアフガニスタン攻撃がたけなわの頃、国家安全保障の専門家がインタビューを受けているのを聞いたのです。米軍への現地住民の反発が高まっているという話で、「なぜ我々はそんなに憎まれるのでしょうか?」という質問に対して、その専門家はこう答えました。米軍は時に村を急襲して、住民に銃を突きつけ、民家を徹底的に捜索しなければならないが、アフガニスタンの文化ではこうしたことは侮辱的だと受け止められるのだと。そのとき僕はこう思ったのを覚えています。「そういうことを侮辱的だと受け止めない国なんてあるのか?」と。そこから徐々に考えの鎖がつながって、もし西側の先進国が高見の見物をきめこんでいるような戦争が、その先進国の国内で起きたらどうだろうと思ったのです。僕はその戦争を傍観者の目ではなく、戦争がはげしく戦われている場所にいる人の目、その戦争から逃れることも目をそむけることもできない人の目から見てみたいと思いました。その意味で、この作品は個別的な憎しみを描いたものではなく、憎しみの普遍性を描きたかったのです。
――あなたは小説家として華々しくデビューする前は、アフガニスタン紛争、米軍のグアンタナモ基地、「アラブの春」にわくエジプト、ミズーリ州ファーガソンでの白人警官による黒人少年射殺事件などを取材してきたと聞いています。そういったことはこの作品にどのような影響を与えましたか?
OEA 小説家はみなそうですが、僕も「パクリ屋」です。ジャーナリストとして活動した間に見聞きしたことから色々なネタを盗んでいます。作品に登場する「キャンプ・ペイシェンス」のテントの配置は、グアンタナモ湾の「キャンプ・ジャスティス」をモデルにしています。名前も数百人が殺されたといわれているレバノンの難民キャンプ「サブラー」を直訳したもの。一見何の問題もなくうまくいっているように見える社会でも、不可視の犠牲の上に成り立っていたりするのだという考えが、取材を通して僕のなかで固まりました。
――何年もの間ジャーナリストとして活動してきて、今度はなぜ小説を書くことにしたのですか?
OEA ずっと以前からフィクションの世界は僕にとって「ホーム」でした。小学校の1年か2年のとき、自分にはお話を書く才能があるようだと気づきました。正確にいうと、他になんの才能もないことに気づいたのですが。父は大変な読書家で、エジプト文学の生き字引でした。僕が育ったエジプトでは本も音楽も映画も、好きなものを楽しめるわけではありません。政府の検閲があるからです。いまでも家のどこかにあるはずですが、僕が買ったニルヴァーナのCD「ネヴァーマインド」は、ジャケットの裸の赤ん坊がマジックで真っ黒に塗りつぶされています。学校の図書館には、イスラエルのことが書かれた本が一冊もなかったと思います。そういう環境で暮らしていると、すべての物語が読んで楽しいとか、カタルシスが得られるということの他に、一種の暗号だと感じられてくるのです。ある社会を知ろうとするなら、その社会がどんな風に物語を語るか、誰の物語を選んで語るか、誰の物語については沈黙するのかと見ていけば、少しずつ見えてくることがあります。大学卒業後にトロントにある新聞社に就職し、昼間は記者として働き、午前0時から5時まで小説を書くという生活を10年近く続けて、これまでに長い作品を4つ書きました。最初の3つは凡作でしたが『アメリカン・ウォー』はいまの時代に必要な作品だと思って出版社に持ち込んだのです。
――この小説で起きている出来事をリアルなことだと考えていますか?
OEA 文字どおりの意味でなら答えはノーです。この小説で起きることは事実上どれも故意にグロテスクにゆがめたレンズを通して再創造されているからです。しかしアナロジカルな意味では、この小説で起きることは全部すでに現実に起きたことなのです。この小説にアラブとイスラエルの紛争、イラク戦争、アフガニスタン紛争、あるいは北アイルランド紛争が透けて見えるとすれば、それは僕がそれらの出来事から色々な要素を盗み、違う衣装を着せて使ったからです。すべての戦争は同じだという決まり文句があります。僕はすべての戦争が同じだとは思いませんが、苦しみの言葉は世界共通だと思っています。
――2074年以降の世界をどういう風に創造したのですか?
OEA これまでにジャーナリストとしてアメリカの色々な場所へ行きましたから、それが作品に表れていると思います。強く記憶に残っているのは、ルイジアナ州南部の陸地喪失について書いた記事です。水上運搬に使われるミシシッピ川の南端にあたる土地が、1時間あたりアメフトのグラウンド1つ分、海に溶けていく。気候変動と産業開発の結果です。南フロリダについても同じような記事を書きました。小さな自治体の市長たちは有権者に、気候変動のせいで今後数十年のうちに自分たちが故郷と呼ぶ場所は人が住むのに適さなくなるかもしれないことを説明しようとしていました。僕はそうした地域の人たちが内陸に移動していくさまを想像したものです。軍関係のことも色々な取材の仕事から知識を得ました。前線基地の施設の配置とか、民兵の戦い方や武装ゲリラとの戦い方とか。変わりダネの取材も随分しました。思いがけないところに脇道がたくさんあるのを何日もかけて実地に歩いてみたり、フロリダ沿岸でミノカサゴの毒にやられる人が多いというレポートがあるとそれを確かめに行ったり。クモの毒に鎮痛効果があることや、南北戦争時代の南部でサー・ウォルター・スコットが文学に大きな影響を与えたことを知ったりもしました。南部での取材を終える頃には、ごった煮のカリキュラムを組んだ大学で1年学んだような気分になっていましたね。
――登場人物の一人が「戦争は銃で戦うが、平和は“物語”で戦うものだ」と語るのが印象的でした。
OEA 2年ほど前、フロリダ州からジョージア州ケニソーへ取材に行きました。すべての世帯が銃を少なくとも一挺備えていなければ
――登場人物の一人が、「この国には戦争が終ったあとでその戦争が正しかったかどうかをみんなが考える習慣がある」といいます。この小説はアメリカが中東でした戦争を厳しく弾劾する小説としての側面があると思いますが、それはあなたが意図したことですか?
OEA それを書いたとき、僕が考えていたのは、戦争が始まるときには決まって大声援があるのに、終ったときにはどこかに消えてしまっていることが多いということです。僕は絶対平和主義者ではありません。暴力は――とくに国家による暴力は――本質的に不正義であり、より大きな不正義を阻止するときにだけならば許されるという考えに賛成です。けれどもこういう考え方をすると、倫理的な葛藤を背負いこむことになります。むしろ絶対的な悪に対して暴力を使うことは絶対的に善であると考えるほうがすっきりするし気が楽です。自分は怪物と戦っているのだと信じこむことができれば、自分も怪物的な行為をしていいと思うことができます。戦争が始まるときに国民が大声援を送るのは、何もアメリカだけの現象ではないと思いますが、今世紀に入ってからのアメリカの中東における軍事行動にその種の現象の派手なものがいくつかあったのは確かです。2003年にアメリカがイラクに侵攻したときのことはよく覚えています。ブッシュ大統領が“任務完了”の横断幕を背に勝利宣言をしたときのメディアの興奮も。でも6年前に最後のアメリカ兵がイラクから公式に引き揚げた日のことはあまりよく覚えていません。勝利感にわいたという記憶は失われてしまっているのです。
――あなたにとって大事な意味を持っている本を教えてください。
OEA 僕にとって大事な本はまず、フォークナーが書いたものすべて。とくに『響きと怒り』と『死の床に横たわりて』ですね。トニ・モリスンの『ビラヴド』と『ソロモンの歌』も。それから、エジプトのノーベル賞作家ナギーブ・マフフーズの「カイロ三部作」。ジェイムズ・エイジーの『家族のなかの死』。マイケル・オンダーチェの『バディ・ボールデンを覚えているか』。マイケル・ハーの『ディスパッチズ――ヴェトナム特電』。僕はこの本を読んでジャーナリストになりたいと思いました。挙げればきりがありません。いま新しい小説を書いています。寓話を改変したような話です。どんな話にしたいのかはわかっているつもりですが、どんな話になるかはまだわかりません。
作家自作を語る
著者プロフィール
オマル・エル=アッカド
Akkad,Omar El
1982年カイロ生れ。ドーハで育ったのち、1998年に家族でカナダに移住。カナダの大手新聞社《グローブ・アンド・メール》にて調査報道に携わる。アフガニスタン戦争、グアンタナモ米軍基地、エジプトの〈アラブの春〉、米ミズーリ州ファーガソンで起きた白人警察官による黒人少年射殺事件などの取材を手がけたのち、『アメリカン・ウォー』でデビューを果たした。2017年8月現在はポートランド在住。
黒原敏行
クロハラ・トシユキ
1957年生れ。英米文学翻訳家。訳書にコーマック・マッカーシー『すべての美しい馬』『ザ・ロード』『ブラッド・メリディアン』、ハクスリー『すばらしい新世界』、マイケル・シェイボン『ユダヤ警官同盟』、パワーズ『エコー・メイカー』など多数。