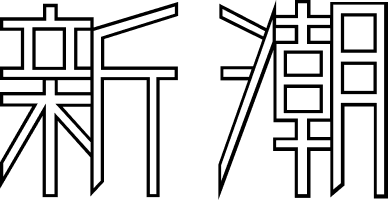君と漕ぐ―ながとろ高校カヌー部―
693円(税込)
発売日:2019/01/29
- 文庫
- 電子書籍あり
君とならきっと、もっと速くなれる!
両親の離婚で引っ越してきた高校一年生の舞奈は、地元の川でカヌーを操る美少女、恵梨香に出会う。たちまち興味を持った舞奈は、彼女を誘い、ながとろ高校カヌー部に入部。先輩の希衣と千帆は、ペアを組んで大会でも活躍する選手だったが、二人のカヌーに取り組む気持ちはすれ違い始めていた。恵梨香の桁違いの実力を知り、希衣はある決意を固めるが。水しぶき眩しい青春部活小説。
第二章 それでも君と夢が見たい
第三章 彼女は孤高の女王
第四章 過去は鮮やかに光っている
第五章 その夢はノンフィクション
第六章 この一瞬を君と
書誌情報
| 読み仮名 | キミトコグナガトロコウコウカヌーブ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮文庫nex |
| 装幀 | おとないちあき/カバー装画、川谷康久(川谷デザイン)/カバーデザイン、川谷デザイン/フォーマットデザイン |
| 雑誌から生まれた本 | yom yomから生まれた本 |
| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |
| 判型 | 新潮文庫 |
| 頁数 | 336ページ |
| ISBN | 978-4-10-180147-6 |
| C-CODE | 0193 |
| 整理番号 | た-126-1 |
| ジャンル | キャラクター文芸、コミックス |
| 定価 | 693円 |
| 電子書籍 価格 | 649円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2019/02/08 |
インタビュー/対談/エッセイ

水しぶき感じる“カヌー小説”の誕生!
吹奏楽部を舞台にした累計144万部突破の大人気青春シリーズ『響け!ユーフォニアム』(以下『ユーフォ』)の著者、武田綾乃さんの次に取り組むテーマは、なんと「カヌー部」。意気込みを著者に聞きました。
“カヌー”を題材に選んだ理由とは
――武田さんの代表作『響け!ユーフォニアム』には、ご自身の吹奏楽部経験が活かされています。今回新作でカヌーという珍しい題材を選ばれたのはなぜですか?
武田 私の地元の京都にはカヌー部が盛んな高校があって、弟も高校でカヌーをやっていたので馴染みがあったんです。「そういえば、カヌーをテーマにした小説ってあまり聞かないし、いずれ書いてみたいなあ」とずっとアイデアを温めてきました。
――武田さんにはカヌー経験がまったくなかったそうですが、取材はどのように行われたのですか?
武田 いろんな形でカヌーの勉強をしました。まずはカヌーの資料を探しましたが、文献がとても少なくて。それでウェブの記事を読んだり、YouTubeを見たりもしました。でもやはり、カヌー部の指導をされている先生やOGの方々のお話が本当に役に立ちましたね。埼玉県大会やインターハイなど、大会も何度か見に行きましたし、オリンピックのボランティア講習会も受けたんですよ。
――取材して大変だったこと、驚いたことは?
武田 当たり前のことですが、カヌー競技は川や湖で行われているので、気候に左右されます。精進湖で取材したときは、前日は寒くて震えるほどだったのに、翌日は真夏のような炎天になって、その変わりやすい天気に驚きました。過酷な状況下で競技を行う高校生のみなさんを尊敬してしまいました。
実際に見たカヌーのレースは、本当にスリリングで面白いです。私が見たのはスプリントですが、羽根田卓也選手がリオ五輪でメダルを取ったカヌースラロームのほか、カヌーポロやドラゴンカヌーなど、いろいろな種類の競技があり、知れば知るほど奥が深いと感じました。
――レースの場面は臨場感たっぷりでした。経験がないのに書くのは苦労されたのではないでしょうか。
武田 実はそこはあまり苦労しませんでした。物語展開を考えたりするほうがずっとつらいですね。情景を描くときは、VRを見ているときのように、物語のなかに自分を没入させて、そこで感じたものをただ文字で起こすだけなんです。ちょっとおこがましいのですが、仏像の彫り師が、設計図もなくただひたすら手を動かしてイメージを形にしていくような感覚です。
「響け!ユーフォニアム」シリーズとは違う作品を
――大人気の「響け!ユーフォニアム」シリーズと同じ“部活小説”である『君と漕ぐ』を書くにあたり、意識したことはありますか?
武田 はい。次のシリーズ作品では「ユーフォ」とはまったく違うものを、と思っていました。キーワードは、「少人数」「関東」「運動部」の三つです。
「ユーフォ」は吹奏楽部の物語なので、部員が百名を超えます。だから『君と漕ぐ』では、四人だけのカヌー部を舞台にして、少人数の関係性を書きたいと思いました。
それと「関東」。「ユーフォ」は京都が舞台でほとんどの登場人物が関西弁で会話しているので、標準語のセリフを書きたくて、埼玉の長瀞の設定にしました。
そして、「運動部」も書いてみたかったんです。「ユーフォ」で描いてきた音楽は、「うまい」「へた」の区別はついても、そこから先の評価基準は複雑です。それに比べてカヌースプリントは、タイムで明確に勝ち負けが決まるので、速い子が圧倒的に「強い」。実力の違いがわかりやすくて、もやもやが入り込む余地のない、そのシンプルさに惹かれました。
――なるほど。埼玉は武田さんにとって馴染みのない土地だと思うのですが、埼玉県民おなじみのローカルネタが盛り込まれていて、社内の埼玉出身者がざわついていました(笑)。
武田 知り合いに寄居の人がいたので、「地元の人しかしらないディープな埼玉ネタを教えて」とお願いしたんです。そしたら「“十万石まんじゅう”のCMの“うまい、うますぎる”は鉄板だから」と言われて(笑)。
現地にも何度か足を運びました。長瀞は自然たっぷりで見所も満載の素敵なところでしたし、秩父鉄道の波久礼駅や野上駅の古くて味のある駅舎は忘れられません。
小学生のときからカヌーでペアを組んできた希衣と千帆。そんな二人だけのカヌー部に、一年生の恵梨香と舞奈が入部することで、『君と漕ぐ』の物語は始まります。新人離れした実力を持つ恵梨香の存在が、先輩たちの関係に波紋をもたらし……。
――カヌー部女子のなかで、武田さんが特に思い入れのあるキャラクターはいますか?
武田 思い入れというのとは違うのですが、二年生の希衣はプロットの段階では「熱血の先輩」という記号的なキャラクターだったのですが、書いていくうちにどんどん多彩な感情が出てきて、最初の想定以上に複雑で深い人物になりました。
――ご自分にも近いところがあると思いますか?
武田 いや、普段からキャラと自分は切り離しているのですが、強いていうなら顧問教師の檜原ちゃんが一番近いですね。歳も近くて、若くて未来のある高校生をのんびり見守るという感じが似ています(笑)。
誰か一人に感情移入して、というより、女子高生たちの「関係性」を描くのが楽しいですね。「ユーフォ」のときから、物語を展開させるときには基本、ペア関係を作るよう意識してきました。「このエピソードでは、あの子とこの子に焦点を当てよう」といった具合です。
――なるほど。『君と漕ぐ』では、タイトルにもそれが現れていますね。「君」に当たるキャラは物語が進むにつれ変わります。
武田 はじめは一年生の舞奈と恵梨香、二年生の千帆と希衣がペアになっているのですが、それが変化していきます。特に千帆と希衣のペアは、いままで書いたことがない関係性ですね。二人がそばを食べながら、互いのカヌーに対する思いの違いを認識して、ペアを続ける限界を悟る場面が、切なくて気に入っています。
――反対に、終盤における希衣と恵梨香が語らう場面には、まるで恋が始まるときのようなときめきがありました。
武田 憧れをともなった友情って、恋愛感情と似ていますよね。誰かと誰かが距離を縮める、あるいは誰かと誰かが自立のために距離を取る、という関係性の変遷をうまく出せたらいいなと思って書いていました。
旺盛な執筆活動の秘訣
――武田さんは昨年だけで『青い春を数えて』『その日、朱音は空を飛んだ』の二冊の単行本と、「ユーフォ」シリーズの文庫一冊を刊行され、並行して連載していた『君と漕ぐ』を今回完成させました。驚異的な多作の秘訣は何でしょうか。
武田 書きたいテーマは本当にたくさんあって、アイデアだけは次々湧いてくるんです。それを形にしようとして必死で書いているうちに、本がたくさん出ていた、という感じですね。YouTuberの話や、女子大生の話なども書きたいし、探偵ものや、めちゃくちゃ怖いホラー小説も書いてみたい、と思っています。
――早くも小説誌「yom yom」では「君と漕ぐ2」の連載がスタートしています。
武田 はい。カヌー部四人の成長も見てほしいですし、今後は、「少年ジャンプ」のように、魅力的なライバルをどんどん登場させたいですね(笑)。
カヌーという競技は、知れば知るほど面白いので、この小説をきっかけに興味を持つ人が増えてくれたら嬉しいです!
(たけだ・あやの 作家)
波 2019年2月号より
※このインタビューは「波」掲載分のロングバージョンです。
プロローグ&第一章 まるごと試し読み

プロローグ
オリンピックの観客席は、一介の高校生にはあまりに高価だった。親に
カヌースプリント。日本では
「舞奈ちゃん、ソワソワしすぎ」
隣に座る
「でも、緊張するじゃないですか。友達が出るんですもん」
舞奈は唇を
「選手たちは舞奈ちゃんほど緊張してないと思うよ」
「そうかもしれないですけど、私は緊張するんです。世界大会はこれまでもありましたけど、オリンピックはみんなこれが初めてなんですよ?」
「確かに、友達がこんな大舞台に出ると思うとドキドキしちゃうよね。シングルに、ペアに、フォアでしょう? こんなにいっぱいレースがあるとバテちゃわないか心配」
「そこらへんは大丈夫です。みんな強いですから」
胸を張って答える舞奈に、千帆が
「あー、間に合った。危ない危ない」
聞こえた声の方へ顔を向けると、頬に日の丸を描いた
「檜原先生、そろそろ試合始まりますよ」
「そう思って急いで戻ってきたの。ほら、二人もいる?」
檜原が差し出して来たのは、五輪の黄と緑の部分がレンズになっているサングラスだった。
「もらっておきます」と受け取る舞奈の隣で、千帆は既に着用していた。周囲からは浮かれているようにしか見えないだろうが、今日ぐらいはいいだろう。なんせ、友人たちの晴れ舞台なのだから。
「そろそろWK-1開始だよ」
舞奈のスマートフォンを
――
彼女は、舞奈の大切な友達だ。

第一章 そして春が始まる
祖父の家はいつだって、線香の
「せっかくだから外を見てまわるか?」
そう言って、父親はポロシャツの二の腕部分で額の汗を
「外って、どこのこと?」
舞奈の問いに、父親は空いている方の手で凹凸の残る道路を指さした。
「ほら、駅の方とか。自然が多くて気持ちいいぞ」
それが父なりの気遣いであることは明らかだった。だが、作業を続ける父を置いて自分一人で出掛けるのも気が引ける。
「うーん、でも、迷子になんないかな。ほら、私スマホ持ってないし」
「道さえ
「まあ、そりゃそうだけど」
板敷の空間へ足を降ろし、置かれていたスニーカーに足を通す。よく言えばレトロな、有り体に言えば古臭いデザインの赤い自転車は、明日からの通学用に祖父母が用意してくれたものだった。やや大きめのサドルに
「じゃあ、ちょっとだけ散歩行ってくる」
「暗くなる前には帰って来るんだぞ」
「はいはい」
表札に刻まれた『
何もない場所だ、と父は自身の故郷のことを表現した。道路は広く、外灯は少ない。都会のように高い建物が密集している空間はなく、視界に広がる風景は畑や山、さらには川ばかりだった。湾曲する道路に沿って、白いガードレールが緩やかにたわんでいる。聞こえてくる列車の音に顔を上げたら、
最寄り駅である
自転車の速度をぐんと上げる。頬を打つ風の感覚が心地よく、舞奈は丸まっていた背中を伸ばした。ガードレール越しに荒川を見下ろせば、黒々とした水面が日差しを細やかに跳ね返している。魚の
「あっ」
思わず声が漏れる。ペダルを踏む足を止め、舞奈はその光景を凝視した。流線形の小舟が、緩やかな川の流れを
「何やってるんですかー」
驚いたのか、少女は勢いよく顔を上げた。キョロキョロと周囲を見回し、それから不思議そうに自分の顔を指さしている。その唇がパクパクと開閉したのは分かったが、
「聞こえないですー」
少女が困ったように頬を
「すごい、ボートだ」
近くで見る小舟は、異様なほどに細長かった。純白の船体は先端が鋭く
「ボートじゃなくて、カヌーね」
「カヌー?」
「そう。全く別物だから」
フンと鼻を鳴らし、少女は水面から小舟を引き上げた。キャンプで使う簡易
「すみません、いきなり話し掛けちゃって」
「それはいいけど……どこの中学の子?」
予想外の質問に、舞奈は目を丸くした。手を勢いよく左右に振り、
「あの、中学生じゃないです。私、明日から高校生なんで」
「ウソ、同い年?」
心底驚いたという顔で、少女は自身の
「タメなんだったら敬語じゃなくていいよ。っていうか、どこの高校なの?」
「ながとろ高校」
「すごい、私も」
そう言って、少女は
「私ね、今日からこっちに引っ越してきたの」
「へえー。引っ越しってどこから?」
「
「どこそれ?」
「池袋の近く」
「あー、なるほど。随分都会から来たんだね」
少女の指先が、先ほどからファスナーの上で行ったり来たりを繰り返している。薄いTシャツに、黒のハーフパンツ。ごくありふれた軽装の上に、彼女は蛍光ブルーのライフジャケットを装着していた。
「ここらへんってなんにもないでしょう? 退屈じゃない?」
「まだ分かんない。今日が一日目だから」
「絶対すぐ飽きるよ、娯楽が少ないからさ。早く十六歳になりたい」
「なんで?」
「なんでって、十六になったらバイクの免許とれるじゃん。どこに行くにも自転車って大変だよ。高校も自転車だと結構遠いし」
「えっ、学校まで自転車で行くつもりなの? 電車があるのに」
舞奈の問いに、少女は顔を逸らした。その視線の先にあるのは一艇のカヌーだ。
ながとろ高校はその名前の通り、秩父郡
「電車、嫌いなの」
腕を伸ばしながら、少女は何でもないような口ぶりで答える。ハーフパンツの
「それに、意外にあっと言う間に着くよ。三、四十分くらい。タイミングによっては電車を待つよりよっぽど早いし。あと、単純に早いと気持ちいい」
「本当に?」
「私的には、ホント」
「じゃあ、私も学校まで自転車で通おうかな」
そしたら電車代も浮くし、と続けた舞奈に、少女はぽかんと口を開けた。じわじわと
「正気?」
「え、変なこと言ったかな」
「だって、見ず知らずの
彼女は未だケラケラと笑い続けている。その
「見ず知らずじゃないよ、友達でしょう?」
少女がピタリと笑うのを止める。その指先が、今度は自身の鼻先に突き付けられた。
「友達って、私のこと?」
「そうじゃないの? だって、同じ高校に行くんでしょ?」
「でも、名前も知らないのに」
「黒部舞奈だよ。ほら、これで問題ない」
「いや、そういう問題じゃなくてね、」
「名前は?」
「は? 何が?」
「だから、名前教えてよ」
自然と手が伸び、少女のTシャツの裾を
「……
「オッケー、恵梨香ね。ほら、これで問題なく友達だよ」
ひらりと手を振ると、恵梨香は
「黒部さんはいつもそうなの?」
「舞奈でいいよ。苗字で呼ばれるの、変な感じするから」
「あー……分かった。舞奈ね、舞奈」
自身の名が呼ばれたことに、舞奈は込み上げる笑みを我慢できなかった。何笑ってんの、と恵梨香が
「私、こっちに友達とかいないから。だから、今日こうやって恵梨香と会えて良かった。明日、同じクラスになるといいねぇ」
「ま、普通科は二クラスしかないから、可能性は五〇パーってとこかな」
そう言って、恵梨香は転がる小石を軽く蹴った。ビーチサンダルに当たった小石が、ぱしゃりと水面に波紋を作る。舞奈は
「さっきさ、恵梨香言ってたよね。これはボートじゃないって。そもそもカヌーとボートって何が違うの?」
「カヌーは前向きなスポーツです、ってよく言うね。見分け方としては、前に進むのがカヌー、後ろに進むのがボートって感じ。乗ったことある?」
「ボートだけ、昔」
「じゃ、あんま分かんないか。ボートだとオールを使って漕ぐでしょ? 両手でばしゃばしゃって。でも、カヌーは一本だけで操作するの。パドルって言うんだけどね」
これ、と恵梨香が棒状のパーツを差し出した。これがパドルか、と舞奈はしげしげと観察する。棒の両端にはゴムベラのような平べったいパーツが角度を変えてくっついていた。
「棒の部分がシャフト、水を掻く部分がブレード。カヌーにも色々あるんだけど、カヤックの場合はこのダブルブレードのパドルを使うの。両腕に持って、回転させるみたいにして漕ぐ。カナディアンの時はシングルブレードっていう水掻きが一つしかないやつを使うんだけどね」
「んー、よくわかんないけど、恵梨香はカヌー部に入ってたの? だから今日も練習?」
「私は、」
「そういうのは、入ったことない。これも趣味でやってるだけだし。まあ、ながとろ高校にはカヌー部あるらしいけど」
「じゃ、高校でもカヌー部に入らないの?」
「いや、そんなつもりじゃ……気が向けば入ろうかなって感じ」
誰かに言い訳するみたいに、恵梨香はぼそぼそと
「私もやってみたい」
「何を?」
「カヌーを」
勢いよく立ち上がると、恵梨香がぎょっとしたように一歩下がった。緑の中に埋もれたタンポポの黄色が、彼女の足元で揺らいでいる。
「恵梨香も私と一緒にカヌー部入ろ」
「なんでいきなり……大体、カヌーやったことないんでしょ? 部活入る必要なくない? 長瀞だったら普通にカヌー体験やってるし、それで満足すれば?」
「でも、せっかくだったらちゃんとやってみたいし。それに、こっちに来たら何か新しいこと始めたいなって思ってたんだよね」
「舞奈は部活とか入ってなかったの。ほら、向こうで」
「水泳部に入ってた。でも、ながとろ高校には水泳部はないみたいだからさ」
ね、と笑いかけると、恵梨香は深々とため息を
「私、部活とか向いてないんだよね、たぶん」
「中学の時は何部だったの?」
「帰宅部」
「じゃ、向いてるかなんて分かんないじゃん。大丈夫、私がいるから楽しいって」
「どっから出てくるの、その自信」
「んー、根拠はない」
「ダメじゃん」
ふはっ、と恵梨香が吹き出す。ぴょんとその場で飛び跳ね、舞奈は彼女の頭上から帽子を取り上げた。汗に
こちらを見下ろす双眸を、舞奈は真っすぐに見返す。
「じゃ、明日は何時集合? やっぱり余裕をもって時間決めておいた方がいいかな。初日だもんね」
「本当に自転車で行くつもり?」
「うん、もちろん」
恵梨香の帽子は、舞奈の頭にはやや小さかった。メッシュ素材の帽子の裏側には、彼女のものらしき甘ったるい匂いが
「それじゃ、明日波久礼駅に七時集合で」
「了解です」
「言っておくけど、遅刻したら一人で先に行くからね」
「肝に銘じておきます」
神妙な顔で
「ほら、帽子返して」
「あ、うん」
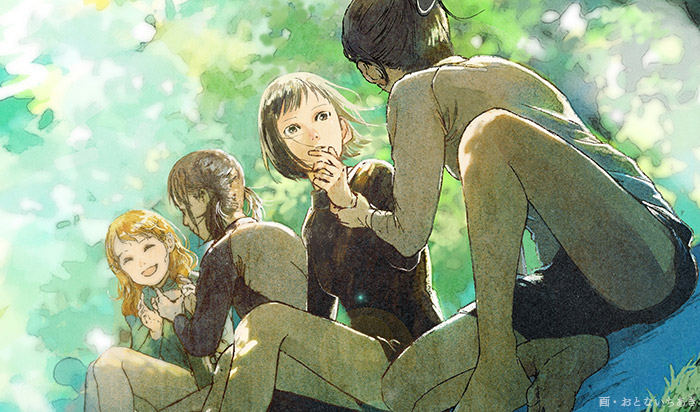
「今日ね、友達ができたの」
「ここらへんの子か?」
隣に座っていた父親が、ちらりとこちらに視線を寄越す。かつては和室だった空間も、祖父母の足腰の衰えと共に洋風のダイニングへと改築された。広々としたテーブルの中央には、祖母が庭で採取した野草がガラス瓶に挿して飾られている。今日は菜の花だ。
「カヌーやってるんだって。湧別恵梨香ちゃんっていうの」
「湧別さんとこの娘さんね。ほら、
すぐにピンと来たのか、祖母が
「あのね、自転車で一緒に学校行こうって約束したの」
「駅までか?」
「違うよ、学校まで」
「何言ってるの、電車があるのにわざわざ自転車で行く必要ないでしょ」
父は顔をしかめ、祖母は心配そうに頬に手を添えている。投げ出した足を交差させ、舞奈は祖母の顔を見た。
「あの自転車、通学用に用意してくれたんでしょう?」
「波久礼駅までの通学用に、ね」
「大した距離じゃないって、恵梨香ちゃん言ってたよ。走ると気持ちいいって」
「それはほら……あそこの子は、ちょっと変わってるから」
里芋の煮っ転がしは
「いいじゃん、変わってても。悪い子じゃないんだし」
「そうは言ってもねぇ」
「おばあちゃんは心配しすぎ。無理そうだったらすぐ電車通学に変えるから」
口を開こうとした祖母の動きを止めたのは、鳴り響く電話の音だった。箸を置き、舞奈はすぐさま席を立つ。
「私が出るよ」
普段通りを
ダイニングの扉を後ろ手で閉め、舞奈は
「もしもし? 舞奈?」
「うん、私。お母さん、どうしたの」
「どうしたのって、心配になったから。今日が引っ越しの日でしょう? うまくやれてる?」
「うん、平気」
「そっちは何にもなくて不便でしょ?
「ふふ、ありがとう。でも、本当に大丈夫だから」
両親の離婚が成立したのは、ほんの数日前だった。兄と姉はすぐさま母親と暮らすことを選択した。悩む素振りすら見せなかったのは、これまでの父の行動を顧みれば当たり前だった。平日も休日も仕事ばかり。共働きの母に家庭の負担を押し付けているくせに、父はいつだって被害者
「あ、お姉ちゃんが電話代わりたいって」
いくらかの世間話を交わした後、母親はあっさりと受話器を姉に譲り渡した。ゴソゴソと何かが動く音がしたかと思うと、冷ややかなアルトボイスが舞奈の耳に飛び込んだ。
「――あー、もしもし。アンタさ、スマホ持ちなさい」
開口一番これだ。姉という生き物は、妹に対して説明を怠りすぎる節がある。舞奈は受話器を逆の腕に持ち替えると、
「いきなりなに?」
「不便でしょ、スマホがなかったら」
「いらないって」
「なんで? 遠慮しなくていいって。アタシが買ってあげる」
「本当にいらないってば。嫌いなの、スマホ」
「そうは言うけどね、お母さんのこと考えても買った方がいいと思うよ。アンタと話したいときに毎回お父さんの実家に電話掛けなきゃいけないの、辛いでしょ」
正論だ、と思った。だから、舞奈は口を
「……アンタ、ホントなんでお父さんを選んだのよ」
ため息交じりの姉の台詞に、舞奈は自身の足元を見下ろす。洗濯を繰り返したせいで薄くなった靴下は、所々に毛玉が
「だって、
漏らした本音に、姉は呆れたように笑った。アンタらしいわね、と彼女は言った。そんなつもりはないけど、と舞奈は唇を尖らせる。
離婚を告げられた日、小さく丸まった父の背中はあまりにも
「スマホはしばらくいいよ。困ったらこっちから電話掛けるから」
「本当にいいのね?」
「うん。心配してくれてありがと」
「別に、アンタを心配したわけじゃないけどね。ま、
姉にとっての家と舞奈にとっての家は、すでに違う場所を指す。それでも、姉は帰って来いという言葉を選んだ。彼女にとって、舞奈の帰るべき場所は今でもなお東京にあるのだ。
ズクリと心臓が
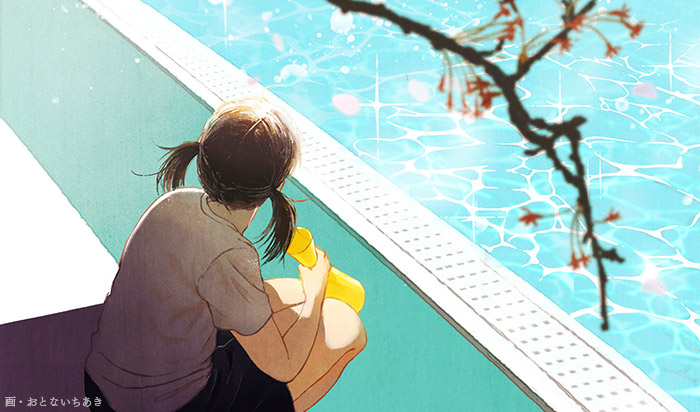
翌朝。自転車のサドルに跨り、舞奈は思い切りペダルを踏みこむ。濃紺のブレザーに、ブルーのラインが入ったワイシャツ。チェック模様のスカートが、立ち漕ぎする度に大きく揺れた。
「本当に来たんだ」
こちらの姿を見つけて早々、制服姿の恵梨香が
「約束は破らないよ、私は」
「みたいだね。じゃ、これから頑張りますか。ちゃんとついてきてよ」
「はーい」
恵梨香の跨る自転車のフレームは、色鮮やかな青色をしていた。彼女の長い脚に合わせたのか、その車輪は舞奈のものより二回りほど大きい。恵梨香の
「大丈夫?」
走行しながら、恵梨香がこちらに声をかける。平気、と応じながら舞奈は彼女の背を追いかけた。荒川沿いに続く長い斜面は、上がったり下がったりを繰り返している。橋を渡ると、吹き付ける風が
「桜、すごいね」
周囲に視線を巡らせながら、舞奈は大きく声を張る。細く伸びる枝の先には、ふっくらとした薄桃色の花が色付いている。立ち並ぶ木々はそれぞれに顔が違い、未だ開花していないものから既に葉をつけているものまで様々だ。
「ヤマザクラだからね。ここらへん、結構多いの」
「誰かが植えたの?」
「勝手に生えてるんじゃない? 野生の桜っぽいし」
「桜にも野生とかあるんだね」
「当たり前じゃん、何言ってんの」
下り道に入り、恵梨香がペダルから足を浮かせる。滑り降りる自転車は徐々に加速していき、向かい風が開いた目の中に飛び込んでくる。外の音が遠くなり、速くなる感覚だけが確かな実感を持って手の中に張り付いていた。ドクドクと高鳴る心臓が、不安がる
高校に辿り着いた頃には、舞奈の頭はひどい有様となっていた。慌ててトイレに駆け込み、鏡を見ながら
「同じクラスだったね」
隣に立つ恵梨香の顔を見上げると、彼女は満更でもない表情で頷いた。廊下に張り出された一年一組のクラス名簿には、確かに舞奈と恵梨香の名前があった。
「うちのガッコ、三年間クラス替えないんだっけ」
「そうそう。だから、舞奈とは三年間同じってことになるね」
「やった」
両手を挙げて喜びを表現する舞奈に、恵梨香は呆れたように肩を竦めた。開きっぱなしだった蛇口の栓を
「さ、早く教室に行こ」
「もう?」
「恵梨香は髪の毛直す必要ないじゃん」
どういう仕組みなのか、激しい風を真っ向から受け止めても恵梨香の髪に乱れはなかった。絹のようなサラサラの黒髪は、頭を軽く振るだけで形状記憶合金みたいにすぐさま元の形に戻る。幼いころから髪質に悩まされていた舞奈にとっては、
「まあ、そうなんだけどね」
歯切れの悪い恵梨香の言葉に、舞奈は手に込めた力を軽く緩めた。
――あそこの子は、ちょっと変わってるから。
昨晩の祖母の言葉が、不意に舞奈の耳元に
「教室に行くの、いや?」
舞奈が尋ねると、恵梨香は軽く目を見張った。薄い唇から細く息をこぼし、彼女は首を横に振る。
「ごめん、そういうわけじゃない。……行こっか」
「いいの?」
「トイレで入学式を始めるのは、
そう言って、恵梨香は
高校生活最初の一日目は、驚くほど穏やかに始まった。クラスメイトは地元の住人ばかりで、
購入した教科書を机の中に押し込み、舞奈はぐっと腕を伸ばす。制服のネクタイとリボンは男女共に自由に選択できるようになっていたが、クラスのほとんどの女子はリボンを着用していた。濃いブルーの生地に、斜めに引かれたホワイトのストライプ。胸元に付けた校章は、モノクロの鳥の形をしていた。
「部活体験だって」
ページの隅を指さし、舞奈は恵梨香の顔を見上げた。ホームルームはとっくに終わり、室内に残った生徒たちは先ほど配られたお手製の小冊子に目を通している。以前に舞奈が通っていた中学校に比べると、ながとろ高校は本当に規模の小さな学校だった。全校生徒は一六十人足らずしかおらず、その癖敷地はやたらと広い。文化系から体育会系まで多くの部活が取り揃えられていたが、その大半は人がいないせいで活動休止中だった。
「水泳部、一応あるじゃん」
カヌー部の隣の欄を、恵梨香がそっと指先でなぞる。
「でも、活動はしてないみたいだね。学校のHPにも載ってなかったし」
「舞奈が入ればまた活動できるかもよ」
「何言ってんの、カヌー部に入るって言ったでしょ」
ほら、と舞奈は恵梨香の眼前に小冊子を突きつける。
「プール、カヌー部が使ってるみたい。体験期間中はプールに来いって書いてある」
「舞奈、本当に行くの?」
「当たり前でしょ、行く気しかないよ」
「うわぁ、本気じゃん」
「最初から本気だってば」
フンと鼻を鳴らし、舞奈は席を立つ。
「わ、本当に人が来た」
プールはフェンス状の
「ちょっと
眼前に飛び出してきた二人組は、舞奈たちとは違う名札の色をしていた。白色のプラスチックプレートは、二年生の
「あ、そうか。えっと、その……ようこそカヌー部へ?」
「なんで疑問形?」
「いや、入ってくれるか分かんないから」
「こういう時は堂々としなさいよ。勢いで勧誘すればいいでしょ」
「勢いって言っても、私こういうの苦手なんだもん」
「頑張りなよ副部長」
「副部長とかあってないような役職じゃん」
ポンポンと飛び交う会話に、舞奈と恵梨香はその場で黙っていることしか出来ない。この二人がこれから自分たちの先輩になるのだろうか、と舞奈は冷静に両者を観察する。
副部長と先ほど呼ばれた生徒は、舞奈に似て小柄な体格をしていた。垂れ下がった眉と小動物のように大きな
その傍らに立つ女子生徒は、舞奈よりも一〇センチほど高い位置に頭がある。ぴっちりと斜めに分けられた黒髪は、
置いてけぼりにされた後輩たちにようやく気付いたのか、背の高い方の先輩がコホンと軽く
「あー、ごめんね。まずは自己紹介から。私は部長の
「部員、少ないんだよねぇ」
頬に手を添え、千帆がおっとりとため息を吐いている。他の学校のカヌー部がどの程度の規模で活動しているかは知らないが、やはり二人というのは相当に少数なのだろう。両腕を組んだまま、希衣が足を肩幅に開いた。
「で、二人の名前は?」
自己紹介を促され、舞奈は慌てて口を開く。
「一年一組の黒部舞奈です。カヌーに興味があって来ました!」
「湧別恵梨香です、舞奈とは同じクラスです」
「カヌーに興味あるなんて珍しいね。クラブとか入ったりしてた?」
希衣の問いに、二人は揃って首を横に振った。そっか、と千帆が頷く。その横顔は、どこかほっとしているようにも見えた。
「じゃ、まずはカヌー部そのものについての説明からかな。こっち来て」
希衣の誘導に従い、舞奈と恵梨香はプールサイドに足を進める。透き通ったターコイズブルーの水面の
「これが我が部の所有するカヌーです、シングル――だと分かんないか、えっと、一人乗り用のカヌーは置き場にあるものを含めるとこの学校に三艇あります。あ、ちなみにカヌーとボートの違いって分かる?」
「前向きに進むのがカヌー、後ろ向きに進むのがボートですよね」
恵梨香に言われた説明をそのまま繰り返す。よく知ってるね、と千帆は感心したように目を見張った。希衣はプールに指の第一関節だけを浸すと、ピンと強く水を弾いた。
「観光地とかで見るカヌーって、もっと太いというか、平べったい形をしてるんだよね。これは浮力と抵抗の問題なんだけど、要は重いものを水に浮かせようと思ったら抵抗が大きい方が安定するわけ。だけどね、私たちが使ってるカヌーは御覧の通り、びっくりするぐらい細いでしょう。これは、抵抗を極限まで削るためのデザインなの。競技用カヌーの特徴だね」
なるほど、と神妙な面持ちで相槌を打つ舞奈に、希衣は言葉を続けた。
「カヌーって一口に言っても、種目にはいくつかの種類があるの。私たちがやってるのはスプリント。フラットウォーターっていう呼び名の通り、障害物のない水を進むスポーツだね。ま、陸上の短距離走とかと同じ、直線距離の速さを競う競技ってこと」
「オリンピックで日本人選手がメダルを取ったことがありましたよね。こう、渓流下りみたいな。障害物を越えていくやつ」
「あぁ、あれはスラロームっていう競技だよ。二五〇メートルから四〇〇メートルのコースの中に、番号が振られたゲートがあるの。それを順番に進んでいくって競技。国内だとなかなか練習できる場所がないから、競技人口は少ないんだけどね。その他にも、カヌーに乗ったままバスケみたいなことをやるカヌーポロとか、激流を下るワイルドウォーターとか、マイナーだけどいっぱい競技があるんだよ」
「はー、知らなかったです」
「でしょう?
「ま、とりあえず二人とも乗ってみよっか。今日はこっちで練習用の服を用意したから、とりあえず向こうで着替えてきてね」
「え、最初から競技用カヌーに乗せるの?」
慌てた様子で口を挟んだのは、副部長の千帆だった。希衣が首を捻る。
「なんか問題ある?」
「初心者の子にいきなりはきつくない?」
「どうせ慣れなきゃいけないんだから、それだったら最初から乗った方がいいでしょ」
「それはそうかもしれないけど……」
口ごもる千帆を横目に、希衣は後輩二人に着替えを促す。舞奈と恵梨香は顔を見合わせると、駆けるようにして更衣室へと向かった。
濡れても平気なように、舞奈はスクール水着の上にTシャツとハーフパンツを着込む。着替え終わった二人を待っていたものは、千帆による初心者のためのレクチャーだった。
「すっごく不安定だからびっくりしないでね。カヌーに乗り込むときは、パドルのシャフト部分――そう、この棒の部分でカヌーと岸を押さえながら片足ずつ乗り込むの。大丈夫、最初は私が押さえておくから」
ライフジャケットを装着した舞奈は、千帆の指示に従い恐る恐るカヌーへ乗り込む。足を入れただけで船体が大きくぐらついたのが分かる。プールの反対側で、恵梨香が涼しい顔でカヌーを漕いでいた。希衣が驚いたように目を丸くする。
「あれ、湧別さんってやっぱり経験者?」
「一応。クラブとかには入ったことないんですけど」
「なんだ、じゃあ細かく説明する必要なかったね。知ってることばっかだったでしょ」
「いえ、あんまり。競技とかそういうのには詳しくなかったので」
パドルを操作しながらにも関わらず、恵梨香には随分と余裕があった。和やかに二人が会話しているのを聞き流しながら、舞奈はふるふると小刻みに震え続ける自身の
「こ、こわい! 揺れてる!」
「そうだね、揺れるね」
「落ちますってこれ、絶対落ちる」
手で支えてもらっているというのに、それでも舟はガクガクと揺れ続けている。必死に腰をくねらせる舞奈に、千帆があっけらかんと言い放つ。
「じゃ、離すね」
「えっ」
重心が安定せず、舞奈は両腕を左右に傾けることでなんとか体の軸を安定させようとする。が、そんな抵抗も
「大丈夫?」
プールサイドから、千帆が心配そうにこちらをのぞき込んでいる。ぷかりと身体を浮かせたまま、舞奈はこくこくと頷いた。
「あの、乗れるようになる気がしないんですけど」
「競技用はねぇ、本当に難しいから。自転車みたいなもんで、一度乗れるようになったら平気なんだけど」
「普通の人って、このカヌーを乗りこなせるようになるのにどのくらい掛かるんですか?」
「そうだねぇ……乗りこなせるって言葉の定義にもよるし、人によってバラバラだけど、大体三か月はかかるかなぁ」
「三か月!」
思わず悲鳴を上げると、恵梨香が慌てた様子で近付いてくる。その姿はあまりに自然体で、見ているだけだとカヌーに乗ることは簡単なのではないかと思えてしまう。パドルが水を押し上げる度に、水面がたぷんと大きく揺れた。
「舞奈、大丈夫?」
「大丈夫じゃないよ。なんか、バランスボールの上で立ち上がろうとした時みたいだった。ずっとグラグラしてるし」
「……舞奈って、普段からそんなアクロバティックなことしてんの?」
「恵梨香はしたことないの?」
「うん、まったく」
設置された手すりに掴まり、舞奈は
「舞奈ちゃん、反対側持ってくれる? 水抜きするから」
千帆の指示に従い、舞奈はカヌーの端を両手で掴む。乗り口を真下に向けてゆさゆさと上下に振ると、内部に
「舞奈ちゃんは筋がいい方だとは思うよ。最初からバランス取れてたし」
「でも、落ちちゃいましたけど」
「それは仕方ないよ。バランスを取り続けるのは難しいから」
千帆に手伝ってもらいながら、舞奈は再びカヌーに乗り込む。転覆し、陸に上がり、水抜きをして、再び乗り込む。一連のサイクルを、舞奈と千帆は延々と繰り返した。慣れてきたせいか、乗り込む技術ばかりがどんどんと磨かれていく。
「あら、見学の子がちゃんと来てくれたのね」
背後から投げかけられた声に、舞奈はカヌーを揺さぶる手を止めた。振り向くと、教師と思われる小柄な女性がこちらへ向かって手を振っていた。全身を覆う赤いジャージに、フリルのあしらわれた真っ白な日傘。そのミスマッチさに、舞奈は目を見張った。
「お疲れ様でーす」
首に掛けたタオルで額を
「あの人は、
「一応って失礼ね、ちゃんとした顧問よ」
わざとらしく頬を膨らませる檜原に、千帆が乾いた笑みを浮かべている。幼く見える面付きのせいか、檜原には教師としての威厳が感じられない。隣に立つ希衣の方が、よっぽど大人びて見える。
「檜原ちゃんはね、美術の先生なの。運動音痴なのにカヌー部の顧問を押し付けられた可哀想な新人教師なんだよね」
「新人じゃないですぅ、もう二年目だから」
「二年目だったらまだまだ新人だよ」
いたずらっぽく笑う千帆に、檜原は訂正することを
「そっちの子は初心者?」
檜原の短い指が、舞奈の方を指し示す。うん、と千帆が気安い口調で頷いた。
「こっちが黒部舞奈ちゃんで、あっちが湧別恵梨香ちゃん。舞奈ちゃんの方は完全な初心者で、今頑張ってるとこ」
「偉いわねぇ。私なんて、今でもカヌーについてチンプンカンプンだもの。よくこんな不安定なものに乗ろうと思うわよねぇ」
パタパタとおばさん染みた仕草で手を振る檜原に、舞奈はほんの少しの共感を抱いた。
「先生もカヌーに乗れないんですか?」
「そこの二人に
「やっぱり落ちちゃいますよね。私も全然ダメで」
「大丈夫よ。黒部さん、私の百倍運動神経良さそうだもの。それに、やり続ければ必ず乗れるようになるのがカヌーらしいわよ」
檜原ちゃんは我慢できなかったけどね、と希衣が

ぼちゃん、ばしゃん。聞きなれた水音が、舞奈の耳元で鳴いている。次の日も、そのまた次の日も、舞奈はプールでカヌーに乗る練習を繰り返していた。
「ちょっとだけど乗れる時間が伸びてきたね。大丈夫、この調子」
二つに結わえた髪を揺らしながら、千帆は穏やかに
「ごめんなさい。千帆先輩も練習したいのに」
「私のことは大丈夫。それに、カヌーを始める子が一人増えたってだけで
「でも、希衣先輩たちみたいに千帆先輩も荒川に練習に行きたいんじゃないですか?」
「朝練で乗ってるから大丈夫。舞奈ちゃんは何も気にしなくていいからね」
ながとろ高校から荒川は、目と鼻の先にある。恵梨香と希衣はカヌーを
「私も川で練習したいなぁ」
舞奈の呟きに、千帆はただ柔らかに笑う。
「もう少ししたらね。そしたら、恵梨香ちゃんと一緒に練習できるから」
「千帆先輩も希衣先輩と早く一緒に練習したいですか?」
「ふふ、まあね」
何度もプールに落ちる舞奈を見かねてか、今日の千帆は濡れてもいいようにラッシュガードを着用している。プールサイドに座る彼女は、膝小僧から下の部分を水の中に浸していた。舞奈はその傍らにちょこんと体育座りをすると、足の指を小さく丸めた。ライフジャケットを脱ぐ。ただそれだけで、身体は少し軽くなった。千帆が小さく笑う。
「恵梨香ちゃんって、背が高いよねぇ。一七〇超えてるでしょ」
「身体測定の時に、前より伸びたって言ってました」
「いいよね、背が高い人って。希衣だって一六〇あるんだよ? 私、一五五しかないのに」
「私なんて一四八センチですよ。一年で五ミリしか伸びなかったんです」
「お、じゃあ舞奈ちゃんと私は仲間だね。一六〇センチいかないフレンズ」
千帆の脚が、水を強く
「本当、羨ましい」
学校からの行きと帰りは、いつも恵梨香と一緒だった。七キロの道のりを、二人は自転車で越えていく。ごつごつとした輪郭を描く
「どうすんの」
先を進む恵梨香が、大きく声を張った。ペダルを
「何が?」
「月曜日が正式な入部日だって先生言ってたじゃん。カヌー部、本当に入るの?」
「うーん」
舞奈は言葉を濁した。カヌーをやりたいという気持ちは変わらない。だが、初心者の自分が本当に部活に入っても良いのだろうか。先輩である千帆は、毎日のように舞奈の練習に付き合ってくれている。今のままでは、彼女の足を引っ張り続けるだけではないのか。
狭い
「恵梨香は入るの?」
問いを口にした途端、恵梨香の動きが止まった。キュッと車輪が
「危ないよ、いきなりブレーキなんて」
思わず文句を言うと、恵梨香はこちらを振り返った。見下ろす視線の鋭さに、舞奈の背はぎくりと
「明日、土曜日じゃん。……暇?」
突然の誘いに、舞奈は困惑を隠せない。ハンドルを握りしめたまま、ぎこちなく頷く。
「ひ、暇だけど」
「それじゃ、波久礼駅に九時集合ね。濡れてもいい
一方的にそう告げて、恵梨香は再びサドルに
八時五十五分。デジタル時計の数字は、集合時刻の五分前を示している。寝ぼけ眼を
「早いね」
伸びる影を靴の先端で踏みつけていると、目前で一台の自転車が止まった。
「どこ行くの?」
「面白いところ。ほら、早く自転車に乗って」
促され、舞奈は素直に指示に従った。恵梨香の羽織るグレーのパーカーには、やや大きめのフードが首からぶら下がっていた。帽子があるならフードなんていらないじゃん、と舞奈は心の中で独り
「乗った? じゃ、出発ね」
舞奈がペダルに足を掛けたのを確認し、恵梨香は
「風が語りかけます」
「なにそれ?」
「知らない? 『うまい、うますぎる』ってやつ。十万石まんじゅうのCM」
「よくわかんないけど、絶対似てないでしょ」
「自分では似てると思うんだけどなぁ」
「似ていないよ。恵梨香、自分で思ってるより声高いもん」
「そう?」
「うん。綺麗な声してる」
「初めて言われた」
他愛のない会話が心地よい。頭を使わずに発する言葉たちは、なんの重みも含んでいない。甘さしか詰まってない綿菓子みたいな、くだらないやり取りが好きだった。楽しいという感情だけが、

「あ、着いた着いた」
恵梨香が導いた先にあったのは、一軒の喫茶店だった。周囲に何もないせいか、手作り感
恵梨香は店前に自転車を置くと、なんの
「
気安く話しかけているところを見るに、恵梨香はこの店の常連客なのだろうか。店内に踏み込むことになんとなく抵抗を覚え、舞奈はぼんやりと外装を見上げた。
「……喫茶せせらぎ」
書かれた店名を読み上げる。東京では嫌になるくらいにカフェを見かけたものだけれど、こちらに来てからはそうした
「ごめん、待たせたね。こっち」
店内から出てきた恵梨香が、慣れた足取りで建物の裏側へと回る。道路からは死角となるような位置に、トタン製の倉庫が設置されていた。恵梨香が鍵を扉に差し込むと、呆気なく倉庫は口を開く。
「ここ、芦田さんの私物置き場」
倉庫の中央に堂々とそびえ立っていたのは、銀色のポールで組まれたラックだった。そこに、数艇のカヌーが差し込むようにして置かれている。その中に見覚えのある舟を見つけ、舞奈は恵梨香のパーカーの
「これ、この前恵梨香が使ってたやつでしょう?」
「そう。いっつも借りてるの」
さらりと質問を肯定し、恵梨香は壁に立て掛けられたカヌーを指さした。
「今日の舞奈はこっちね。レジャー用のカヌー」
丸みを帯びたシルエットは、普段乗るカヌーに比べてずんぐりとした形をしている。それを担ぐようにして持ち上げた舞奈に、恵梨香が慌てたように倉庫の隅からハンガーを取り出してきた。
「これつけるの、忘れずにね」
初めて会った時の恵梨香と同じ、蛍光ブルーのライフジャケット。その
水面にカヌーを浮かべ、いつもの如くパドルを駆使しながら中へと乗り込む。競技用のカヌーと違い、足裏に覚える安定感は確かなものだった。水に浮かぶ感覚が面白く、舞奈はがむしゃらにパドルを動かす。ぱしゃぱしゃと水滴を跳ね上げながら、カヌーは緩やかに前進した。
「それだったら乗れるでしょ」
いつものように競技用カヌーに乗った恵梨香が、にこりと笑みを深くする。真っすぐに伸びる彼女の上半身は、体幹がしっかりとしているのか、流れに
「乗れるけど、なかなか思った方向には進まないね」
「あー。レジャー用のカヌーにはラダーっていう
「でも、全然落ちない」
「そう。初心者でも簡単に乗れるの。観光地とかで使われてるカヌーは大抵こういう形なんだよ」
「へー」
「今日は風が強いから、余計に前進しにくいのかもね」
舞奈が進むペースに合わせ、恵梨香はのんびりと水を
「恵梨香も最初はこういうカヌーに乗ってたの?」
「うん、初めて乗ったのはそのカヌーだった。もう何年前の話かなぁ」
「それからずっとカヌーに乗ってるんだもんね、そりゃあスイスイ動けるよね」
「まあ、こういうのは慣れだからね」
パドルを動かしていると、肩の辺りの筋肉が痛くなってきた。内部に備え付けられたストレッチャーに、舞奈は足裏を押し付ける。
疲れ切った腕を下ろし、舞奈は水の流れに身を任せる。どこからか散った白い花弁が、ふわふわと水上を漂っていた。
「舞奈さ、あんまグダグダ考えすぎない方がいいよ。
隣から聞こえる声に、舞奈は
「馬鹿じゃないもん」
反論すると、恵梨香はクツリと喉を鳴らした。
「そうだね、舞奈は馬鹿じゃない」
「結局どっちなの」
「どっちも」
そう言って、恵梨香はパドルを握り直した。平べったいブレードが、暗い水中に深く切り込む。グンと勢いよく前進した恵梨香のカヌーを、舞奈は慌てて追いかける。
「見て」
必死にパドルを動かす舞奈を
「すごい!」
思わず感嘆の声を漏らす舞奈に、恵梨香がゆるりと頬を緩めた。
「ここ、私のお気に入りなの。川からじゃないと来られないんだよ」
「こんなの、初めて見た」
ひらひらと舞い落ちる花びらが、舞奈の鼻先に着地する。指先でそれを拾い上げると、恵梨香は可笑しそうに歯を見せて笑った。
「カヌーって、楽しいでしょう?」
「うん、楽しい」
さざめく水面も、散り行く桜も、眼前の世界を構成する何もかもが美しかった。弾けるような恵梨香の声が、舞奈の心臓を
「……私、部活入るよ」
まるで歌うように、舞奈は決断を口にした。恵梨香は大きく目を見開き、それからそっとその
プロモーションムービー
イベント/書店情報
- 終了しました
著者プロフィール
武田綾乃
タケダ・アヤノ
1992(平成4)年、京都府生れ。2013年、日本ラブストーリー大賞最終候補作に選ばれた『今日、きみと息をする。』で作家デビュー。同年刊行した『響け! ユーフォニアム』はテレビアニメ化され人気を博し、続編多数。2021(令和3)年、『愛されなくても別に』で吉川英治文学新人賞を受賞。その他の作品に「君と漕ぐ」シリーズ、『石黒くんに春は来ない』『青い春を数えて』『その日、朱音は空を飛んだ』『どうぞ愛をお叫びください』『世界が青くなったら』『嘘つきなふたり』などがある。