【創作】村上春樹「武蔵境のありくい」
羽田圭介「その針がさすのは」
新潮 2025年5月号
(毎月7日発行)
| 発売日 | 2025/04/07 |
|---|---|
| JANコード | 4910049010556 |
| 定価 | 1,200円(税込) |
【創作】
◆武蔵境のありくい――〈夏帆〉その2(130枚)/村上春樹
絵本作家の夏帆はありくいの夫婦に導かれ、「文明の果つるところ」武蔵境へと引っ越した。彼女が負わされた危険な責務。そして、物語はどこからやってくるのか? 前作から1年、待望の最新小説。
◆その針がさすのは(230枚)/羽田圭介
夫婦で不妊治療に通い、馴染みの店に寄る。学生時代を過ごした中野で暮らし始めて、8年が経った。ノスタルジーと再開発が折り重なる街で、僕はどんな大人でいるのだろう。第2回東京中野文学賞大賞作!
【掌篇】
◆温泉相撲/筒井康隆
温泉地で関取たちが湯を楽しみながら対戦する興行が始まった。だが、取り組みは思わぬ展開に……。
【連載小説】
◆マイネームイズフューチャー(第2回)/千葉雅也
綾瀬を訝しみながらも、行動を共にするようになった悠介。新宿区を中心に、点と点が繋がっていく。
【対談】
◆助手席で天皇小説を体験する(往路)――『天使も踏むを畏れるところ』をめぐって/松家仁之×高橋源一郎
同じ道なのに運転の仕方がまったく違う――作家の視座で歴史・建築・天皇制の本質を問う、刺激的対話。
【紀行文】
◆よそものの帰郷――八丈島訪島記/滝口悠生
生まれ故郷の島で自作について語り、「内地」との距離を思う。生と死を超え、家族と過ごした数日間。
【連載評論】
◆数学する惑星(第2回)星界への報告/森田真生
「天からの文」を観測し、いち早く宇宙から地球を見ていたガリレオ・ガリレイヘの時空を超えた応答。
【ノンフィクション】
◆触れるポートフォリオ(第8回)強さと柔さ/島本理生
【リレーコラム 街の気分と思考】
◆四ヶ月の憤懣/斎藤真理子
◆うるせえ、お前が進化しろ/ヒコロヒー
【新潮】
◆読書たち――Reads 開発記/阿久津 隆
◆この幸いについて/小田原のどか
◆末期の眼、始まりの声/須藤輝彦
【書評委員による 私の書棚の現在地】
◆竹中優子『ダンス』/高瀬隼子
◆『母の友』最終号/小池水音
【本】
◆小山田浩子『ものごころ』/赤松りかこ
◆朝比奈 秋『受け手のいない祈り』/田中慎弥
◆柴崎友香『遠くまで歩く』/東辻賢治郎
◆古川真人『港たち』/玉置周啓
【特別書評】
◆無とはなにか――高村 薫『墳墓記』を読む/町田 康
【連載コラム】
◆料理の人類学のかたわらで(第10回)/藤田 周
わずかに天使の食べものではない鮨
【連載評論】
◆雅とまねび――日本クラシック音楽史(第5回)/片山杜秀
◆独りの椅子――石垣りんのために(第13回)/梯 久美子
◆小林秀雄(第116回)/大澤信亮
【連載小説】
◆Ifの総て(第11回)/島田雅彦
◆荒れ野にて(第85回)/重松 清
第58回新潮新人賞 応募規定
執筆者紹介
この号の誌面
編集長から
村上春樹「武蔵境のありくい」
羽田圭介「その針がさすのは」
◎物語はどこからやってくるのか? 村上春樹「武蔵境のありくい」は、そうした大きな問いに貫かれている。絵本作家の夏帆はブラジルから逃げてきたありくいの夫婦にうながされ、武蔵境へ引っ越した。そして彼女は、叔父が「文明の果つるところ」と蔑むその土地で、裏ルートを使いシロアリを入手するという責務を負わされる。密輸に関わる商店街の「とぎや」店主の正体は? そもそもこれは夢でないなら何なのか? 謎が謎を呼び、現実と虚構、都市と郊外の境目に位置する街の様子が変化する。夏帆の姿を通し、小説家自身の創作の根源にも迫るような一篇だ◎羽田圭介「その針がさすのは」の舞台は、同じく中央線沿いの中野。不妊治療に取り組むもなかなか思う結果が出ない「僕」の生活を、奔放な同級生・長尾が掻き乱す。これまでになく落ち着いた筆致で中年の危機に差し掛かった男たちの身体と内面を描く、著者の新境地ではないか。場所の力を感じさせる二中篇をご堪能いただきたい。
編集長・杉山達哉
バックナンバー
雑誌バックナンバーの販売は「発売号」と「その前の号」のみとなります。ご了承ください。
雑誌から生まれた本
新潮とは?
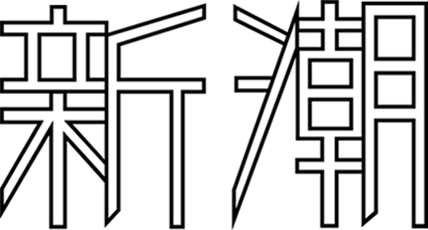
文学の最前線はここにある!
人間の想像力を革新し続ける月刊誌。
■「新潮」とはどのような雑誌?
「新潮」は日露戦争の年(1904年)に創刊された、百歳を超える文芸誌です。現役の商業文芸誌としては世界一古いという説があります(ただし第二次大戦中は紙不足のため数号、関東大震災のときは1号だけ休刊)。その歴史の一端は小誌サイト内にある〈表紙と目次で見る「新潮」110年〉でご覧ください。
■革新し続ける文学の遺伝子
もちろん古いことと古臭いことはまったく別です。百余年にわたり、たえず革新を続けてきたことこそが「新潮」の伝統であり、その遺伝子は現編集部にも確実に引き継がれています。ケータイ小説やブログ、あるいは電子配信、電子読書端末まで、いまだかつてない〈環境変動〉がわたしたちの生に及びつつある今、時代精神を繊細に敏感に感じ取った小説家、批評家たちが毎月、原稿用紙にして計1000枚以上(単行本にして数冊分)の最新作を「新潮」を舞台に発信し続けています。
■日本語で表現されたあらゆる言葉=思考のために
デビュー間もない20代の新人からノーベル賞受賞作家までの最新作がひとつの誌面にひしめきあうのが「新潮」の誌面です。また、文芸の同時代の友人である音楽、映画、ダンス、建築、写真、絵画などの領域からも、トップクラスの書き手、アーティストが刺激的な原稿を毎号寄せています。文芸を中心にしっかりと据えながら、日本語で表現されたあらゆる言葉=思考の力を誌面に結集させたい――それが「新潮」という雑誌の願いです。






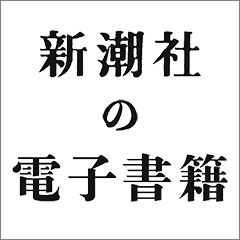
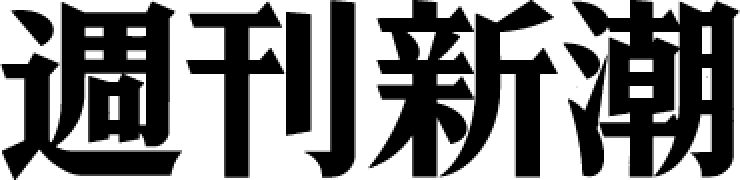

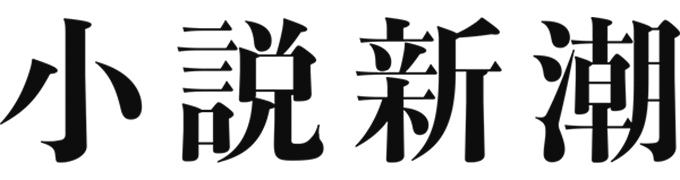
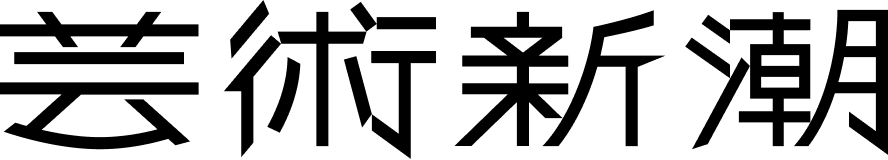
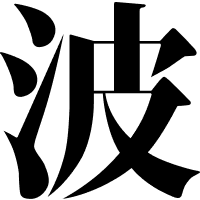
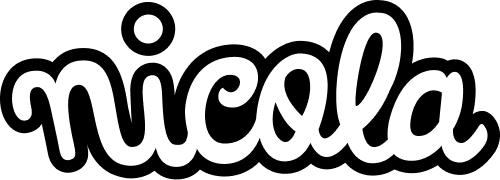
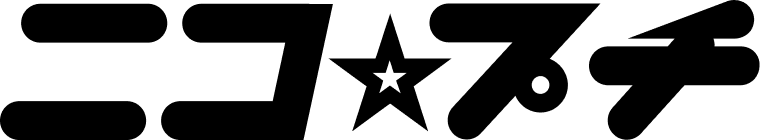
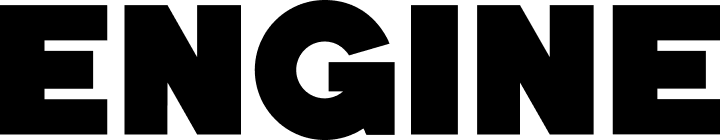
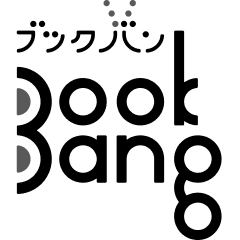
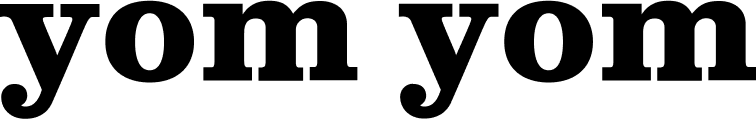
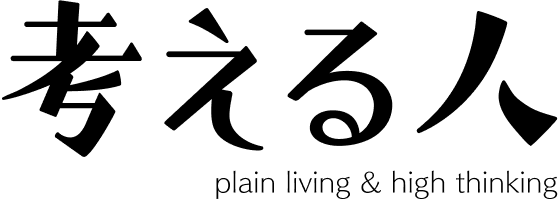
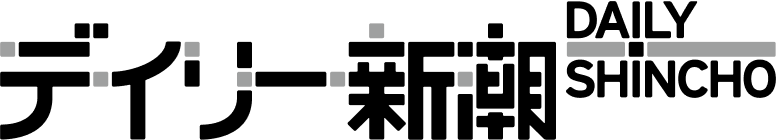
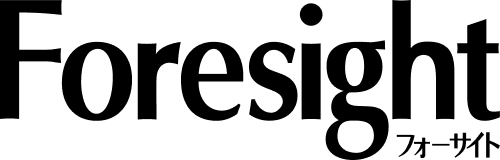
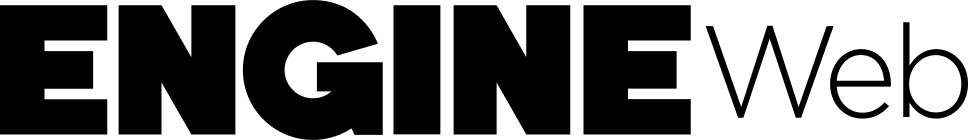
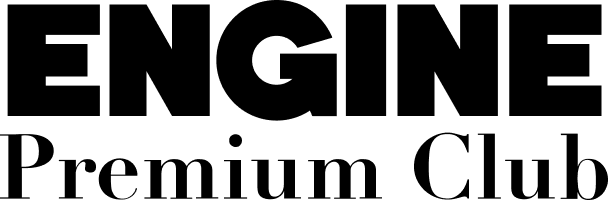

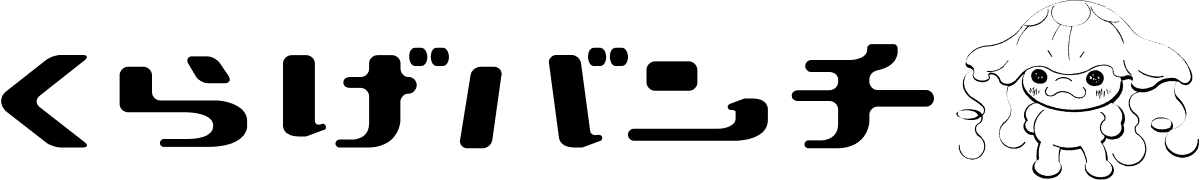



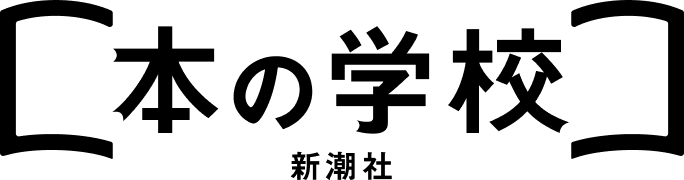
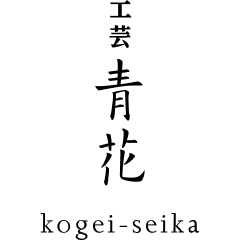
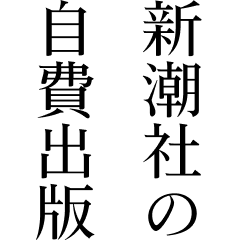
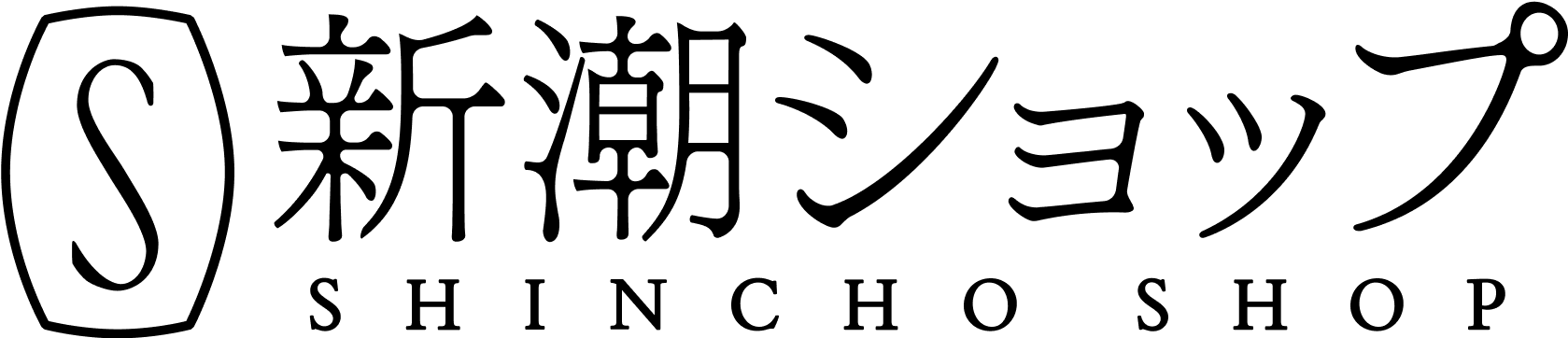

 公式X
公式X












