第22回 受賞作品
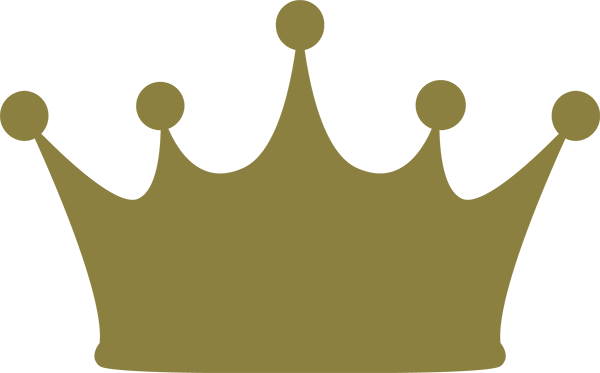 優秀賞受賞
優秀賞受賞

――この度は優秀賞の受賞、おめでとうございます。選考結果はどんな風にお聞きになりましたか。
その日はWBCの決勝があった日でした。午前に試合を見たあと、夕方に連絡をいただいたのでよく憶えています。正直、応募した当初は一次選考も通過できないと思っていたから、とにかく驚いてしまって……。ものすごい数の偶然が積み重なり、不思議な運が巡り巡って、賞をいただけたのだろうと思います。
――もともと本はたくさん読まれていたのでしょうか。
学生時代は先生の薦めであさのあつこさんの「バッテリー」シリーズを読んだり、学校の読書タイムで東野圭吾さんのミステリを読んだり、平均的な読書量だったと思います。本をたくさん読むようになったのは、数年前に引っ越しをしたことがきっかけでした。新居のすぐそばに新しい図書館ができて、そこへ行ってみたときに『オリバー・ツイスト』(ディケンズ著・中村能三訳)が目に入ったんです。題名は聞いたことがあるのにストーリーを知らないな、と洋画を選ぶような軽い気持ちで借りてみたら、これがなかなか読みすすめられなくて……。
だけどどこか気になるものがあり、何度か借り直してようやく読み切りました。そのときの達成感と物語への満足感が、読書への入口だったかもしれません。
もうひとつ、読書にハマるきっかけになったのは、谷崎潤一郎の『細雪』です。言葉遣いや文章そのものが面白く、そんな楽しみ方があるのかと圧倒されました。ストーリーだけでなく、日本語まで面白い、と言えばいいのでしょうか。リズムが楽しくて、心地よくて、驚きました。それ以来、もっといろんな人の作品を読んでみよう、と手を伸ばすようになりました。
――小説を書こうと思ったきっかけはなんだったのでしょうか。
一昨年の末にまた引っ越しをすることになって、そのときに心機一転新しいことをしてみたいと思いました。コロナや生活環境の変化などもあり、自分の意見を誰かに伝える機会が減る中で、他人と対峙しながらその場で紡ぐ言葉より、文字の形に思いを練り上げながら書く作業をしたくなったんです。そういうのが自分には合っているのかな、とも思いました。
最初は、夫に読んでもらおうと文章を書き始めました。その日実際にあった出来事を起点に、もしこんな風に展開したら面白いな、と思うことを物語として考えてみたのですが、実際に取り組んでみると、まったく書き上げられなくて……。結局箇条書きのようなものをもとに口頭で説明する形になってしまいました。それでも夫が面白がってくれたことは嬉しかったです。
――賞への応募はどの段階で目指されたのですか。
ちゃんとひとつの物語を完成させたいと思ったからです。夫に見せる文章は、繰り返すうちにそれらしくなってはきたものの、最終的には書きたいことを文字にし切れず、意図をあとで説明するなど甘えが生じていました。また、物語が浮かんで書き出しても、そのあとの流れを掴めないこともありました。小説を書くのはなんて難しいんだろうと思いましたね。
行き詰まって、ネットで小説の書き方にまつわる情報を探していたとき、R-18文学賞の編集者の方のインタビュー記事を見つけました。そこで、森見登美彦さんが「書く時間より直す時間を多く取るべき」とおっしゃっていたという話が出ていて、すごく腑に落ちました。当たり前かもしれないのですが、まずは書いてみて、そのあと何日もかけて何度も何度もしつこいくらいに読み返して書き直して、ゆっくりと完成に近づいていけばいい、と思えたらふっと力が抜けました。
同じインタビューには、R-18文学賞の選評が勉強になるとも書かれており、実際にHPで見てみるととても参考になりました。1行アキは多用しないほうがいいなど、なるほどと思うことがたくさんあり、それらを読み込むうちにこの賞に応募してみたいと思うようになりました。
――受賞作「鬼灯の節句」はどのようにして紡がれた作品なのでしょうか。
作中にも少し書いたのですが、幼い頃、ツバメのひなが蛇に食べられてしまう場面を目にしたことがありました。そのときはすごく残酷だなと怯えたのですが、人間も鶏や羊を食べるとき、若いほうが食べやすいということがあると思います。若くて柔らかいもの、抵抗の少ないもの、歯の立てやすいもの。そういう犠牲になりやすいものの上に成り立っている命がたくさんある。そういう思いや、その残酷さが身近なものに感じられたことが、物語としてでてきたのかもしれません。
沼を舞台にすることは最初から決めていて、祖母が靴箱の上で育てていた鬼灯も頭に浮かんでいました。鬼灯の季節を調べている折、その根が堕胎などにも用いられていたということを知って、自分の中で何かが繋がる感覚がありました。それこそR-18文学賞の過去の選評の中に「五感を使う」ということに関する言葉があり、自分の体験をベースにしながら、フィクションとして、紡いでいきたいと思って書き上げた作品です。
――今後はどんな風に創作の道を歩んでいきたいですか。
ラストについて、自分はこれが答えだと思って書いたけれど、後から読み返すと、これでよかったんだろうか、と不安になり、選考の結果を聞くまでずっと悩んでいました。あの結末を褒めていただけるのはすごく嬉しいのですが、その一方でいろんな考えの人がいるとも思います。万人に好かれるものを書くことはできずとも、書くからには覚悟をもたなくてはいけない、と強く感じました。
物語は、読む人がいて下さってこそ成り立つものだと思います。今後、作品を書く機会をいただけるなら、そういった読み手の方々のことをきちんと心にとめて、書いていきたいです。

