
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
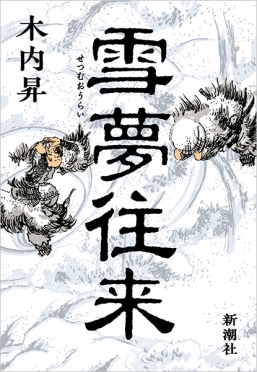
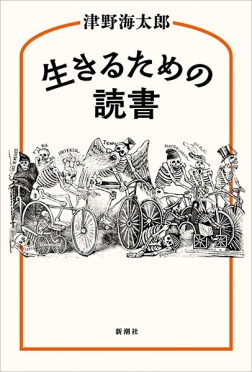
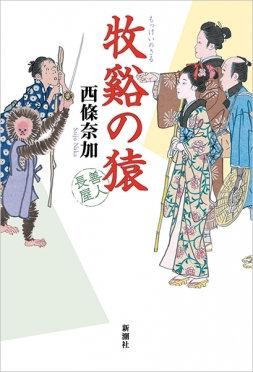

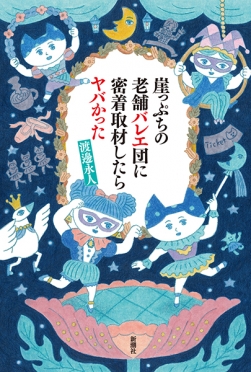
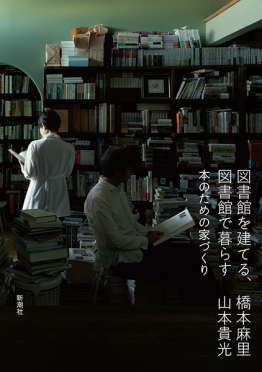
|
|||
| 〉新刊一覧 | |||
| 〉新潮社の本 | |||
|
|||
|
|||
|
|||

|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||

|
|||
|
|||
|
|||
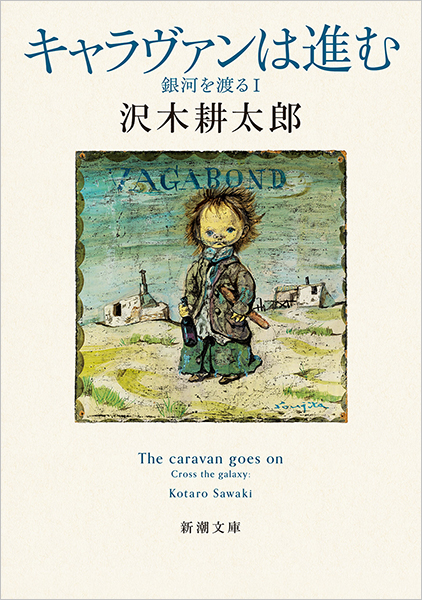
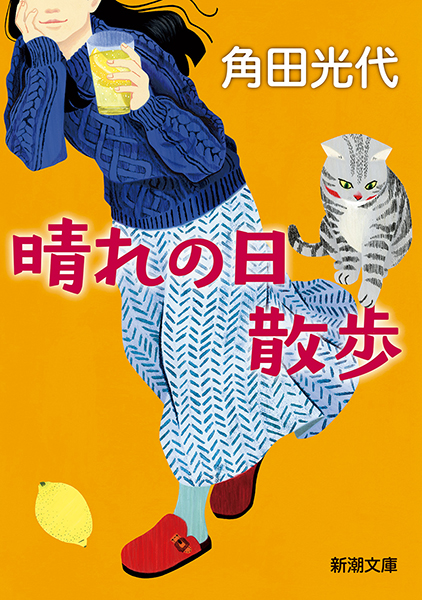
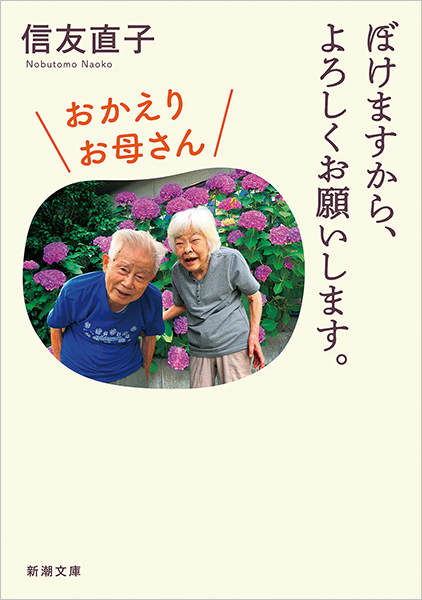


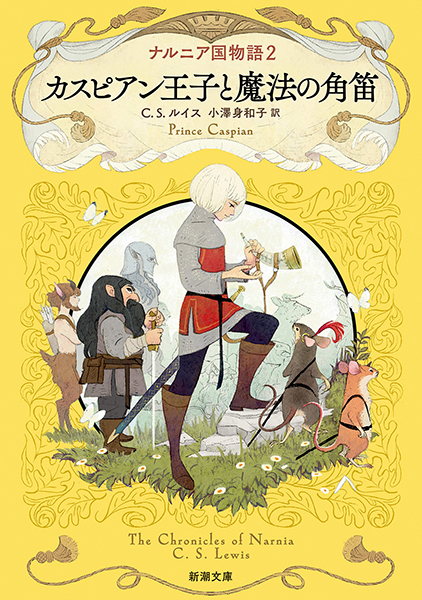


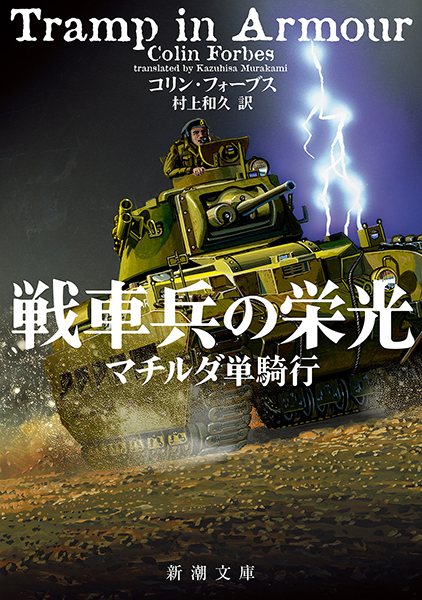
|
|||

|
|||
| 〉新潮文庫 | |||
|
|||
|
|||
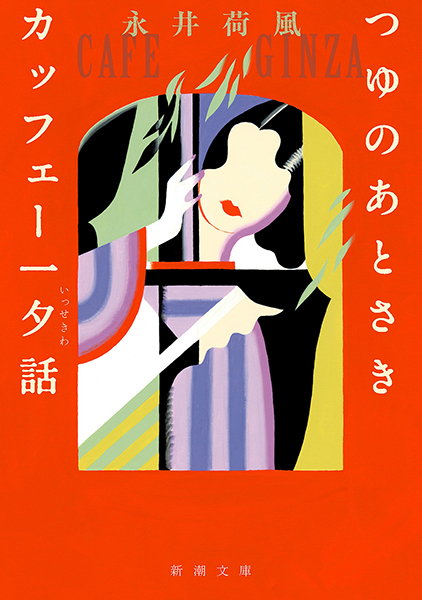
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
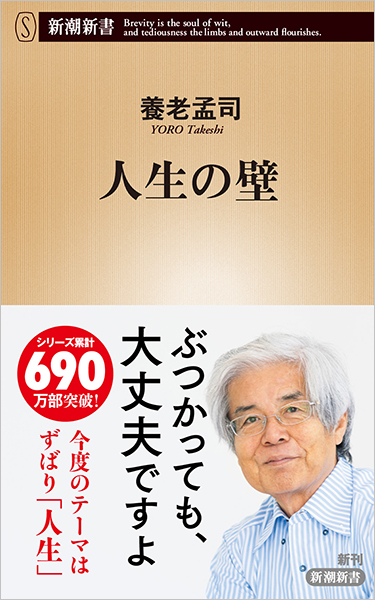
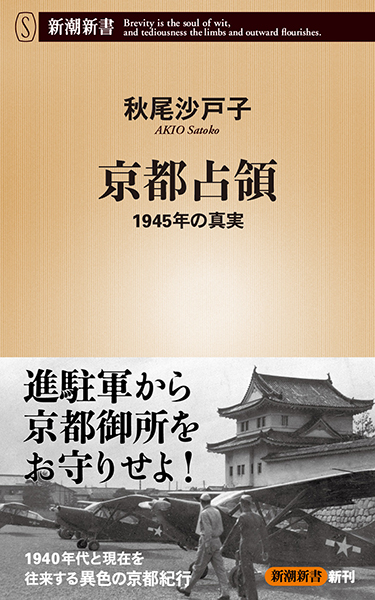
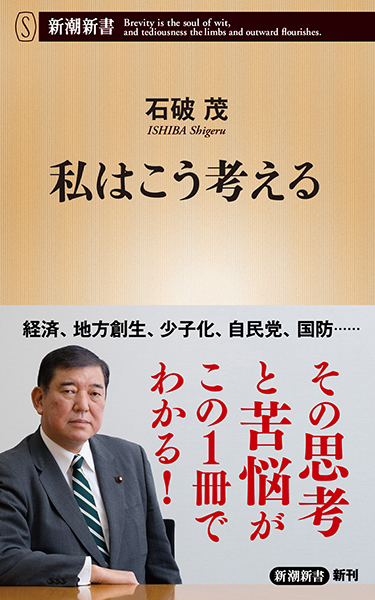
|
|||
| 〉新潮新書 | |||
|
|||
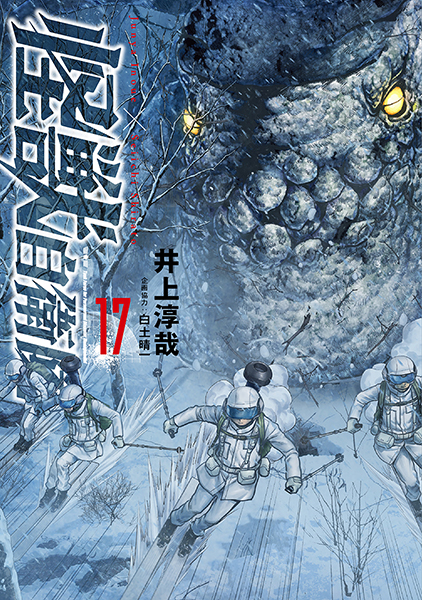
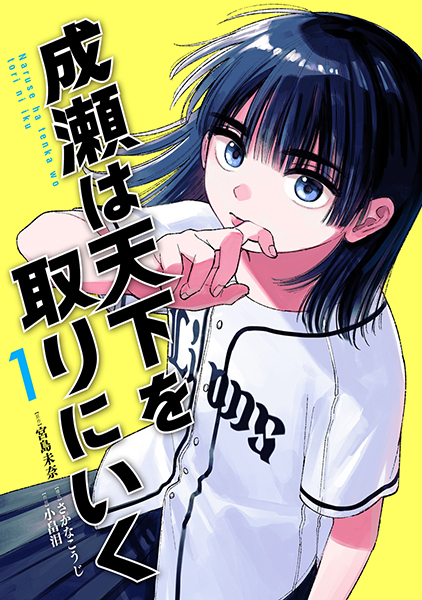

|
|||
| 〉コミックバンチKai | |||
| 〉くらげバンチ | |||
|
|||
|
|||

|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
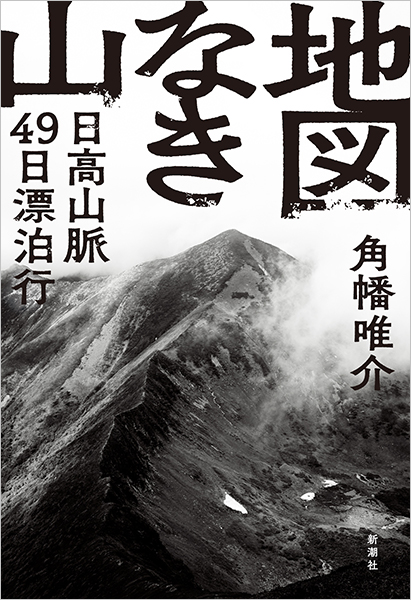
|
|||
|
|||
|
|||
 波 2024年12月号 より |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||

|
|||
|
※メールマガジンの登録・退会は、「情報変更・配信停止」から行ってください。 ※弊社から配信している全メールマガジンの一括登録解除はこちらから行ってください。 Copyright(c), 2024 新潮社 無断転載を禁じます。 発行 (株)新潮社 〒162-8711 東京都新宿区矢来町71 新潮社読者係 03-3266-5111 |
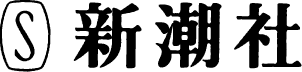
|

