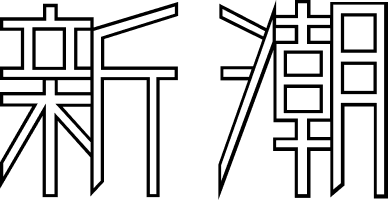光の場、電子の海―量子場理論への道―
1,815円(税込)
発売日:2008/10/24
- 書籍
ミクロの究極に迫った20世紀物理学の流れが一望のもとに!
量子場理論とは、量子力学の完成形である。物理学専攻の大学院生でさえ理解が容易ではないという超難解な理論を、本書はあくまで一般読者のために、明快に解説してみせる。20世紀の天才科学者たちは「物質とは何か」という謎をどう解明してみせたのか? その思考の筋道が、文系人間にも理解できる画期的な一冊!
書誌情報
| 読み仮名 | ヒカリノバデンシノウミリョウシバリロンヘノミチ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮選書 |
| 発行形態 | 書籍 |
| 判型 | 四六判変型 |
| 頁数 | 256ページ |
| ISBN | 978-4-10-603622-4 |
| C-CODE | 0342 |
| ジャンル | 物理学 |
| 定価 | 1,815円 |
書評
物の理を楽しむための物理学の真髄
ぼくはかつて物理少年だった。物理学者ラザフォードの伝記を読んだことが大きなきっかけだったと記憶している。まるで恐竜おたくが恐竜の学名をそらんじるように、α崩壊とかβ崩壊を口にする中学生だった。ただしその後、ハードサイエンスから生き物を扱うソフトサイエンスに転向したのだが。
ともかくも、いっぱしの物理少年として物理学のポピュラーサイエンスを読みふけりはしたが、なぜか量子論までは行き着かなかった。その後も朝永やファインマン、ダイソンらのエッセイ風の文章には親しみつつも、彼らの業績をもっと詳しく知りたいという思いにはならなかったのだ。
その理由の一端は、天才科学者たちが積み上げてきた知の体系をつまみ食いすることへのためらいだったかもしれない。単なる科学者列伝や、アナロジーだらけの「解説書」では、壮大な知的体系を楽しむことはできない。かといって、大著を通読できるほどの根性もなかった。
しかし今回、本書を読んだことで、胸のつかえが降り、話の筋道が自分なりに明瞭に見えてきた。それと同時に、理論物理学というものに対する少年時代の刷り込みが、稚拙で中途半端なものだったことも思い知らされた。
これまでぼくは、ボーア、シュレディンガー、ハイゼンベルクなど綺羅星のごとき物理学者は、それぞれ完璧な論理展開を基に、既知のデータに裏付けられた緻密な理論を提唱し、それが新たな実験で実証され定着していくことで、現代物理学は進んできたとばかり思い込んできた。なればこそ「ハード(厳密)」なサイエンスなのではないかと。ところが本書を読むと、彼らもまた、極端な話、思いつきとこじつけというきわめて人間くさい営為として科学理論を紡いでいたことがわかる。そのあたりの経緯と背景について、原著論文を読み込んだ著者の筆致は大いに読ませる。
また、これまで量子的という言葉の意味が今ひとつ腑に落ちていなかったが、電子の安定な軌道は離散的でしかも整数倍になっていると仮定しないと実験データに合致しないことから量子論が誕生したといういきさつには、目を見開かされた。マーカス・デュ・ソートイの『素数の音楽』で、素数論と素粒子論がひょんなところで結びつきつつあるという件を読み、茫漠としたつながりの不思議に静かに感動した思いがよみがえった。
本書の真骨頂は、量子場理論の誕生へと至る道筋である。量子力学から素粒子論への展開は量子場という概念なくしてはありえなかったことがよくわかる。奇しくも南部陽一郎、益川敏英、小林誠の各氏のノーベル物理学賞受賞が、本書の主旨の正しさを実証することになった。超ひも理論や多次元宇宙などを論じた海外のベストセラーが日本でも売れている。しかし、そうした本に走る前に、まず本書こそ読まれるべきだろう。
(わたなべ・まさたか サイエンスライター)
波 2008年11月号より
立ち読み
はじめに
多くの科学史家は、1926年を、物理学の転換点となる画期的な年だとしている。この年、シュレディンガーによる波動力学とハイゼンベルクらによる行列力学の同等性が証明され、両者を総合した「量子力学」が完成したと言われるからだ。しかし、本当にそうなのだろうか?
量子力学は、半導体・レーザー・原子核などさまざまな分野に応用され、現代の科学技術文明を支える基礎理論となっている。こうした応用の際に必要となる道具立てのほとんどが1926年までに出揃ったので、確かに、この時点で量子力学の枠組みが確立され、これ以降は、できあがった理論を応用する時代に入ったと見ることもできる。
だが、当時の物理学者にそうした自覚があったとは思えない。水素原子の構造に関する予測は測定データと高い精度で一致していたので、量子力学が“役に立つ”理論であることは間違いなかったが、自然の謎を究明しようと奮闘してきた人たちにとって、1926年当時の量子力学は、まだまだ未熟な理論だったはずだ。
「量子」のアイデアは、波動だと思われていた光がときには粒子のように振舞い、逆に、典型的な粒子であるはずの電子がときに波動のように振舞うという認識に由来する。ところが、1926年版の量子力学では、光は理論の枠組みに取り入れられておらず、電子も、実体は粒子でありながら、その運動の仕方が波動方程式に従うという曖昧な形でしか定式化できなかった。量子力学とは、その大仰な名称とは裏腹に、単なる「粒子の量子論」にすぎないのである。
こうした状況に飽きたらない研究者たち(特に、ディラック、ヨルダン、パウリ、ハイゼンベルク)は、1926年以降も理論の改良を続け、遂に、一つの完成形を作り上げる。これが、粒子ではなく場を量子論的に扱う量子場の理論である。量子場の理論では、電子と光が同じ理論形式で記述されており、どちらも粒子と波動の二重性を示す理由が不自然でない形で示された。
量子場の理論の最大の障害は、数学的な扱いがきわめて難しい点である。この理論の形式は1929年に提案されるが、当初は信頼できる計算がほとんどできなかった。曲がりなりにも計算できるようになるのは、第二次世界大戦終結後の1940年代末であり、数学的な定式化がほぼ完成するのは、ようやく1960年代になってからである。しかも、計算がどうしようもなく難しいにもかかわらず、量子場の理論は、技術的な応用には全くといって良いほど役に立たない。半導体の設計や新素材の開発を行うには、1926年版の量子力学さえ使えれば充分なのである。大学教育で量子場にほとんど目が向けられないのは、そのためである。
とは言っても、量子場の理論が、科学的な自然理解の極致であり、人類の英知の到達点であることは確かである。たとえ何の役に立たなくとも、そこに示される物理世界の驚くべき姿をかいま見ることは、心を豊かにしてくれる体験ではないだろうか。
さらに、量子場の理論を視野に収めることは、ミクロの究極に迫ろうとした20世紀物理学史の全体像を理解する上でも、非常に重要である。これまで、1926年までの量子力学の形成史と、1960年代以降の素粒子論の進展は、別個に語られることが多かった。しかし、この2つを量子場の理論というミッシング・リンクでつなぐならば、体系的な理論と知的な直観に基づいて探究を進めた物理学者たちの努力の跡が、一筋の太い線となってはっきりと見えてくるはずだ。
こうした観点から、本書では、物理学の専門的な知識のない人を対象に、量子場の理論の解説を試みる。入門書の常道に従って歴史を辿っていくが、関連する話題を全て取り上げるのではなく、量子場理論に至る道程が明確になるように、粒子と波動の二重性という問題を常に中心にして話を進めていく。
まず序章で、粒子的な原子と波動的な場から世界が構成されるという19世紀の二元論的な見方を紹介する。第1章から20世紀に入り、粒子・波動の二重性が現れる最初のケースとしてアインシュタインの光量子論を取り上げる。続いて、第2章で、ニュートン以来の古典物理学では説明できない現象として原子の安定性に触れ、第3章で、それを解決する理論として、電子を波動と見なすシュレディンガーの波動力学を紹介する。第4章では、ハイゼンベルクらによる行列力学について述べるが、細かい点は省略して、量子条件と不確定性原理に焦点を絞ることにする。
これに続くのが本書の主要部である。第5章と第6章で、量子場の理論への突破口を切り開いたディラックの業績(電磁場の量子化と相対論的電子論)について紹介し、第7章で、量子場理論の最も正統的な形式であるハイゼンベルクとパウリによる量子電磁気学を取り上げる。
さらに、第8章で具体的な計算を可能にした朝永振一郎らのくりこみ理論を紹介し、終章では、素粒子論の発展と標準模型を総括する。
量子論の歴史を解説した書物は巷に溢れているが、多くの場合、1926年に理論形式が完成するというシナリオに合致するように、後知恵によって研究成果を解釈し直している。本書では、そうした後知恵を用いず、研究を実施した時点で科学者たちがどのように考えていたかを、論文から読みとれる限り明らかにしていく。その方が、なぜ量子場という概念が必要になるかが理解しやすいからである。
また、数学の知識があまりない読者を想定して、多項式や分数式より難しい数式は極力使わないことにした(波動関数の説明のために、1箇所だけ三角関数を使ったが)。ただし、これでは説明があまりになおざりになってしまうので、数式を用いた説明がほしい人のために、「もっと深く知りたい人のための注」を付けておいた。理工系の読者は、できれば目を通すようにしていただきたい。
量子場の理論は難解である。だが、その内容をある程度まで理解したとき、人は驚きと喜びを禁じ得ないだろう。世の中には、不確定性原理やシュレディンガーの猫といった話題を取り上げて、量子力学の不思議さを吹聴する書物が少なくないが、量子場の理論を学ぶと、そうした軽薄な騒ぎに巻き込まれることが恥ずかしくなるだろう。この理論は、それほどにも深遠である。
量子論がわからないと嘆く人、量子論などマスターしたと思いこんでいる人は、是非、本書に目を通してほしい。
担当編集者のひとこと
20世紀物理学の真髄が、あなたにも理解できる。
ご存じのように、今年のノーベル物理学賞は三人の日本人に与えられました。でも、彼らの業績のどこがノーベル賞ものなのか、新聞の解説記事を読んだだけでは腑に落ちません。わかったようで、じつは全然わからない。いきなり「素粒子の標準模型」と言われても困ってしまいますし、そもそも「素粒子」とは、その言葉からイメージされるような極小の「粒」ではないのですから。
では、素粒子とは何か? これをきちんと理解するためには、「素粒子の標準模型」の基礎となった「量子場理論」を知らなければ話が始まりません。とはいえ、この量子場理論は、物理学専攻の大学院生にとってさえ理解が容易ではないシロモノ。本書は、そんな超難解な理論を、あくまでも一般読者のために解説してみせました。20世紀の天才科学者たちは、いかにして自然のミクロな究極に迫り、「物質とは何か」という謎を解き明かしたのか? 理系思考の究極ともいうべき20世紀物理学の発展の筋道が、文系読者にも一望のもとに見渡せるようになる、画期的な一冊です。
2008/10/24
キーワード
著者プロフィール
吉田伸夫
ヨシダ・ノブオ
1956年、三重県生まれ。東京大学理学部物理学科卒業、同大学院博士課程修了。理学博士。専攻は素粒子論(量子色力学)。東海大学、明海大学で非常勤講師をつとめながら、科学哲学や科学史をはじめ幅ひろい分野で研究を行なっている(ホームページ「科学と技術の諸相」参照)。著書に『宇宙に果てはあるか』『光の場、電子の海』(いずれも新潮選書)、『日本人とナノエレクトロニクス』(技術評論社)などがある。