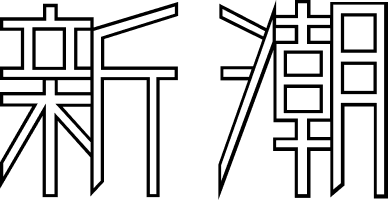青い鳥
2,090円(税込)
発売日:2007/07/20
- 書籍
先生はうまくしゃべれない。だから、“たいせつなこと”しか言わない――。涙を超えたほんものの感動に出会える最新作!
村内先生は中学の非常勤講師。国語教師なのに吃音を持つ先生の、一番大切な仕事は、ただ「そばにいること」。「ひとりぼっちじゃない」と伝えること。いじめ、自殺、学級崩壊、児童虐待……子どもたちの孤独にそっと寄り添い、だからこそ伝えたい思いを描く感動作。すべての中学生、中学生だったすべての大人に捧げる救済の書。
目次
ハンカチ
ひむりーる独唱
おまもり
青い鳥
静かな楽隊
拝啓ねずみ大王さま
進路は北へ
カッコウの卵
ひむりーる独唱
おまもり
青い鳥
静かな楽隊
拝啓ねずみ大王さま
進路は北へ
カッコウの卵
書誌情報
| 読み仮名 | アオイトリ |
|---|---|
| 雑誌から生まれた本 | 小説新潮から生まれた本 |
| 発行形態 | 書籍 |
| 判型 | 四六判変型 |
| 頁数 | 328ページ |
| ISBN | 978-4-10-407507-2 |
| C-CODE | 0093 |
| ジャンル | 文芸作品、文学賞受賞作家 |
| 定価 | 2,090円 |
書評
波 2007年8月号より 読み手の胸で生き続ける一人の教師 重松 清『青い鳥』
村内先生、村内先生。心でそっと呼んでみる。祈りにも似た想いをこめて――。本書は、吃音の国語の臨時講師、村内先生と、彼の赴任先での生徒とのドラマを描いた連作短編集である。臨時講師であるから、村内先生は渡り鳥のように中学を転々とする。そして、彼の赴任先には、抱えきれない重い石を心にひそませている生徒がいる。村内先生は、そういう子のためにやってくるのだ。
ここでは、実に様々な子どもたちの抱えた“重い石”が描かれる。ある子どもは、ポケットに入れたハンカチを握り締めることでしか、自分自身を保っていられない。巧妙ないじめによって、「学校にいるときと、学校の友だちと一緒のときと、学校のことを考えているときだけ」しゃべれなくなってしまう、場面緘黙症を患ってしまったのだ。
自分でもわけが分からないままに、担任の教師を発作的に刺してしまった子どもがいる。陽気で明るくノリのいい先生が、自分のことを扱いづらく感じていたことは分かっていたけれど、そのことで先生を嫌っていたわけでも、恨んでいたわけでもない。どうしてそんなことをしたのか、自分が一番分からないのだ。でも、自分がしてしまったことでますます自分の居場所を無くしてしまった、そんな子どもがいる。
私立の受験に失敗して、自分の周りにプライドという壁を高く築き上げることでしか、自分を守れない子どもがいる。自分に都合のいい「帝国」の中に君臨することで、自分を納得させることしかできないその子は、でも本当は淋しい。彼女が見下している友だちたちより、本当はずっとずっと淋しい。淋しいから、誰かを攻撃せずにはいられないのだ。
本書には、沢山の子どもたちの“重い石”が描かれる。読んでいて、そのあまりの重さに、胸が塞がれる。彼らが抱えるものがリアルに迫ってくればくるほど、では、彼らをそこまで追い詰めたのは誰なのか、何なのか、という作者からの無言の問いかけがくっきりと立ち上がってくる。
ここまで彼らを追い詰めた原因は、社会でも文科省でもない。原因の一因ではあるかもしれないが、根本的なことではない。彼らを追い詰めたのは、私たち大人だ。大人である私たちが、彼らにこんなものを抱えさせてしまったのだ。そのことに対する忸怩たる思いに、いたたまれなくさえなる。
とはいえ、本書は大人を糾弾するための物語ではない。村内先生という一人の教師は、彼にしかできないアプローチの仕方で、子どもたちの“重い石”と向き合う。それによって子どもたちが救われていく、という八編の物語を通じて、作者が一番伝えたかったことは、大人たちに、今そこにある子どもたちの危機にちゃんと気づいて欲しい、ということなのだと思う。それと同時に、「(そんな子どもたちを)救おうと思えばまだ間に合う」のだ、ということなのだと思う。その一つの方法論として、村内先生が、いる。
石の重さで、今にも沈んでいきそうな子どもたちに、村内先生は言う。「間に合ってよかった」と。君と出会えたからよかった、と。前述の私立の受験に失敗した女の子は、例によって村内先生を「つぶし」にかかる。その時、村内先生が彼女に言うのだ。
「先生に、でででっ、できるのは、みんなのそばにいる、こっことだけ、ででででっ、でっ、です」と。そして、続けて言うのだ。先生がほんとうに、答えなければいけない生徒からの質問は、わたしはひとりぼっちですか、という質問だけである、と。その答えは一つしかない、と。先生がそばにいることが、答えなのだ、と。
私はこのくだりで、ぼろぼろ泣いてしまった。先生、という言葉を、「親」に代えて、いや、「大人」に代えて、一人でも多くの人に、この言葉を読んで欲しい、と思う。読んで、そして忘れないで欲しいと思う。現実にも村内先生はいて欲しい。どこかにいて欲しい。でも、もっと大事なのは、この物語を読んだ私たち一人一人が、村内先生たらんとすることなのだと思う。
ここでは、実に様々な子どもたちの抱えた“重い石”が描かれる。ある子どもは、ポケットに入れたハンカチを握り締めることでしか、自分自身を保っていられない。巧妙ないじめによって、「学校にいるときと、学校の友だちと一緒のときと、学校のことを考えているときだけ」しゃべれなくなってしまう、場面緘黙症を患ってしまったのだ。
自分でもわけが分からないままに、担任の教師を発作的に刺してしまった子どもがいる。陽気で明るくノリのいい先生が、自分のことを扱いづらく感じていたことは分かっていたけれど、そのことで先生を嫌っていたわけでも、恨んでいたわけでもない。どうしてそんなことをしたのか、自分が一番分からないのだ。でも、自分がしてしまったことでますます自分の居場所を無くしてしまった、そんな子どもがいる。
私立の受験に失敗して、自分の周りにプライドという壁を高く築き上げることでしか、自分を守れない子どもがいる。自分に都合のいい「帝国」の中に君臨することで、自分を納得させることしかできないその子は、でも本当は淋しい。彼女が見下している友だちたちより、本当はずっとずっと淋しい。淋しいから、誰かを攻撃せずにはいられないのだ。
本書には、沢山の子どもたちの“重い石”が描かれる。読んでいて、そのあまりの重さに、胸が塞がれる。彼らが抱えるものがリアルに迫ってくればくるほど、では、彼らをそこまで追い詰めたのは誰なのか、何なのか、という作者からの無言の問いかけがくっきりと立ち上がってくる。
ここまで彼らを追い詰めた原因は、社会でも文科省でもない。原因の一因ではあるかもしれないが、根本的なことではない。彼らを追い詰めたのは、私たち大人だ。大人である私たちが、彼らにこんなものを抱えさせてしまったのだ。そのことに対する忸怩たる思いに、いたたまれなくさえなる。
とはいえ、本書は大人を糾弾するための物語ではない。村内先生という一人の教師は、彼にしかできないアプローチの仕方で、子どもたちの“重い石”と向き合う。それによって子どもたちが救われていく、という八編の物語を通じて、作者が一番伝えたかったことは、大人たちに、今そこにある子どもたちの危機にちゃんと気づいて欲しい、ということなのだと思う。それと同時に、「(そんな子どもたちを)救おうと思えばまだ間に合う」のだ、ということなのだと思う。その一つの方法論として、村内先生が、いる。
石の重さで、今にも沈んでいきそうな子どもたちに、村内先生は言う。「間に合ってよかった」と。君と出会えたからよかった、と。前述の私立の受験に失敗した女の子は、例によって村内先生を「つぶし」にかかる。その時、村内先生が彼女に言うのだ。
「先生に、でででっ、できるのは、みんなのそばにいる、こっことだけ、ででででっ、でっ、です」と。そして、続けて言うのだ。先生がほんとうに、答えなければいけない生徒からの質問は、わたしはひとりぼっちですか、という質問だけである、と。その答えは一つしかない、と。先生がそばにいることが、答えなのだ、と。
私はこのくだりで、ぼろぼろ泣いてしまった。先生、という言葉を、「親」に代えて、いや、「大人」に代えて、一人でも多くの人に、この言葉を読んで欲しい、と思う。読んで、そして忘れないで欲しいと思う。現実にも村内先生はいて欲しい。どこかにいて欲しい。でも、もっと大事なのは、この物語を読んだ私たち一人一人が、村内先生たらんとすることなのだと思う。
(よしだ・のぶこ 文芸評論家)
著者プロフィール
重松清
シゲマツ・キヨシ
1963(昭和38)年、岡山県生れ。出版社勤務を経て執筆活動に入る。1991(平成3)年『ビフォア・ラン』でデビュー。1999年『ナイフ』で坪田譲治文学賞、同年『エイジ』で山本周五郎賞を受賞。2001年『ビタミンF』で直木賞、2010年『十字架』で吉川英治文学賞、2014年『ゼツメツ少年』で毎日出版文化賞を受賞。現代の家族を描くことを大きなテーマとし、話題作を次々に発表している。著書は他に、『流星ワゴン』『疾走』『その日のまえに』『きみの友だち』『カシオペアの丘で』『青い鳥』『くちぶえ番長』『せんせい。』『とんび』『ステップ』『かあちゃん』『ポニーテール』『また次の春へ』『赤ヘル1975』『一人っ子同盟』『どんまい』『木曜日の子ども』『ひこばえ』『ハレルヤ!』『おくることば』など多数。
判型違い(文庫)
この本へのご意見・ご感想をお待ちしております。
感想を送る